『エクソシスト』が(スティーヴン・キング曰く)「親から見た子どもの異物感」なら、『ヴィジット』は「孫から見た曾祖母世代の異物感」だったのかな。
シャマラン『ヴィジット』について
「不可能」をいつから日本人が使っていたかということに関して
僕は明治大正の本を日々読み漁ってるすごい人ではないので、以下はすべてインターネットで調べたことです。
江戸期
「不可能」という組み合わせ自体は漢籍を輸入する過程で江戸時代にはもう日本人の目に触れていたらしく*1、日本人儒学者の山井崑崙(鼎)が中国古典の比較考証を行い、後に荻生北渓*2によって校訂された『七経孟子考文』にも「不可能」の文字が見える。
自分は江戸時代の漢文を読めるほど学も知性も高くないので、果たしてこれが山井が書いた文なのか、北渓が打った注の一部なのか、そもそも中国古典*3の原文にあったものなのかはわからない。*4ただ、すくなくとも仏教や儒学に通じたインテリ層は「不可能」という単語をこのころから目にはしていたのである。
明治前半
明治以降はどうなのか、という話になると、google先生が言うには確認できるもので一番古い用例は当時の外務省が発行していた外交報告書『大日本外交文書』の十三巻(明治十三年)で、そこにはふつーに「不可能ナリ」とか書かれていたらしい。
らしい、というのは原文をあたっての確証を得られていないからで、『大日本外交文書』は外務省によって全巻全文のデジタルアーカイブを公開されているのだが、テキスト化されていないため、膨大な資料をちまちま読んでいるうちに「何が条約改正だ!!!!!!しね!!!!!!」みたいな気分になってくる。そりゃあ志々雄様も国崩しに走るわけだ。
グーグル先生もグーグル先生で謎の OCR技術によって用例を探しだしてくれるぶんには素晴らしいのだが、『学問のススメ』に含まれている「𠃍*5能ワズ」を拾ってきて「『可能』ですよ! コレ!」と喜々として差し出してくるくらいにはバカ犬なので、全面的には信用できない。せめてグーグルで全文読めればなとも思うんだけど、著作権者(この場合は外務省?)の許可が降りないとかなんとかいいわけして見せてくれない。しかしいちいち1000ページ近い明治初期の文章を読んでいく*6のも大変なのでこのへんはがんばれない。
まあたぶん、漢籍古典に通じたインテリ層が明治政府にも登用されて文書を書いていた、みたいな流れがあったんだと思う。たぶんだけど。
だけど一方で、「不可能」が普段使いされていなかったのは事実のようだ。明治元年に編まれた日仏辞典『Dixtionnaire Japonais-Francais』には「可能」も「不可能」も見当たらない*7。同じ辞書では、孔多さんによると、明治二十一年の英和辞典『和訳字彙:ウェブスター氏新刊大辞書』にも明治十九年の日本語辞典『言海』にも載っていない。
明治後半
「不可能」が今に残る文学作品に登場するのは時代が下って 明治三十年代からだ。
青空文庫でざらり調べたかぎり、一番早く「不可能」を作文に使ったのは僧侶である清澤滿之で、彼は亡くなる直前の明治三十六年に雑誌『精神界』に発表した文で、「若し眞面目に之を遂行せんとせば、終に「不可能」の歎に歸するより外なきことである。私は此「不可能」に衝き當りて、非常なる苦みを致しました。若し此の如き「不可能」のことの爲に、どこ迄も苦まねばならぬならば、私はとつくに自殺も遂げたでありませう。」などとやたら「不可能」をフィーチャーしている。わざわざカッコでくくるくらいだから、珍しい単語とみなされていたのかもしれないし、清澤的にはいっそ自分の造語くらいに考えていたのかもしれない。
その次に使ったのもやはり仏教学の大家、井上円了。明治三十八年の「妖怪談」で「全く不可能でございます」と、いかにも気張りのないフツーの使い方をしている。
仏教外の人間としては、夏目漱石が『中学文芸』によせて学生時代の思い出を語ったエッセイ「落第」(明治三十九年)で「今の日本の有様では君の思って居る様な美術的の建築をして後代に遺(のこ)すなどと云うことは迚(とて)も不可能な話だ」と述べている。*8
用例は明治四十年代になると爆発的に増える。
もしかすると、明治四十年に発表された田山花袋の『蒲団』が契機だったのかもしれない。正宗白鳥が『文壇五十年』に書いてるところによると『蒲団』は「一種の革命宣言」みたいな衝撃が当時はあって、信者もアンチもこぞって影響を受けていたらしい。小説家がこぞって『蒲団』を読みこむうちになんとなく頭に「不可能」という単語がすりこまれていった、と考えるのは九割九分まちがっているだろうけれど、想像するだけならたのしい。
森鴎外も明治四十一年に「不可能」を見出すや、使い勝手のよさを気に入ったのか、その後、『雁』、『青年』、『独身』といった明治四十年代の自作に「不可能」を使いまくっている。
それよりひとつ下ふたつ下の世代の作家たちになるともうなんのてらいもない。
坂口安吾に至っては明治黎明期を舞台に勝海舟を主人公にすえた『明治開化安吾捕物帖』で「不可能」「不可能」と連発している。明治三十九年生まれの安吾にとって「不可能」を勝海舟が口にするのになんの違和感もなかったということだ。
事ほど左様に、日本語において不可能は可能化されてきたわけですね。
*1:日本に輸入されたという清の『欽定古今圖書集成』からも「不可能」が検出される
*2:荻生徂徠の弟。ちなみに山井は徂徠の弟子だったんそうである。へー。
*4:「子曰」とあるので、原典からの引用である可能性が一番高い気がする
*5:「事」の略字。
*6:もしかしたら十三巻以外も読まないといけないかもしれない
*7:「説明(expliquer)できないこと」として「不可説」というのは載っていた。「不可説」は仏教の用語(可算数字として最上級の単位)であるので、日本人には昔から馴染みぶかかったんだと推察される
*8:漱石の弟子である科学者にして俳人・寺田寅彦のエッセイのなかでも「不可能」という言葉が頻用される。師匠から教えられて学んだのか、その逆なのか、どちらでもないのか
No country for Any man――『ビースト・オブ・ノー・ネイション』
原題: Beats of No Nation
監督: キャリー・ジョージ・フクナガ
製作年・国: 2015・米

NETFLIX 製作映画第一弾。
そのまま映画でも使われた原作小説のタイトルの元ネタは、アフロ・ビートのパイオニア、フェラ・クティが一九八九年に発表したアルバム『Beast of No Nation』
Fela Kuti - Beasts of No Nation
舞台は西アフリカのどこか*1。内戦の続く国の非武装中立地帯に住む少年アグー(エイブラハム・アタ)は温かい家族に囲まれ、比較的おだやかに暮らしていた。が、そんなある日、首都でクーデターが勃発し、暫定政権が樹立。情勢が変わって彼の住む街へも政府軍が進駐してくる。母と妹はヒッチハイクで首都へと避難し、アグーは兄や父らとともに街に残ることに。「先祖代々の土地である街を守るぞ」息巻く地元住民だったが、銃で武装した軍隊になすすべもなく虐殺されていく。父、兄、祖父も政府軍に捕まり、反乱軍と勘違いされ処刑の憂き目に。アグーだけは父と兄の助けで命からがらジャングルの闇の奥へと逃げこむが、そこでも反乱軍ゲリラに捕まってしまう。
「指揮官」と呼ばれる部隊長(イドリス・エルバ)の前にひきずりだされたアグーは、家族を政府軍に奪われたことを告白。「指揮官」は「今日から俺が一人前の兵士に育ててやる。親父の仇をとるんだ」とアグーをゲリラへ入隊させる。少年兵となったグーの地獄巡りがはじまる。
と筋だけ説明すると、『ジョニー・マッド・ドッグ』じゃん、と思われるかもしれない。どっちもエキストラや脇役*2に内戦経験者・元少年兵*3を起用してリアル感を出そうとするあざとさも似ている。けれど両者のストーリーを比較してみるとむしろ違いが際立ってくる。
『ジョニー・マッドドッグ』は理不尽な世間に振り回される一少年の目線とドキュメンタリックなリアルさ*4に徹していたが、『ビースト・オブ・ノーネイション』はマフィア映画的な「ファミリーの盛衰」の話としての側面を持つ。
「指揮官」はちょっとしたカリスマで、行き場のない人間を集めて「俺たちは家族だ」と言いつつも容赦なく使い捨てては悪どく成り上がっていき、最後には自分の慾望に呑まれて何もかも失ってしまう。ちょっと『スカーフェイス』っぽい。また、『ジョニー』では主人公ジョニーの拠り所として少女との淡い恋愛関係が描かれていたが、それを本作では戦友である少年兵との絆に置きかえている。ホモソーシャルに振れているというか、全編を通じて女性は売春窟や戦闘の中でレイプされる存在でしかない。
ちゃんとした軍隊を描いたドラマよりも、本当にそこ以外行き場のないぶん、「家族」感が強い。だけど、けっして幸せな家族じゃない。「指揮官」は「俺たちは家族だ」という言葉を連発するけれども、それは彼の野望を達成するためのアジにすぎない。ブラック企業の経営者みたいなものだ。「俺は親だから子どもであるお前をを守る。だから、子どもであるお前も親を守るのが義務だろ?」なんて平気で言う。そのうさんくささをアグーは敏感に嗅ぎとる。
だからこそ、というべきなのか、アグーは母の面影を求めて戦場を彷徨い、「指揮官」の「家族」にどこかノれないからこそ神様に祈る。だが神は祈りを聞き入れてはくれない。アグーは太陽を呪う。「あなたを掴み、この手で光をすべて絞りだしてやりたい。そうすれば、ずっと夜になるから」。
ヴォイス・オーヴァーで語られるアグーの内面はかなり詩的だ。親が教師で熱心なキリスト教徒だったためかわからないが、彼のこの独白のおかげで真に迫ったドキュメンタリックなタッチとはまた違ったレイヤーで、どこか観念的で幻想的な雰囲気を醸し出される。
それはもちろん、キャリー・フクナガの作家性によるものなんだろう。ある種の魔術感・幻想性みたいなものは撮影にも色濃く出ている。丈の高い植物に囲まながら手探りで進むシーンや闇に赤々と輝く火のイメージが何度も繰り返され、「ここは迷宮なんだよ」と示唆してくる。また『ジェーン・エア』では多用されていたフレア*5も今回抑え気味だな、と思ったら終盤、ここぞとばかりに使いまくる。
一番印象深い画はなんといっても、ドラッグをキメたアグーの目に映る戦場が、一面ピンク色に染まるシーン。ここはモッセ・リチャードという報道写真家のアイディアのいただきらしい*6.。


(上がリチャードの作品、下が本編)
キャリー・フクナガはもしかしたらジョー・ライトと似たような性質のフィルムメーカーなのかもしれない。作品そのものをアリス・リデルに見立てて、ファンタジー外のジャンル*7からファンタジーの世界へとまよいこませ、やわらかいドラッギー感へといざなう。そういう描き方をする。ライトは『PAN』で完全にファンタジーに振れちゃったけど。この手のタイプの人にド直球ファンタジー撮らせたら多分ダメになっちゃうんで、なんとか本作みたいなリアルっぽい路線で行ってほしい。次は『IT』のリメイクか、或いはSFなんだっけ?
NETFLIX 限定ドキュメンタリー、アニメ、特番: 『FはFamilyのF』、『The Propaganda Game』、『ビル・マーレイ:クリスマス』
『FはFamilyのF (F is for Family)』
F is for Family - Main Trailer - Netflix [HD]
一話と二話だけ。七十年代*1のアメリカ郊外の五人家族マーフィー一家を描いたコメディアニメ。
パパのフランク(声ビル・バー)は頑固な父権主義的男性で、家では子どもたちに威張り散らし事あるごとに人種差別的な悪態をついているが、隣人の気のいいリア充を嫉み、職場である潰れかけた空港では上司にも客にも部下にもへつらう小市民。
ママのスー(声ローラ・ダーン)は典型的な主婦。しかし、いったん家事から離れると何の趣味やいきがいもなく、そのことを自覚すると泣きながら「私はこれで幸せなはず」と自分に言い聞かせる。
長男で十四歳のケヴィン(声ジャスティン・ロング)はデニムジャケットにメタル音楽を愛好する落第寸前のバッドボーイ。父親フランクに反発して口汚く罵りさえするが、ときには十四歳相応の豆腐メンタルをのぞかせる。基本的にそっけないが、弟思いな一面も。
次男のビル(声ハーレイ・ラインハルト*2)は生真面目で気弱な男の子。
長女で末っ子のモーリーン(声デビー・デリーベリー)はパパから溺愛されてるやんちゃ娘。
この五人の視点から複層的に彼らの「七十年代」な日常を描く。クリエイターはスタンダップコメディアンのビル・バー*3と『シンプソンズ』の名脚本家マイケル・プライス。
『マッドメン』を嚆矢として*4、最近アメリカで「六十年代七十年代の無神経でマッチョ崇拝で差別主義的で男性中心社会だったアメリカのヒドさを笑おうぜ」的な映画やドラマが流行っているっぽい。でも、単なるリベラルのシニカルな笑いってだけじゃなくて、古き良きアメリカへのノスタルジーも掬い取ってる気もする。
それはともかくとして、内容は意外に手堅く渋い家族ドラマ。基本的には、パパが(時代的にも)失われつつある父親のマッチョな威厳を家族やご近所に示そうとして空回りしてしまう、というのを毎回繰り返すっぽい。しかしシンプルに「時代に乗り遅れつつある古い父親」を笑いの対象にするだけでなくて、そこに働く父親としての悲哀や子どもたちとの関係を織りこむことで最終的には心温まる*5ホームドラマへ落としこむ。そういう複雑なストーリーを二十六分できっちりおさめる手腕はさすが『シンプソンズ』のベテラン脚本家、といった感じ。『ボージャック・ホースマン』もだけど、Netflix のオリジナルアニメシリーズにはどこか不器用なダメ人間へのやさしさがある。
アルバロ・ロンゴリア監督『The Propaganda Game』(2015、スペイン)
THE PROPAGANDA GAME - Foreigners need to come here and see the reality
非 NETFLIX 製作だけど、公開は世界最速。スティーヴン・ソダーバーグ監督『チェ』二部作などをプロデュースしたアルバロ・ロンゴリアによる「北朝鮮行ってみた」ドキュメンタリー。現地取材の映像を織り交ぜつつ、北朝鮮にまつわる虚実を検証しようとこころみる。
一時期に比べるとだいぶニュースバリューは下がったんだろうけれど,日本は比較的北朝鮮にまつわるニュースに接する機会が多い国だ。なので、この映画で新事実を発見して驚く、なんてことはそうそうないと思う。
唯一目新しい存在が、ロンゴリアを案内するスペイン人アレハンドロ・ペレス。このペレスという人はスペイン生まれで生粋のスペイン人であるにもかかわらず、十代のころから北朝鮮に魅了されてそのシンパとなった異色の人物。2000年に設立された 国際文化友好団体、 Korean Friendship Association (朝鮮友好協会?)の会長をつとめ*6、 二十年以上にわたって北朝鮮を訪問する外国人観光客や取材記者たちの案内を行っている。
ペレスはロンゴリアから「北朝鮮っておかしいんじゃない?」と疑問をぶつけられるたびに「いや、おかしいのはアメリカだ。"我々"じゃない」と反論する。当人の気持ちとしては北朝鮮の国民なのだ。彼は何かの大会で「偉大なる指導者様」に熱烈な感謝を捧げ、彼を称える歌を熱唱し、訪問先の学校で「北朝鮮は世界中の国から尊敬と羨望を集めている」と力説する。
識者は「ペレスは北朝鮮にいいように利用されているだけ」と言う。西側の人間、特に白人が北朝鮮の体制を全面的に称揚してくれるなんて、めったにあることじゃないから、宣伝塔としていいように国内外で使われているだけだ、と。
実際そのとおりなんだろう。ただ、自分の故郷ではなんでもないような「その他大勢」の一人が別の国に行くと、下にも置かない厚遇を受ける、というのはある種夢のようで、その夢に酔いたくなる気持ちはわからないでもない。
ソフィア・コッポラ監督『ビル・マーレイ・クリスマス(A Very Murray Christmas)』(2015、米)
A Very Murray Christmas - Trailer - Netflix [HD]
「ネットフリックス・オリジナル・フィルム」ではなくて「ネットフリックス・オリジナル・ホリデー・スペシャル」と銘打たれているので映画じゃなくて特別番組的なあつかいなんだろう。尺も一時間弱しかない。
開幕するや吹雪の舞うクリスマスイブのNYをカーライル・ホテルのガラス越しに眺めるビル・マーレイ(本人役)の後ろ姿が出てきて、洒落たピアノにやたら物悲しいクリスマスソングをのせて歌う。「世間はクリスマスで楽しそうだけど、俺は1月まで消えていたいよ」……。
マーレイはクリスマス生放送特番に出演することになっているのだが、本人は「クリスマスとかみんな街に出てて誰も愚にもつかん特番なんてみねえだろ……」と超ネガティブモード。共演するはずのスターたちも現場にはおらず、スタッフは「アーカイブの映像から合成する」と言う。グダグダに次ぐグダグダのなか、生放送がはじまるが、開始早々マーレイはMCを放棄。会場のホテルから逃走をはかる。そして偶然、コメディアンのクリス・ロックと遭遇。「彼を出せば番組が持つ!」と確信したマーレイはいやがるクリスを無理やり生出演へひきずりこむ。が、突然の停電によって結局番組は取りやめに。踏んだり蹴ったりのマーレイだったが、ホテルのバーで一杯引っ掛けようとしたことがきっかけで彼にもクリスマスの小さな奇跡が起こる。
クリスマス特番らしく、歌あり笑いありのゆるゆるなハートフル・コメディ。オールスターキャストでもあって、エイミー・ポーラーやらマイケル・セラやらジェイソン・シュワルツマンやらマーヤ・ランドルフやらいかにもソフィア・コッポラ好きしそうなサブカルキャストで固められている。その上、ジェリー・ルウィスやフェニックス*7といった歌手まで出演していてみんなでクリスマスソングを歌う。はてはマイリー・サイラスやジョージ・クルーニーまで出てきたり。
Miley Cyrus - Silent Night (A Very Murray Christmas)
さびしげにうなだれているだけで哀れさを、なんとなくテンション高くなってるだけで多幸感を産出するビル・マーレイ力に頼ったビル・マーレイ番組。こういう特番特有のホンワカしたノリやドミノ・コッポラが好きな人じゃないと辛いんじゃないか。辛かった。
このクズ野郎映画がすごい! 2015年版
いやー去年も新作クズ野郎映画がたくさんありましたね。
といわけで、各クズ野郎映画からよりすぐったベストクズ野郎十五名をここで発表したいと思います。
本当は「2015年に観た新作映画ランキング」の一部門としておまけにつけるくらいのノリで書いてたものがなんかやたら膨れ上がってしまったので、急遽独立させました。では、はじめます。
『ナイトクローラー』(ダン・ギルロイ監督、米)
ナイトクローラーさんことルイス・ブルーム記者(演:ジェイク・ジレンホール)
映画『ナイトクローラー』予告
圧倒的サイコパスっぷりで日々圧倒的成長を遂げていく今世紀最高の即戦力男。
三文スクープ専門のカメラマンでありながらにアーティスティックなこだわりを持ちあわせ、フレッシュでニュースバリューのある画を撮るためなら事故現場の死体を勝手に動かすことも辞さない。まさにニュースの天才。本作ではそんな彼の努力! 友情! 勝利! そして愛! の日々をあますところなく堪能できる。
『フォックスキャッチャー』(ベネット・ミラー、米)
ゴールデン・イーグルことジョン・デュポンさん(スティーヴ・カレル)
フォックスキャッチャー 予告篇
戦車からオリンピック代表チームまで、なんでも金の力で買う最強のお坊ちゃま。彼の最大の不幸は、生まれたから人の心さえ所有できる財産に恵まれていたことだったのかもしれない。おそろしいことに実在の人物。
『セッション』(ダミアン・チャゼル、米)
アンドリュー・ニーマン(マイルズ・テラー)&テレンス・フレッチャー(JKシモンズ)
映画『セッション』本予告
二〇一五年度のベストカップル。優しそうな顔で音楽学校の学生ニューマンを籠絡しといてからの理不尽きわまる罵倒の嵐で一気に観客の心をわしづかみにする筋肉ハゲ教師フレッチャー教授。彼に虐待されるうちにニューマンくんも「適応」し、クズ野郎の才能(音楽の才能はあまりない)を徐々に開花させていく様子が素晴らしい。
『恋人たち』(橋口亮輔、日)
四ノ宮弁護士(池田良)
恋人たち 2015 映画予告編
他人の心を理解できずガンガン踏みにじってくるくせに、いざ自分が嫌なとこつかれると死にそうになる。そんな誰にでもある心の暗部をそのまま擬人化させた素敵なキャラクター、それが四ノ宮弁護士です。
『恋人たち』は全体的に嫌な人間しか出てこない心温まる*1クズ人間映画で、観終わったあとには「本当にクズなのは人間ではなく、この国であり、この社会だったんだ……」という水木しげるマンガみたいな気分に浸れるのでとても良い。
『EDEN/エデン』(ミア・ハンセン=ラブ、仏)
DJポール(フェリックス・ド・ジヴリ)
フランス映画『EDEN/エデン』予告編
十代のころからクラブでDJとして鳴らしフランスのハウス・ミュージックに一時代を築く……までには至らず、ダラダラとDJ生活をつづけていくうちに気がつけば金ナシ未婚の三十代。かつての友人ダフト・パンクが世界的な名声を得ていく一方で、ポールの趣味はどんどん時代とかけ離れていき客も減少、パーティは毎度赤字という状況に陥ってしまう。最終的にDJをやめて真面目に働きだすんですが、そのかたわらで小説教室にかよって文化系女子と「ボラーニョいいよね〜」サブカル糞野郎トークかますあたりコイツ実は何も学んでなくない? という気がする。これが実の兄だったというから監督のミア・ハンセン=ラブの苦労が伺えます。
『皆殺しのバラッド メキシコ麻薬戦争の光と闇』(シャウル・シュワルツ、米・メキシコ)
ナルコ・コリード歌手のエドガー・キンテロ
『皆殺しのバラッド メキシコ麻薬戦争の光と闇』予告編
ドキュメンタリー、つまり完全実話。
メキシコでは麻薬カルテル同士の抗争で日々何百何千というギャング、そして市民たちが死んでいく。そんな血にまみれたギャングの日常と栄光を歌うのがナルコ・コリードと呼ばれるジャンルの歌曲群だ。このナルコ・コリードの題材としてフィーチャーされるのが大物ギャングの証、という風潮まであるらしい。
エドガー・キンテロはそんなナルコ・コリードの人気若手歌手。しかし、彼自身はマフィアではない。どころかメキシコ人ですらなく、カリフォルニア在住の兄ちゃんだ。にもかかわらず「ムカつくあの馬鹿を殺してやったぜ」だとか「警官をぶち殺せ」だとか過激な歌詞のコリードを歌ってメキシコで大ヒット。ついには「俺の人生をコリード化してくれ」とギャングの大物からオファーを受け、メキシコへ。そこでマシンガンまで撃たせてもらう至れり尽くせりの大接待を受け、超ご満悦になるキンテロくん。
一方そのころ「世界で最も危険な街」、ギャング抗争の激戦地であるメキシコのシウダー・フアレスでは「最後の警官」(この街で警官をやっている人間は、ギャングから賄賂を受け取るか、それを断って殺されるか、あるいは警察をやめるかのどれかひとつしか選べない)リチ・ソトが孤独で不毛な戦いをつづけていた……というふうに、キンテロくんのノーテンキなアイドル生活とリチ・ソトさんの地獄のような日常が交互に示されて、観客はなんとも言いがたい心持ちになる。無知は罪なのではなく、悪なのだ。
『ビースト・オブ・ノーネイション』(キャリー・フクナガ、米)
指揮官(イドリス・エルバ)
ビースト・オブ・ノー・ネーション予告編 - A Netflix Original Film [HD]
アフリカの某国で闘争を行っている反政府軍のゲリラ部隊を指揮するカリスマ。脱落=死を意味する過酷なトレーニングとあやしげな土着の魔術で少年たちを洗脳し、戦闘員に仕立てあげる。
彼はことあるごとに「俺たちは家族だ」と舞台の家族性を強調し、主人公の少年兵にも「俺はおまえの親父だ」と諭すが、実のところ彼は「家族」を自分の野心を達成するための道具程度にしか考えていない。そしてその彼の身勝手さが、ただでさえ悲惨な内戦をより深い地獄へと塗り替えていく。
『オン・ザ・ハイウェイ その夜、86分』(スティーヴン・ナイト、英・米)
ロック(トム・ハーディ)
車中の男と電話の会話のみで物語が展開!映画『オン・ザ・ハイウェイ その夜、86分』予告編
ビル工事で指揮をとる建設会社社員のロックは、超重要な作業日の前夜に突然責任ある立場を放り出して車で走りだす。彼が昔たった一度だけ過ちを犯した相手が妊娠しており、その夜に彼女が産気づいたというのだ。「美人じゃないけど、かわいそうな女なんだ」などと口走り、仕事、会社、そして一緒にサッカーの試合を観戦する約束をしていた家族をも放り出して、妊婦の運ばれた病院を向かう。
いままで放っておいた不倫相手が妊娠していたというのでいきなり情が湧くまではまあいいとして、そのために数千人の生活と生命が関わるプロジェクトをアル中の下っ端に丸投げし、かつ自分の子どもと妻をほっぽりだすというなかなかの責任感のなさ。しかも、車で走っている(八十六分間ずっと運転席で一人芝居するハーディしか映らない)あいだ、ずっとブツブツ気持ち悪い独り言をつぶやいて、ついには自分の親父の幻影と戦い出す始末。
本作で監督も兼任しているスティーヴン・ナイトの脚本(『イースタン・プロミス』とか『ハミング・バード』とか『完全なるチェックメイト』とか)は「移民ネタが多い」とよく言われるけれど、そんなことより「他人には理解できない強烈なパラノイアを抱えて半分崩壊しかけている人間」がよっぽど特徴的な気がする。ナイトが単独で脚本書いた『Burnt』(ジョン・ウェルズ監督)もそういう話なんだろうなあ。
『名もなき塀の中の王』(デヴィッド・マッケンジー、英)
囚人ネビル・ラブ(ベン・メンデルソーン)
『名もなき堀の中の王』10月10日より、新宿K's cinemaほか全国順次公開!!
ジャック・オコンネル*2演じる主人公がたまたま父親であるネビルとおなじ刑務所にぶちこまれる。父親はなんとか彼なりに父子の絆を取り戻そうとするが、十何年も刑務所で臭い飯を食ってきたクズなので子どもとどう接したらいいかわからず、迷走しまくる。息子は息子で、同房の囚人と「懇ろ」になったり、牢名主に媚を売ったりする親父の情けない姿に幻滅し、ますます彼に対する不信を深めていく。果たしてネビルさんは息子の親愛を勝ち取れるのか――。涙無くしては見られない、クズ野郎頑張り映画です。
ネビルを演じるベン・メンデルソーンは今、クズ野郎界でもっともアツいクズ野郎俳優として知られています。オーストラリア映画『アニマル・キングダム』で大変身勝手な理由から自分の甥とその恋人をひどい目に合わせるクズヤクザ中年を演じたことで注目を浴び、以後、『ジャキー・コーガン』でヤクザの賭場へ押し入って強盗を働きブラピ演じる殺し屋のターゲットとなるチンピラ犬泥棒、『ダークナイト ライジング』でウェイングループの乗っ取りを目論むビジネスマン、『エクソダス』でユダヤ人を虐める総督、『プレイス・ビヨンド・ザ・パインズ』でライアン・ゴズリングの超絶バイクテクを見込んで銀行強盗に誘う修理工、『ロスト・リバー』で生活に困窮したシングルマザーを怪しげなショーの仕事に誘う銀行マン、『ブラック・シー』で潜水艦チームを崩壊させるきっかけを作る短気な潜水士、などなど錚々たる大作・名作でクズ野郎っぷりをふりまいております。ここまでタイプキャスト極まった俳優もなかなかみかけない。
メンデルソーンは今後もライアン・レイノルズと共演する『ミシシッピ・グラインド』やギャレス・エドワーズ*3監督のスターウォーズスピンオフ『ローグ・ワン』などが出演作として控えており、これらの作品でどんなクズ野郎っぷりを見せつけてくれるのか、ファンの期待が高まっています。
『ホーンズ 容疑者と告白の角』(アレクサンドル・アジャ、米)
ご町内のみなさん
『ホーンズ 容疑者と告白の角』予告
ある日唐突に恋人殺しの容疑をかけられたダニエル・ラドクリフ、そんな彼をさらに唐突な事態が襲う! なんといきなり角が生えてきたのだ! しかもその角は周囲の人間を「正直になんでも白状させる」効果を具えていた!
というわけでラドクリフの行くところ会う人みな慾望と悪意に真っ正直になります。これで事件解決できるぜやっほいかとおもいきや、みんなが正直すぎるあまりむしろ混迷を深めていく有様に……。
『完全なるチェックメイト』(エドワード・ズウィック、米)
ポール・マーシャル弁護士(マイケル・スタールバーグ)
トビー・マグワイア主演 映画『完全なるチェックメイト』予告編
ソ連との対抗試合を途中放棄してチェスからの引退を宣言した天才ボビー・フィッシャーの前に現れた謎の弁護士。「おれと一緒に国に尽くさないか」と愛国者を自称してボビーを再びチェスの世界に引き戻す。わがまま三昧に高額な報酬や無茶苦茶な要求を繰り出すフィッシャーを、ときに脅し、ときになだめすかしながら、彼の数少ない友人として、ソ連のチェスチャンピオンとの世紀の一戦をお膳立てしていく。
ところが物語が進行するにつれ、フィッシャーの圧倒的な棋力が彼自身の精神をむしばんでいるのだと判明する *4。フィッシャーのサポート役である神父は「このままだと彼が壊れてしまう。治療してやるべきだ」と主張するが、マーシャルは「お国のためだ。うかうか治療してチェスが弱くなってもらっては困る!」とはねつける。やがては神父もチェスプレーヤーとしての暗黒面に落ち「もっと強いフィッシャーが見たい……」とマーシャルの意見に転び、もはや誰もフィッシャーを救おうとしなくなる。
劇中のボビー・フィッシャーも傍から見ればなかなかのクズ野郎なのだが、完全にビョーキの人物として描かれていることだし、しかも環境によってその病気が悪化させられていった被害者であるという面は否めない。反して、この大義を掲げる正気の人間であるマーシャル弁護士こそ、まさにホンモノのクズ野郎と呼ぶにふさわしい人物なのだ。「本当のクズ野郎とは何か?」を問うスティーヴン・ナイト渾身の脚本芸。
『ラブ&マーシー 終わらないメロディー』(ビル・ポーラッド、米)
精神科医ユージン・ランディ(ポール・ジアマッティ)
映画「ラブ&マーシー 終わらないメロディー」予告編
立ち位置としては『完全なるチェックメイト』の弁護士と似ているかもしれない。ランディもまた自らの目的のために物凄い才能を持った人間を食い物にする男だ。ただ、弁護士は狂気じみた愛国心からあくまでフィッシャーの才能を伸ばす方向に振っていたけれど、この精神科医は金さえ手に入ればどんなに天賦の才能をスポイルしてもかまわない、というスタンスだ。小悪人じみているというか、より身近な悪の恐ろしさを感じるというか。
ランディが寄生するのは六十年代に人気を集めたバンド「ザ・ビーチ・ボーイズ」の音楽面でのクリエイティブを一手に担った才人ブライアン・ウィルソン。金のなる木を意のままに操るため、ランディは精神科医という立場を悪用して症状を悪化させる薬を与えてブライアンを弱らせ、保護者として版権なども取り上げてしまう。小悪人といえど、時機さえあれば偉大なる才能を破壊しつくしてしまう、という事実に凡人である我々は震え上がるしかない。
『フレンチアルプスで起きたこと』(リューベン・オストルンド、スウェーデン・デンマーク・仏・ノルウェー)
二児の父親トマスさん(ヨハネス・バー・クンケ)
せっかくの家族旅行だったのに…!映画『フレンチアルプスで起きたこと』予告編
アルプスの雪山にスキー旅行へやってきたトマスさん一家。楽しい一家団欒を過ごすはずが、とあるトラブルに見合われたさいに家族を見捨てて一人だけ逃げ出したことでトマスさんの夫としての威厳と立場が一挙に崩壊、妻からも不信の眼で見られるように……。トマスさんはアルプス滞在を終えるまで妻からの信頼を取り戻すことができるのか? といった内容。
いやあ、これはトマスさんの行動も仕方ないでしょう、と思う反面、妻視点からすれば「いざというときに家族を見捨てる旦那」として映るのもまたわかるわけで、このリストに挙げたなかでは一番観客に近い「クズ」かもしれない。
とはいえ、トマスさんもちょくちょくオリジナルなクズっぷりを発揮します。雪山で知り合ったカップルに対して奥さんが「こいつ私ら捨てて逃げ出したんですよ〜」と冗談気味にチクられると「いやいや全然そんなことやってないし(笑)」と本気で否定しにかかったり、「許してくれよー」と泣き出したかと思えば奥さんから「うそなきすんじゃねえ!」と一喝されて「すいません嘘でした」と謝ったり、逃げ出した事実を自分でも認めたくないばっかりに認知を拒否する行動をとりまくり、とにかく情けない。
『ブラック・シー』(ケビン・マクドナルド、英・ロシア)
潜水士フレイザー(ベン・メンデルソーン)
ジュード・ロウ主演 映画『ブラック・シー』予告編
メンデルソーンあげいん。
黒海に沈むナチスの金塊を目指して結成されたジュード・ロウ率いる底辺野郎サルベージチーム。オンボロ潜水艦に乗りこむ乗員はロシア人とイギリス人で半々、いずれも揃って荒くれ者ばかりなので、当然船内には険悪な空気が漂う。
その中でもとりわけ喧嘩っぱやいのが我らがメンデルソーン演じる潜水士フレイザー。ロシア人側の乗員たちに喧嘩を売りまくり、ついにはとんでもない事件をひきおこしてしまう。
こーゆーよーな、いきがってはいるけれど、実は心が弱くて壊れやすい、不安定なクズ野郎を演じさせたらメンデルソーンは一級です。
『あの日のように抱きしめて』(クリスティアン・ペッツォルト、ドイツ)
ピアニスト、ジョニー・レンツ(ロナルト・ツェアフェルト)
映画『あの日のように抱きしめて』予告編映像
ユダヤ人の妻を裏切ってナチスに売った疑惑をかけられている夫ジョニー。そんな彼のもとに、終戦後、収容所から開放された歌手の妻が戻ってくる。しかし、目の前の女性が妻であると彼にはわからない。なぜなら、妻は顔に負った傷を修復するため顔面再建手術を受けており、容姿がすこし変貌していたのだ。
真実を切り出せない妻に、ジョニーはある提案を行う。「きみは僕の妻によく似ている。彼女は資産家だったが、収容所で死んでしまった。遺産相続のために妻のフリして親戚に会ってくれないか?」
驚くべきことに、妻はこの提案を了承する。裏切られたかもしれないとはいえ、いまだ愛する夫を見捨てるという選択肢はとれなかった。彼女は「自分」であることを気づいてもらいたくて、さんざんアピールを繰り返すがジョニーは眼をそらしつづける……。
このシチュエーションを考案したアイディア力の勝利。
追記枠
『最後まで行く』(キム・ソンフン、韓国)
殺人課のコ・ゴンス刑事(イ・ソンギュン)
【予告】最後まで行く
クズ野郎映画の本場、韓国からの現れたクズ野郎界の新星汚職デカ。
冒頭でいきなり通行人を轢いたと思ったら、死体をトランクに詰め逃走を図る。路上の検問を高圧的な態度で切り抜けたはいいものの一難去ってまた一難、今度は民間企業からの贈賄容疑(殺人課ぐるみでやってる)で内務監査の取り調べを受けるハメに陥る。同僚から内務監査班が車のトランクを調べるために向かっていると聞かされたコは慌てて死体を隠匿する方法を考え出す。それが、亡くなったばかりの母親の棺に死体を忍び込ませるというトリック。ここまでで三十分も経ってない。いかに彼がクズ野郎であるかがおわかりいただけるかと思う。
とにもかくにもディクスン・カーばりのトンチで窮場を切り抜けた……かとおもいきや、今度は謎の男から「お前が男を殺したことを知っている」という脅迫電話がかかってくる。それは彼を越える巨悪からの挑戦状でもあった。果たしてコ刑事の明日はどっちだ。
2015年に観た新作映画で好きな劇中歌・エンディングソング・サントラ
動画リンクばかりなので重いです。
挿入歌(オリジナル or カバー)
『あの日のように抱きしめて』――「Speak low」(ニーナ・ホス)
Nina Hoss Speak low Phoenix
『はじまりのうた』――「Lost Stars (Into the night mix)」(アダム・ラヴィーン)
Adam Levine - Lost Stars (Into the Night Mix) (Begin Again OST)
『君が生きた証』――「Stay with You」(ラダーレス)
Stay With You - Rudderless Movie Soundtrack
『イントゥ・ザ・ウッズ』――「Prologue」
Prologue: Into the Woods (From “Into the Woods”) (Audio)
挿入曲
『インヒアレント・ヴァイス』――「Les Fleur」(ミニー・リパートン)
Inherent Vice Soundtrack (Vicio Propio) #07. Les Fleur OST BSO
『インヒアレント・ヴァイス』――「Sukiyaki」(坂本九)
Inherent Vice Soundtrack (Vicio Propio) #09. Sukiyaki OST BSO
『EDEN/エデン』――「Caught in the Middle (Gospel revival remix)」(ジュリエット・ロバーツ)
Juliet Roberts - Caught In the Middle
『ソレダケ that’s it』――「アンニュイ」(bloodthirsty butchers)
エンディング曲(フィニッシング・ストローク)*2
『ワイルド・スピード SKYMISSION』――「See You Again」(ウィズ・カリファ feat チャーリー・パス)
Wiz Khalifa and Charlie Puth Perform 'See You Again'
『インヒアレント・ヴァイス』――「Any Day now」(チャック・ジャクソン)
Chuck Jackson - Any Day Now (Great clip from 1965)
『Mommy』――「Born to Die」(ラナ・デル・レイ)
Lana Del Rey - Born to Die Lyrics Video
『ヒックとドラゴン2』――「Where No One Goes」(ヨンシ)
"Where No One Goes" (How To Train Your Dragon 2) [Official Lyric Video]
『ラブ&マーシー 終わらないメロディー』――「Wouldn’t it be nice」(ザ・ビーチ・ボーイズ)
Beach Boys - Wouldn't It Be Nice
エンディング曲*3
『百日紅 Miss Hokusai』――「最果てがみたい」(椎名林檎)
椎名林檎-「最果てが見たい」from林檎博’14
『新選組オブ・ザ・デッド』――「生きて生きて」(サンボマスター)
サンボマスター「生きて生きて」MUSIC VIDEO short version
『The COCKPIT』――ー「Curve Death Match」(OMSB, BIM)
『バクマン』――「新宝島」(サカナクション)
サカナクション / 新宝島
『クリード チャンプを継ぐ男』――「Last Breath」(フューチャー)
Future – Last Breath from CREED
2015年に観た新作映画ベスト20とその他
ベスト作品
参考: 上半期のベスト
評価基準は「ドラッグとして有用か否か」です。
1.『インヒアレント・ヴァイス』(ポール・トーマス・アンダーソン、米)
八月のガラッガラな劇場でダラダラとダウナーに何度も繰り返し観る映画、すなわち夏の映像ドラッグとしてこれ以上にドープな映画は存在しない。そして二度三度と繰り返していく内に、これは逃走についての、アメリカン・ハードボイルドの基調である「共にあること」*1についての寓話であることがすけてみえてくる。そうなれば三倍おいしい。世界政府は一刻もはやく国民の健康と福祉のために本作を薬用映画として公認および合法化し、毎年夏に『おおかみこども』とセットで一日中併映すべき。フローズンバナナチョコレートつきで。
2.『セッション』(ダミアン・チャゼル、米)
ハゲ vs ふてくされたガキ。キャラクターのキチガイ性みたいなことばかり言われていて、たしかにそこも素晴らしいのですけれど、編集やモチーフを打ちこんでくるテンポも神がかっている。画面のなかにいる人間も見ているほうの人間もすりつぶされる九十分。
3.『ナイトクローラー』(ダン・ギルロイ、米)
サイコパス糞野郎成功譚。夜のロサンゼルスをパキッとしたルックスで撮るとそれだけで魔術的な舞台がたちあがる。『インヒアレント・ヴァイス』とならんで L.A. ってズルいよなあ、と思わされる映画です。
4.『フォックスキャッチャー』(ベネット・ミラー、米)
笑ってはいけないスティーブ・カレル24時。不穏さだけで人の興味は二時間超も持続するのか。します。しうるのです。
5.『イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密』(モルテン・ティルドゥム、英・米)
すべてのシーン、すべてのセリフ、すべての光が『イミテーション・ゲーム』という物語に奉仕している。その度をこえた人工性はときに快楽ですらあるのです。
6.『マップ・トゥ・ザ・スターズ』(デヴィッド・クローネンバーグ、カナダ・米・ドイツ・仏)
姉映画のオールタイム・ベスト。『25時のバカンス』とならぶ宿命論的姉論のマニフェスト。
7.『恋人たち』(橋口亮輔、日)
100%ピュアなディスコミュニケーション・ポルノ。日常に巣食う嫌さをえんえん見せつけられていくだけで人は二時間超の映画を持続的に視聴できるのか。できる、できるのだ。
8.『マッドマックス怒りのデスロード』(ジョージ・ミラー、米)
やはりこれも編集というか、タイミング、あるいは速度の映画で、冒頭の砦内でのウォーボーイズとの追いかけっこにおける「微妙に早送りしてない?」感とかすげえ脳髄にキます。
9.『EDEN/エデン』(ミア・ハンセン=ラブ、仏)
ダメ人間映画。音楽の才能はそれなりにあるもののそれなりにしかないので実際食ってけないダメな人間が特に現状を革命しようとも思わないままダラダラ場当たり的に愉快に過ごしていって後年そのツケの返済に迫られてしにそうになる――『インサイド・ルーウィン・デイヴィス』じゃん。
10.『ブルー・リベンジ』(ジェレミー・ソルニエ、米・仏)
理不尽に奪われた尊厳を取り戻すために、理不尽極まりない復讐へとつきすすむ人間の物語はいつだって美しい。どのカットにも青いオブジェクトが写り込んでいるという『アデル、ブルーは熱い色』みたいな謎演出もありますが、まあ、それはともかく。
11.『花とアリス殺人事件』(岩井俊二、日)
美しい。岩井俊二なんてバブル後の日本のウィンプさの象徴だろくらいにしかみなしておらず、実際前作にあたる『花とアリス』は心底どうでもよく考えていたのですが、この映画はとにかく美しい。背景のモブがそれぞれ別個の意志をもった生命のごとく不揃いに動作するアニメってそれだけでフレッシュですよねえ。
12.『ブラック・シー』(ケビン・マクドナルド、英・ロシア)
蟹工船 in 潜水艦。クズ野郎どもをまとめて一箇所に集めると学級崩壊が起こる。傷つくのはクズ野郎ばかりで、学校というシステムそのものは涼しい顔で稼働しつづけるんだ。
最初は良識あるバランサーだったのに段々深海に魅入られておかしくなっていく艦長へ投げつけられる言葉、「『ヤツら』って誰だよ!!!」が非常に印象的。そう、「ヤツら」はここにはいないし、永遠に打ち負かされない。
13.『アクトレス 女たちの舞台』(オリヴィエ・アサイヤス、仏・スイス・ドイツ・米)
舞台のリハーサルと日常の会話がおなじカット内でシームレスにつながり、それが虚実の皮膜を溶かしていく、といえばいたって平凡なメタフィクションに思われそうだけど、その凡庸さへの陥穽を監督の演出と女優たちのケミストリーでぎりぎり回避した傑作会話劇。
14.『名もなき塀の中の王』(デヴィッド・マッケンジー、英)
父子ものには弱いなあ。ベン・メンデルソーンの十八番、「実は弱いくせにいきがってる中年オヤジ」のどうしようもなさがいかんなく炸裂しております。
15.『ホワイト・ゴッド 少女と犬の狂想曲』(コーネル・ムンドルッツォ、ハンガリー・ドイツ・スウェーデン)
犬たちは、現実で、映画で、絶え間なく人間から虐待されつづけてきた。これはそんな犬たちの反逆の物語なんです。犬の公民権運動なんです。ラストにおいて主人公の女の子がみせるある態度は、『ヒックとドラゴン』にも匹敵する尊さを放っている。
16.『神々のたそがれ』(アレクセイ・ゲルマン、ロシア)
去年なにかのイベントで観た時には正直よくわからないというか、ほとんど寝てたんだけど、今年『フルシタリョフ、車を!』などを経て改めて観なおしてみるととてつもなくテンションの張った傑作だったとわかりました。
17.『アメリカン・スナイパー』(クリント・イーストウッド、米)
いろんな意味で、素晴らしいバランス。アメリカ映画の神は違うね。
18.『はじまりのうた』(ジョン・カーニー、米)
音楽に語らせ、音楽で語り合い、音楽を謳う。実にピュアな音楽讃歌。しかしありがちなナイーブさは慎重に排除されていて、全編に渡って骨太なマッスルを見せつけてくれもする。
19.『馬々と人間たち』(ベネディクト・エルリングソン、アイスランド)
遠い遠い寒い国にも、人間と動物は居て、つまらないことで死んだり生きたりしてるんだなあ、ということを実感できる。
20.『ヴィジット』(M・ナイト・シャマラン、米)
これまでの姉フィクションの伝統を踏まえながらも、弟と互いの弱さを補いあいながらトラウマを克服するという「対等な姉弟関係」を創出した影の姉映画オブジイヤー。
ベスト姉映画部門

☆『マップ・トゥ・ザ・スターズ』(デヴィッド・クローネンバーグ、カナダ・米・ドイツ・仏)
『海街diary』(是枝裕和、日)
『ヴィジット』(M・ナイト・シャマラン、米)
『ブルー・リベンジ』(ジェレミー・ソルニエ、米・仏)
『シンデレラ』(ケネス・ブラナー、米)
『トゥモローランド』(ブラッド・バード、米)
短観:メタファーとしての姉あるいは姉的運命論の完成形『MttS』、輻輳する姉妹関係のダイナミズムが絶妙な『海街』、等身大かつ対等なバディとしての姉像を描いた『ヴィジット』が今年の三大姉映画。映画界全体としては昨年に比べて姉映画日照感が否めなかったのですが、この三作を収穫できただけでも補ってあまりある。
『ブルー・リベンジ』における姉はワンポイント的な起用でしたが、その使い方がなかなか強烈。
ベスト音楽映画部門
参考:2015年に観た新作映画で好きな劇中歌・エンディングソング・サントラ - つんかる
☆『はじまりのうた』(ジョン・カーニー、米)
『EDEN/エデン』(ミア・ハンセン=ラブ、仏)
『セッション』(ダミアン・チャゼル、米)
『君が生きた証』(ウィリアム・H・メイシー、米)
『ラブ&マーシー 終わらないメロディー』(ビル・ポーラッド、米)
『ラブ&ピース』(園子温、日)
短観:音楽という文化そのものの尊さをファンタスティックに、しかし無理のないバランスで文字通り謳い上げた『はじまりのうた』に一票。個人的にはカーニーの前作『ONCE』より雑味が取れていて好きです。音楽(楽曲)そのものへのオブセッションでいえば『君が生きた証』が意外な拾い物でした。ちなみに『ストレイト・アウタ・コンプトン』は今年に入ってから観たので来年のベストでの取り扱いとなりますが、果たしてあれを超えてくる音楽映画が今年やってきてくれるのか。
ベスト動物映画部門

☆『馬々と人間たち』(ベネディクト・エルリングソン、アイスランド)
『ホワイト・ゴッド 少女と犬の狂想曲』(コーネル・ムンドルッツォ、ハンガリー・ドイツ・スウェーデン)
『映画 ひつじのショーンバック・トゥ・ザ・ホーム』(マーク・バートン&リチャード・スターザック、英・仏)
『ラブ&ピース』(園子温、日)
『ゾンビーバー』(ジョーダン・ルービン、米)
『さらば、愛の言葉よ』(ジャン・リュック・ゴダール、仏)
短観:動物映画にも色々あるわけですが、2015年は『馬々と人間たち』*2と『ホワイト・ゴッド』のツートップをおいて他にない。どちらも人間の鏡像として動物たちを描いきつつも、そのスタイルがそれぞれに違っていて、それぞれに良い。
可哀想な犬オブジイヤー

☆『ホワイト・ゴッド 少女と犬の狂想曲』(コーネル・ムンドルッツォ、ハンガリー・ドイツ・スウェーデン)
『ジョン・ウィック』(チャド・スタエルスキ、米)
『奇跡の2000マイル』(ジョン・カラン、オーストラリア)
『映画 ひつじのショーンバック・トゥ・ザ・ホーム』(マーク・バートン&リチャード・スターザック、英・仏)
『キングスマン』(マシュー・ヴォーン、英・米)
短観:出てくる映画の七割で「人間の身代わり」として殺される傾向にある可哀想な動物、それが犬。『ホワイト・ゴッド』はそうしたストックキャラクターとしての可哀想な犬像を一定程度踏襲しつつも、既存の人間至上主義映画に対するアンチテーゼをかましたお犬様レボリューション映画です。
ベストアニメーション部門

☆『インサイド・ヘッド』(ピート・ドクター、米)
『映画 ひつじのショーンバック・トゥ・ザ・ホーム』(マーク・バートン&リチャード・スターザック、英・仏)
『花とアリス殺人事件』(岩井俊二、日)
『劇場版ムーミン 南の海で楽しいバカンス』(グザビエ・ピカルド&ハンナ・へミラ、フィンランド)
『クーキー』(ヤン・スヴェラーク、チェコ)
『I LOVE スヌーピー THE PEANUTS MOVIE』(スティーヴ・マーティノ、米)
短観:ここにあげたアニメ映画はどれもすばらしいのですが、やはり今年は『インサイド・ヘッド』一択でしょう。ストーリーテリングの革命ですらあった。純アニメーション的な快楽(人間ならざるものがぬるぬる動く)でいえば、もちろんストップモーション系統の『クーキー』や『ひつじのショーン』が強い。ストップモーションといえば、ライカの『Box Troll』はいつ公開されるんだ???
コミュ障ポルノ部門

☆『恋人たち』(橋口亮輔、日)
『イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密』(モルテン・ティルドゥム、英・米)
『フォックスキャッチャー』(ベネット・ミラー、米)
『ブラック・シー』(ケビン・マクドナルド、英・ロシア)
『完全なるチェックメイト』(エドワード・ズウィック、米)
『ナショナル・シアター・ライヴ2015 「二十日鼠と人間」』(アンナ・D・シャピロ、英)
短観:コミュ障ポルノとは、要するにコミュニケーションが下手くそすぎて悲惨かつドラマティックな事態をひきおこしてしまう愛すべき人々が出てくる映画のことです。たいがいの場合、人の生死や国の存亡といった事柄がコミュニケーション能力不足により出来したりするのですが、そのようなコミュ障ブロックバスター化傾向のなかで、表面上「たいしたこと」は起こっていないにもかかわらず嫌さを極めたコミュニケーション不全を発症しているのが『恋人たち』です。
私的ブレークスルー俳優

☆ローリー・キニア(『NTL オセロー』*3、『ホロウ・クラウン』/『リチャード二世』*4、『007/ スペクター』、『イミテーション・ゲーム』)
ベン・メンデルソーン(『名も無き塀の中の王』、『エクソダス: 神と王』、『ブラック・シー』、『ロスト・リバー』)
マーク・ストロング(『イミテーション・ゲーム』、『キングスマン』、『リピーテッド』)
クリステン・スチュワート(『アクトレス』)
エマ・ストーン(『マジック・イン・ムーンライト』、『バードマン』)
ダミアン・チャゼル(『セッション』、『ファンタスティック・フォー』)
短観: 粗野ですらある不遜な容貌、暗く沈んだような眼、そしてあらゆる凶相要素を裏切って発せられる低く高貴な声、ローリー・キニアの魅力にふれたのは『イミテーション・ゲーム』の警部役で、そこから『オセロー』や『リチャード二世』といった主演作を観てこいつはとんでもねえな、と。ローリー、ストロング、JKシモンズが今年の三大ハゲ。
女優二人はこれまで正直魅力をよく理解できていなかったのだけれど、それぞれアサイヤス、ウディ・アレンといった女優の使い方に通暁した監督の演出によってようやくその真価を知るにいたりました。
![インヒアレント・ヴァイス ブルーレイ&DVDセット(初回限定生産/2枚組/デジタルコピー付) [Blu-ray] インヒアレント・ヴァイス ブルーレイ&DVDセット(初回限定生産/2枚組/デジタルコピー付) [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51F-vm2froL._SL160_.jpg)
インヒアレント・ヴァイス ブルーレイ&DVDセット(初回限定生産/2枚組/デジタルコピー付) [Blu-ray]
- 出版社/メーカー:ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント
- 発売日: 2015/08/19
- メディア:Blu-ray
- この商品を含むブログ (7件) を見る
![セッション コレクターズ・エディション [Blu-ray] セッション コレクターズ・エディション [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Da53lYYbL._SL160_.jpg)
- 出版社/メーカー:ギャガ
- 発売日: 2015/10/21
- メディア:Blu-ray
- この商品を含むブログ (18件) を見る
![ナイトクローラー [Blu-ray] ナイトクローラー [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ZfN6BUOLL._SL160_.jpg)
- 出版社/メーカー:ギャガ
- 発売日: 2016/02/19
- メディア:Blu-ray
- この商品を含むブログ (2件) を見る
2015年のミステリ映画を回顧する
そもそもの問題として映画に「ミステリ」はあり得るのか、というアレがあるわけですが、それはそれとして、今でもジャンル映画としてのミステリ映画はそれなりに公開されていて、面白いものもたくさんある。
というわけで、去年とお正月に観た2015年の新作ミステリ映画を総括いたしましょう。
ちなみにここで扱う「ミステリ映画」には二種類あります。
ひとつは事前に製作者側ないし宣伝側でミステリとしてパッケージされた*1ジャンル*2としてのミステリ映画で、もうひとつは特にそういうパッケージングはされていない(ミステリとして期待されていない)映画です。
前者は赤、後者を青で塗り分けていきたいと思います。
番号は自分からみて「ミステリっぽい」順にソートしました。わりあい雑なので参考程度に。
1.『プリデスティネーション』(スピエリッグ兄弟監督)
演:サラ・スヌーク、イーサン・ホーク
1981年にタイムトラベルが発明された世界。時空警察の捜査官(ホーク)は爆弾魔「フィズル・ボマー」によって設置された爆弾の解体作業に失敗し、大やけどをおってしまう。かろうじて一命を取り留めた彼は「最後の任務」を拝命し、1970年*3のニューヨークへ跳ぶ、
とあるバーでバーテンダーとして働き出した捜査官のもとに、ある夜、ジョン(スヌーク)と名乗る一人の男性客が現れ、自分の人生を披瀝しはじめる。曰く、ジョンはその昔、「ジェーン」いう名の少女であったというのだが……。
ハインライン原作のSFミステリ*4。
ストーリー、登場人物、ラニングタイムを極限まで切り詰め研ぎ澄ました、変態的なまでにタイトな映画。少なくない人が途中で着地点を看破できると思うけれど、「じゃあ具体的にどうやってそこまで持ってくのか」を芸術的に突き詰めて飽きさせない。
2.『君が生きた証』(ウィリアム・H・メイシー監督)
演:ビリー・クラダップ、アントン・イェルチ、セレーナ・ゴメス、ローレンス・フィッシュバーン
大学構内で発生した銃乱射事件によって息子を亡くした男、サム(クラダップ)。
息子の死にショックを受けた彼はそれまで務めていた広告会社を退職し、ボートで寝起きしながら日雇いの仕事で生計を立てる毎日を送っていた。そんなある日、そんな彼のもとに離婚した元妻から息子の遺品である楽器や自作CDを譲り渡される。
息子が遺した楽曲を聴き、歌っていくうちに亡き息子の姿をそこに見出すようになるサム。彼は息子の曲を、ライブバーで歌うことを決める。
言っちゃうとなんだけど叙述トリック映画です。叙述トリックのキモはどんでん返しする部分そのものよりも、どんでん返しによってそれまで語られてきたことがどう変容するのかにあると思うのですが、それを下手なミステリよりディープな部分で達成している。
提示されたシチュエーション(息子の死によって荒れた生活をおくる父親)や道具立て(死んだ息子が遺した歌)、それに出てくるキャラクターたちまでもがちゃんとトリック発動後の変化に絡んでくる。それでいていわゆる「トリックに奉仕させれている」感があまりない。トリック自体はあくまでストーリーの従属物なのです。
ミステリというジャンル外でミステリ的な技法を用いるときの、ある種の理想形なんじゃないかとすら思います。
逆に言えば、「ストーリーのためのトリック」だけでなく「トリックのためのトリック」が許されるのもジャンルとしてのミステリのいいところではないのかな、とそういうことも照射的に再確認させられました。
3.『女神は二度微笑む』(スジョイ・ゴーシュ監督)
演:ビディヤ・バラン、ナワーズッディーン・シッディーキー
イギリス在住の妊婦ヴィディヤ(バラン)がインドへ渡ったっきり失踪してしまった夫を捜してカルカッタへやってくる。夫が宿泊していた宿や勤務先で必死に聞き込みを行うヴィディヤだったが、誰一人として夫を知るものに出会わない。そんななか、ダムジという夫と瓜二つの人物の存在を知る。果たしてダムジの正体とは? 彼女の夫はなぜ失踪したのか?
インドからやってきたド直球本格ミステリ。プロットから語りの細やかさに至るまで繊細に配慮されている。伏線あり、捜査あり、殺人あり、高圧的な警察あり、陰謀あり、どんでん返しあり、盛り上がるクライマックス(インドならではの舞台設定が嬉しい)ありと嬉しさアリアリの満漢全席。ミステリファンで嫌う人はあんまりいないんじゃないかな。
4.『最後まで行く』(キム・ソンフン監督)
演:イ・ソンギュン、チョ・ジヌン、チョン・マンシク
企業から班ぐるみで賄賂を受け取っていたドぐされ刑事が母親の葬式の帰りに車で人を轢いてしまい、事件を隠蔽するために母親の棺桶(キリスト教式なので土葬)に遺体を隠そうする、という黄金期海外本格じみたところからはじまってどんどん刑事がドツボにハマっていく地獄めぐり映画。
とにかく、これでもか、というぐらいに全編通してサスペンスが連続する。『アルゴ』なんて目じゃないくらい、ギッチギチにドキドキをコッテリ詰めこみまくっている。この密度。この圧力。ものすごい凝った伏線やどんでん返しみたいなものはないんだけれど、そんなもんなくても映画ってのはおもしろく作れるんや! ということを教えてくれる。
5.『ランダム 存在の確立』(ジェームズ・ウォード・バーキット監督)
演:エミリー・フォクスラー、モーリー・スターリング
量子論SFホラー、いわゆる「シュレディンガーのネコ」ものだと聞けば、その時点でかなりの人が観る気失せるかもしれないけれど、これは存外に掘り出し物。伏線やアイテムの使い方が明示的かつソリッドで、ほとんどのシーンが民家のリビングで繰り広げられる会話劇でありつつもしっかり見せてくれる。説明不足でない程度には親切で、説明過多でない程度の上品さも良い。
6.『マジック・イン・ムーンライト』(ウディ・アレン監督)
演:コリン・ファース、エマ・ストーン
ロマンチック・コメディ。舞台は1920年代。エセ霊能力者を告発して名を挙げた人気マジシャン(ファース)が友人の頼みで自称霊能力者(ストーン)のインチキを見破るため、コート・ダジュールへ。しかし、霊能力者はあきらかにトリックを駆使しているようには見えない不思議パワーを次々と発揮、彼女の魅力もあいまってマジシャンは「彼女はホンモノではないのか?」と不安に陥っていく……というお話。
『アメイジング・スパイダーマン』でトッポい使われ方してたエマ・ストーンが本作では最高に輝いていたり、最初は自信満々だったコリン・ファースがストーンにいろんな意味で幻惑されていく様子がキュートだったりと出てくるキャラクターみんながこちらの心臓をわしづかみにしてくる。そのキャラクターの魅力でもってエマ・ストーンの正体を宙吊りにしといてからの真相開示、そしてその後のどんでん返しの観せ方がこれしかない、というクレバーさ。
7.『真夜中のゆりかご』(スサンネ・ビア監督)
演:ニコライ・コスター=ワルドウ、マリア・ポネピー、ウルリク・トムセン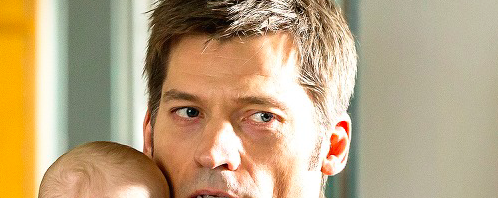
赤ん坊をめぐるクライム・ナーブスリラー。ビアにしろヴィンターベアにしろ日本に入ってくる最近の北欧映画ってだいたいまあ暗いんですが、『真夜中のゆりかご』はそのなかでもトップクラスの嫌さを醸し出している。90年代っぽい神経症的なスリラーをより洗練した形で見事に造形しなおした重厚な作品です。
8.『ホーンズ 容疑者と告白の角』(アレクサンドル・アジャ監督)
演:ダニエル・ラドクリフ、ジュノ・テンプル、マックス・ミンゲラ
ホラーコメディ・ミステリ。恋人を殺害した容疑をかけられたハリーポッター野郎こと*5ラドクリフ。そんな彼がある朝目覚めると山羊っぽい角が生えていた! しかも、その角は周囲にいる人間に「思ったことをなんでも洗いざらい喋らせてしまう」という不思議なパワーを具えており、窮地のハリーポッター野郎は自らの無実を証明すべく、角を利用した真犯人探しへと乗り出す、といった内容。
不条理な笑いに満ちているけれど、意外ときっちり捜査ミステリやってる。
9.『ファイナル・ガールズ 惨劇のシナリオ』(トッド・ストラウス=シュルソン監督)
演:タイッサ・ファーミガ、アダム・ディヴァイン、マリア・アッカーマン
ホラーコメディ。女優の母親を交通事故により亡くしてしまった少女(Tファーミガ)がひょんなことから友人たちと一緒に、かつて母が出演していた80年代のB級カルトスプラッタ映画の世界へ迷いこんでしまう。何もかもが「脚本」通りに起こる世界で、いかにモンスターから逃れ、生き延びることができるか。そして少女は再会した母親(映画のなかの世界なので、厳密には母親ではない)を「殺され役」の運命から救うことができるのか?
『スクリーム』後のメタホラーの流れを汲みつつジャンル映画としてのホラーをコメディチックにハッキングした作品というとまず『キャビン』が思い浮かびますが、本作も言ってみればそんな『キャビン』チルドレンの一つ。ただ、単なる 80s パロディに終わらず、スプラッタ・ホラーの枠組みを駆使して友情を描き、ひいては「いかにしてフィクションで人は救われるのか」というなかなかスゴイ域にまで達しています。
10.『薄氷の殺人』(ディアオ・イーナン監督)
演:リャオ・ファン、グイ・ルンメイ、ワン・シュエピン
エロ人妻クライム・サスペンス。見てくれはアート映画だし、事実そのように評価されているけれども、それなりにツイストも仕掛けられていて飽きない。
11.『オキュラス/怨霊鏡』(マイク・フラナガン監督)
アメリカ・ホラー映画界でちゃくちゃくと「観るべき監督」の地位を固めつつあるフラナガンのホラー。
子どものころ両親を「呪いの鏡」に殺された、と信じている姉弟が復讐を果たすためにその鏡を拉致・監禁し、鏡をぶっ壊す方法を探る。
数々の特殊能力(マインドコントロール、幻覚作用)を持つ鏡をいかにして破壊するかをロジカルに探っていくプロセスが面白い。カメラで「現実」を映しといて幻覚と現実を判断したり、鏡に殺されないようにある予防線を張ったり……方向性もスタイルもぜんぜん違うけれど、森川智喜の『スノーホワイト』を彷彿とさせる。
12.『22ジャンプ・ストリート』(フィル・ロード&クリストファー・ミラー監督)
演:チャニング・テイタム、ジョナ・ヒル
相変わらずの伏線芸だし十分楽しめたんけれど、やはり一作目の衝撃に比べると……。
13.『インヒアレント・ヴァイス』(ポール・トーマス・アンダーソン監督)
演:ホアキン・フェニックス、ジョシュ・ブローリン、オーウェン・ウィルソン
『三つ数えろ』や『ロング・グッドバイ』などの迷宮系ハードボイルド映画の血統を受け継ぐラリパッパ探偵映画。たぶん原作読むか二度以上観るかしないと事件の構図がよくわからないと思う。それはともかくとして、とにかく楽しい映画です。
14.『ドラフト・デイ』(アイヴァン・ライトマン監督)
演:ケビン・コスナー、ジェニファー・ガーナー、デニス・リアリー
NFL(アメフト)の新人ドラフトが舞台、というかなり変化球なドラマ。ぼんやりしたルールが観客に提示されて、そのルール内で(あるいはその穴をついて)どうやって最大の利益を獲得していくか、という特殊設定本格みたいな趣向がほどこされている。まず、「ドラフト中に指名権(来年以降の分も含む)や選手(その場で獲得した選手を含む)を他球団とトレードできる」という設定が新奇きわまりない。
で、弱小球団のGMを任されているケビン・コスナーが実力主義で新人を採用したい監督と人気優先でスター選手を取りたいオーナーとの板挟みなりつつ、頭脳と弁舌でもって、どうドラフトを乗り切っていくのか、という話。
知能ゲーム仕立てとはいえ、わりとゴリ押しな面も強いので、あんま盲点の論理的なものを期待しすぎるとがっかりする。むしろドラマ部分がしっかり作りこまれていて、そちらのほうに好感を持てるかな。
15.『イニシエーション・ラブ』
演:前田敦子、綾野剛
乾くるみの同名作の映画化。叙述トリック原作の映画化、というと、近年亡くなった某メフィスト作家の某作が思い浮かぶ。あれはあれで興味深かったものの、やはり「逃げ」に走っていた感は否めなかった。
そこにきて『イニラブ』は真っ向勝負をかけてきて、しかもそれを極めて映画的に成功させた、という点で評価に値する。泡坂妻夫リスペクト(主人公の本棚が劇中トリックを示唆している)なんかもあったりして。
「ラスト十分*6は余計だろ」という声はまあわかるんだけど、あれやんないと意味わかってくれない観客だって多いのだし、実際「あれ」をやってもわかってくれなかった客もいたそう*7で。
ミステリとは、つくづくインストールしなきゃいけないプラグインの多い文学ジャンルなのだと思い知らされます。
16.『ジャッジ 裁かれる判事』(デビッド・ドプキン監督)
演:ロバート・ダウニー・Jr. 、ロバート・デュバル、ビンセント・ドノフリオ
いちおう法廷もの(逆転系)だが、主眼はあくまで父子(デュバル、ダウニーJr.)ドラマ。功成り名を遂げた名判事が一転、とある事件の犯人に仕立てられてしまう。その父親を弁護するために現れたのがダウニーJr. 演じる判事の息子兼弁護士。だが、この父子、犬猿の仲だった。「おまえの助けなど借りん!」と意地をはる父親を果たしてダウニーは救えるのか、といった内容。可もなく不可もなし。
17.『リピーテッド』(ローワン・ジョフィ監督)
演:ニコール・キッドマン、コリン・ファース、マーク・ストロング
とある事故のせいで一日ごとに記憶がリセットされる身体になってしまった妻(キッドマン)。夫(ファース)はそんな彼女を献身的に介護する。が、ある時、彼女のもとに医師(ストロング)から電話がかかってきて「君は夫に内緒でビデオ日記をつけているはずだ」と言われる。指示されるがままにデジカメの隠し場所をさぐりあてるキッドマン。そのデジカメには彼女に寄る驚愕の「告白」が記録されていた……。
現実離れした日常で、みるからに怪しいイケメン夫といかにも怪しいイケメン医師のあいだに板挟みになって苦しむキッドマンの煩悶を描いたナーブスリラー。
ネタが明かされていくにつれてどんどん凡庸かつ退屈になっていくのがこの手の宿命的な悲しさだけれど、コリン・ファースの演技力やストロングのハゲ力のおかげでフツーに楽しめる作品にはなってる。
18.『ジョーカー・ゲーム』(入江悠監督)
演:亀梨和也、深田恭子、伊勢谷友介
ニッチ世界史ミステリ作家だった柳広司を一躍売れっ子に押し上げた同名作が原作。アクション出来ない人を演出でごまかせるのが映画のいいところではあるが、そういうのにも限界があるということを教えられる。これに二時間費やすくらいなら、『陸軍中野学校』を観たほうがよい。
19.『ヴィジット』(M・ナイト・シャマラン監督)
演:ディアナ・デュナガン、ピーター・マクロビ―、オリビア・デヨング、エド・オクセンボールド
ホラー。「果たしてこのおばあちゃんは本当に僕達私達の実の祖母なのか!?」という部分の解決はわりとどうでもよくて、むしろ主人公の姉弟がいかにして自分たちの抱えるトラウマを克服していくのか、というプロセスがロジカルな興味で処理されている。
20.『ブラック・ハット』(マイケル・マン監督)
演:クリス・ヘムズワース、ワン・リーホン、ヴィオラ・デイヴィス
天才筋肉ハッカーが香港かどこかでテロリストどもを摘発するために頑張るクライムアクション。
一応謎解きパートみたいなものも挿入されているけれど、基本は銃撃戦を観て聴くための映画。
あとよく「こんなマッチョなITギークいないだろっw」みたいにツッコむやつらがおりますが、おいおい、筋肉ハッカーだぞ、ロマンだろが。
21.『シグナル』(ウィリアム・ユーバンク監督)
演:ブレントン・スウェイツ、ローレンス・フィシュバーン、オリビア・クック、ボー・ナップ
SFスリラー。MITで毎日たのしいギークライフを送る大学生(スウェイツ)が謎のハッカーを追ううちにたどり着いたネヴェダで、友人たちといっしょに謎の組織に拉致監禁されてしまった! ので、彼らは怪しい職員(フィッシュバーン)の魔手をふりほどき、施設からの脱出を試みる。
予告編でも明かされていたけど、少年たちがスーパーな特殊能力を獲得するSFスリラー。演出が死ぬほどねむたいし、オチも六十年代レベルのコテコテさに溢れているけれども、SFXは良かった。
22.『ギリシャに消えた嘘』(ホセイン・アミニ監督)
演:ヴィゴ・モーテンセン、キルスティン・ダンスト、オスカー・アイザック
みんな大好きパトリシア・ハイスミスの『殺意の迷宮』が原作。アテネで出会った青年と詐欺師夫婦の三角関係珍道中を描いた重めのノワールだったような記憶もあるけど、まったく頭に残ってない。
23.『毛皮のヴィーナス』(ロマン・ポランスキー監督)
演:エマニュエル・セニエ、マチュー・アマルリック
会話劇コメディ。同名の戯曲のオーディションというシチュエーションで、謎の女セニエが高慢な演出家アマルリックを翻弄していく。巧みな演出とメタファーと演技で世評こそ高いけれど、大筋としてはセニエのワンサイドゲームが90分まるまる続くだけなので、雑に観ると退屈するし事実退屈だった。
24.『ハイネケン 誘拐の代償』(ダニエル・アルフレッドソン監督)
演:アンソニー・ホプキンス、ジム・スタージェス、サム・ワーシントン
誘拐された大富豪のホプキンスが口先三寸で誘拐犯グループたちの絆を崩していく……と宣伝されたように覚えているんだけど、実際そんなにホプキンスは活躍せず、誘拐犯たちが勝手に自滅していった印象。
25.『花とアリス殺人事件』(岩井俊二監督)
声:蒼井優、鈴木杏
百合アニメ。『花とアリス』の前日譚。クラスで畏敬を集める霊能力少女の謎! みたいなパートもあるけど三十分くらいでネタばらしされる。それはともかくフツーに傑作です。
見逃した重要作と備考:
『ソロモンの偽証』(前後編):キネ旬の日本映画ランキングでミステリとしては最上位にランクイン。
『白い沈黙』:ミステリ作家やミステリ評論家が絶賛コメントを寄せていた。
『ベルファスト’71』: metacritics の「2015年に公開された映画ランキング」の「ミステリ・スリラー・サスペンス部門」で第一位。
他にもインドリダソンの『湿地』が映画化されて東京で特集上映されてたらしいですが、そんなもんまで追えねえよ。

- 発売日: 2015/06/30
- メディア:Amazonインスタント・ビデオ
- この商品を含むブログを見る

- 作者:パトリシアハイスミス,榊優子
- 出版社/メーカー:東京創元社
- 発売日: 1988/07
- メディア:文庫
- この商品を含むブログ (2件) を見る
2015年に読んで面白かった新刊大賞
参考:2011年読書まとめ - フィララバキシア
今更2013年新作のベスト - フィララバキシア
2014年度新本格新刊本屋大将大賞 - フィララバキシア
犬の力――2015年度8月までのポケミス・ラウンドアップ - フィララバキシア
去年は絶望的に読んでなかったので、去年のまとめみたいなテンションで書けない……。
読書ログを呼び出す元気もないので思い出してなんとかやります。
わたしの一ダース
ミュリエル・スパーク『ブロディ先生の青春』

- 作者:ミュリエルスパーク,Muriel Spark,木村政則
- 出版社/メーカー:河出書房新社
- 発売日: 2015/09/25
- メディア:単行本
- この商品を含むブログを見る
デイヴ・エガーズ『ザ・サークル』

- 作者:デイヴエガーズ,Dave Eggers,吉田恭子
- 出版社/メーカー:早川書房
- 発売日: 2014/12/19
- メディア:単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (5件) を見る
後半にかけての展開は飛躍がすぎる感もあるけれど、その大味さを含めて愉快です。
ミハイル・エリザ―ロフ『図書館大戦争』

- 作者:ミハイルエリザーロフ,北川和美
- 出版社/メーカー:河出書房新社
- 発売日: 2015/11/26
- メディア:単行本
- この商品を含むブログ (5件) を見る
「フィクションも楽しいだけど、現実も大事だよね」だとか「現実社会に対して示すべき健全さ」などといった常識的な視点は完全に欠落していて、ただドラッグとしての読書が称揚されている。本は楽しい、本は面白い、本のない人生なんて生きるに値しない。幻想が現実なんだ。これがウクライナ人作家のソ連時代に対するノスタルジーから生まれたというのだから、おそろしい。
そういえば、ソ連とは本と本への幻想から生まれた国だったなあ、と思い起こさせる。
ミランダ・ジュライ『あなたを選んでくれるもの』

- 作者:ミランダジュライ,Miranda July,岸本佐知子
- 出版社/メーカー:新潮社
- 発売日: 2015/08/27
- メディア:単行本
- この商品を含むブログ (20件) を見る
しかし、そういうアナログな人々はネットにはびこる人間たちよりよっぽど夢想家なのだ。なぜならいまやネットは現実と地続きだから。むしろ新聞や雑誌といった媒体のほうが非リアルな場だ。
現実派ジュライは現在と現実に取り残された夢想家たちを、ほんわかと、しかしどこまでも冷ややかに観察する。ところがある一点で、彼女はファンタジーの領域に必要と好奇心に駆られ、進んで足を踏み出す。そこで奇跡が起こる。フィクションに「選ばれる」人間というのは確実に存在するのだな、と思います。
ルース・レンデル『街への鍵』

- 作者:ルース・レンデル,山本やよい
- 出版社/メーカー:早川書房
- 発売日: 2015/08/07
- メディア:単行本
- この商品を含むブログ (9件) を見る
なぜレンデルというミステリ作家(本人はそう呼ばれることを嫌っていたが)が巨匠と呼ばれていたのか、『ロウフィールド館』を読んだときにはよくつかめなかったその事実が、本書ではよく実感できた。
アンドリューホッジス『エニグマアラン・チューリング伝 』

- 作者:アンドルーホッジス,Andrew Hodges,土屋俊,土屋希和子
- 出版社/メーカー:勁草書房
- 発売日: 2015/02/20
- メディア:単行本
- この商品を含むブログを見る
倉橋由美子『最後の祝宴』

- 作者:倉橋由美子
- 出版社/メーカー:幻戯書房
- 発売日: 2015/05/26
- メディア:単行本
- この商品を含むブログ (4件) を見る
この人の視力を明晰にしているのは何も憎しみだけでない気がする。
ロベルト・ボラーニョ『アメリカ大陸のナチ文学』

- 作者:ロベルト・ボラーニョ,野谷文昭
- 出版社/メーカー:白水社
- 発売日: 2015/06/04
- メディア:単行本
- この商品を含むブログを見る
トレヴェニアン『パールストリートのクレイジー女たち』

- 作者:トレヴェニアン,江國香織
- 出版社/メーカー:ホーム社
- 発売日: 2015/04/03
- メディア:単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (8件) を見る
ジュディ・バドニッツ『元気で大きいアメリカの赤ちゃん』

- 作者:ジュディバドニッツ,Judy Budnitz,岸本佐知子
- 出版社/メーカー:文藝春秋
- 発売日: 2015/02/07
- メディア:単行本
- この商品を含むブログ (9件) を見る
ウラジミル・ソローキン『ブロの道 氷三部作:一』

- 作者:ウラジーミルソローキン,Vladimir Sorokin,松下隆志
- 出版社/メーカー:河出書房新社
- 発売日: 2015/09/28
- メディア:単行本
- この商品を含むブログ (9件) を見る
ラヴィ・ティドハー『完璧な夏の日』

- 作者:ラヴィ・ティドハー
- 出版社/メーカー:東京創元社
- 発売日: 2015/02/21
- メディア:Kindle版
- この商品を含むブログを見る
マンガ
単発
たかみち『百万畳ラビリンス』*2

- 作者:たかみち
- 出版社/メーカー:少年画報社
- 発売日: 2015/11/11
- メディア:Kindle版
- この商品を含むブログ (2件) を見る
平方イコルスン『駄目な石』

- 作者:平方イコルスン
- 出版社/メーカー:白泉社
- 発売日: 2015/04/27
- メディア:コミック
- この商品を含むブログ (6件) を見る
速水螺旋人『螺旋人同時上映』

- 作者:速水螺旋人
- 出版社/メーカー:講談社
- 発売日: 2015/12/22
- メディア:コミック
- この商品を含むブログ (14件) を見る
窓ハルカ『俗の金字塔』

- 作者:窓ハルカ
- 出版社/メーカー:リイド社
- 発売日: 2015/09/11
- メディア:コミック
- この商品を含むブログを見る
縁山『だいたいめる子』

だいたいめる子 (WANIMAGAZINE COMICS SPECIAL)
- 作者:縁山
- 出版社/メーカー:ワニマガジン社
- 発売日: 2015/08/10
- メディア:コミック
- この商品を含むブログ (5件) を見る

- 作者:小島アジコ,麻草郁
- 出版社/メーカー:KADOKAWA/アスキー・メディアワークス
- 発売日: 2015/06/26
- メディア:コミック
- この商品を含むブログ (4件) を見る
志村貴子『わがままちえちゃん』

- 作者:志村貴子
- 出版社/メーカー:KADOKAWA/エンターブレイン
- 発売日: 2015/03/25
- メディア:コミック
- この商品を含むブログ (14件) を見る

- 作者:近藤ようこ
- 出版社/メーカー:KADOKAWA/エンターブレイン
- 発売日: 2014/12/25
- メディア:コミック
- この商品を含むブログ (3件) を見る

フォービリオンナイツ ~久正人傑作短編集~ (アース・スターコミックス)
- 作者:久正人
- 出版社/メーカー:泰文堂
- 発売日: 2015/02/12
- メディア:コミック
- この商品を含むブログ (6件) を見る
模造クリスタル『ビーンクとロサ』

- 作者:模造クリスタル
- 出版社/メーカー:イースト・プレス
- 発売日: 2015/03/15
- メディア:コミック
- この商品を含むブログ (6件) を見る
完結マンガ臨終図鑑
涼川りん『りとる・けいおす』

- 作者:涼川りん
- 出版社/メーカー:双葉社
- 発売日: 2014/10/28
- メディア:コミック
- この商品を含むブログを見る
室井大資『秋津』

- 作者:室井大資
- 出版社/メーカー:エンターブレイン
- 発売日: 2012/10/15
- メディア:コミック
- 購入: 7人 クリック: 157回
- この商品を含むブログ (20件) を見る

リューシカ・リューシカ 1 (ガンガンコミックスONLINE)
- 作者:安倍吉俊
- 出版社/メーカー:スクウェア・エニックス
- 発売日: 2010/06/22
- メディア:コミック
- 購入: 19人 クリック: 328回
- この商品を含むブログ (104件) を見る
白浜鴎『エニデヴィ』

- 作者:白浜鴎
- 出版社/メーカー:エンターブレイン
- 発売日: 2013/06/15
- メディア:コミック
- この商品を含むブログ (9件) を見る
うさくん『にゃん天堂』

- 作者:うさくん
- 出版社/メーカー:KADOKAWA/アスキー・メディアワークス
- 発売日: 2015/07/24
- メディア:コミック
- この商品を含むブログを見る
河添太一『謎解きドリル』

- 作者:河添太一
- 出版社/メーカー:スクウェア・エニックス
- 発売日: 2014/09/22
- メディア:コミック
- この商品を含むブログを見る
岡村星『ラブラブエイリアン』

- 作者:岡村星
- 出版社/メーカー:日本文芸社
- 発売日: 2014/03/14
- メディア:Kindle版
- この商品を含むブログ (1件) を見る
道満晴明『ヴォイニッチ・ホテル』

- 作者:道満晴明
- 出版社/メーカー:秋田書店
- 発売日: 2010/11/19
- メディア:コミック
- 購入: 28人 クリック: 326回
- この商品を含むブログ (77件) を見る
たばよう『宇宙怪人みずきちゃん』

宇宙怪人みずきちゃん 1 (少年チャンピオン・コミックス・タップ!)
- 作者:たばよう
- 出版社/メーカー:秋田書店
- 発売日: 2014/06/06
- メディア:コミック
- この商品を含むブログ (2件) を見る
だが、たばようは間違いなく二十一世紀において最も卓抜して「リアル」で「ヤバい」漫画家なのだ。
以って瞑すべし。
連載第一巻
まつだこうた『おかか』

- 作者:まつだこうた
- 出版社/メーカー:講談社
- 発売日: 2015/10/06
- メディア:コミック
- この商品を含むブログを見る
横山旬『変身!』

- 作者:横山旬
- 出版社/メーカー:KADOKAWA / エンターブレイン
- 発売日: 2015/04/25
- メディア:Kindle版
- この商品を含むブログを見る
松田洋子『私を連れて逃げて、お願い』

- 作者:松田洋子
- 出版社/メーカー:KADOKAWA/エンターブレイン
- 発売日: 2015/01/24
- メディア:コミック
- この商品を含むブログ (5件) を見る
ペトス『亜人(デミ)ちゃんは語りたい』

- 作者:ペトス
- 出版社/メーカー:講談社
- 発売日: 2015/03/06
- メディア:コミック
- この商品を含むブログ (7件) を見る
沙村広明『波よ聞いてくれ』

- 作者:沙村広明
- 出版社/メーカー:講談社
- 発売日: 2015/05/22
- メディア:コミック
- この商品を含むブログ (28件) を見る

- 作者:志村貴子
- 出版社/メーカー:太田出版
- 発売日: 2015/04/14
- メディア:コミック
- この商品を含むブログ (14件) を見る
小路啓之『メタラブ』

- 作者:小路啓之
- 出版社/メーカー:講談社
- 発売日: 2015/05/22
- メディア:Kindle版
- この商品を含むブログを見る

- 作者:山口貴由
- 出版社/メーカー:秋田書店
- 発売日: 2015/10/20
- メディア:Kindle版
- この商品を含むブログ (1件) を見る
画・青木雅彦、原・柴田ヨクサル『プリマックス』、柴田ヨクサル『妖怪番長』

- 作者:蒼木雅彦,柴田ヨクサル
- 出版社/メーカー:集英社
- 発売日: 2015/09/18
- メディア:コミック
- この商品を含むブログ (4件) を見る

- 作者:柴田ヨクサル
- 出版社/メーカー:講談社
- 発売日: 2015/05/22
- メディア:Kindle版
- この商品を含むブログを見る
久正人『ジャバウォッキー1914』

- 作者:久正人
- 出版社/メーカー:講談社
- 発売日: 2015/10/09
- メディア:コミック
- この商品を含むブログ (8件) を見る
画・雨依新空、原・夢枕獏『ヴィラネス 真伝・寛永御前試合』

ヴィラネス -真伝・寛永御前試合-(1) (ヤンマガKCスペシャル)
- 作者:雨依新空,夢枕獏
- 出版社/メーカー:講談社
- 発売日: 2015/03/06
- メディア:コミック
- この商品を含むブログを見る
奇想短編ベスト
ケヴィン・ウィルソン「今は亡き姉ハンドブック:繊細な少年のための手引き」(『地球の中心までトンネルを掘る』)
カレン・ラッセル「帰還兵」(『早稲田文学2015年夏号』)
リディア・デイヴィス「甲状腺日記」(『サミュエル・ジョンソンは怒っている』)
ジュディ・バドニッツ「セールス」(『元気で大きいアメリカの赤ちゃん』)
ジュディ・バドニッツ「ナディア」(『元気で大きいアメリカの赤ちゃん』)
平方イコルスン「19話/『スペシャル)』(トーチweb)
マクレーンコミックス「第8話/『怒りのロードショー』(月刊コミックニート)
カフカ、多和田葉子訳「変身」(『ポケットマスターピース1 カフカ』)
澁澤龍彦「久生十蘭のこと」(『文芸の本棚 久生十蘭』)
感想
あんまり上手い海外ミステリ読んでも心に響かなくなってきた。
今年はもっと必至にやります。なんか毎年言ってる気がするけど。
今週のトップ5
1.ジェームズ・ポンソルト監督『人生はローリングストーン』
アメリカにデイヴィッド・フォスター・ウォレスという小説家がいた。一九六二年生まれだから、町田康やチャック・パラニュークなどと同い年で、パラニュークに至っては月日(二月二十一日)まで一緒だ。
一九九六年出版のディストピア大作『Infinite Jest』*1で一躍名声を博し、ピンチョンなどの流れを汲む米ポストモダン文学の寵児として文壇に迎えられた男である。彼はその後もノンフィクションや短編を中心にコンスタントに作品を発表をしつづけ、十数年ぶりとなる長編『The Pale King』を準備している最中の二〇〇八年に唐突な自死を遂げた。その三年後、『The Pale King』は未完ながら出版され、翌二〇一二年のピューリッツァー賞の最終候補にノミネートされた*2
日本人好きする劇的な人生を送ったわりに本邦じゃマイナー以下の存在で、せいぜい初期作が数冊訳された程度。おそらくはピンチョン並に重厚かつ難解なのに、ピンチョンほどいろんな面でペイしないせいだろう。それでも英語圏では今でもリスペクトされている。彼の死に際して弔辞を寄せた面々を眺めると、その偉大さと文学的重要性を察せるかもしれない。: ドン・デリーロ、ゼイディー・スミス、ジョージ・サウンダース、そしてジョナサン・フランゼン……
映画は二〇〇八年、作家のデイヴィッド・リプスキー(ジェシー・アイゼンバーグ)のもとに「ウォレス(ジェイソン・シーゲル)が自殺した」という電話がかかっているところから始まる。リプスキーは、一九九六年に『Infinite Jest』の出版ツアー*3で『ローリング・ストーン』誌の記者としてウォレスに五日間ほど密着取材を行った経験があった。リプスキーはその時の奇妙な、しかし得難い体験をつらつら思い出す……と書くと「なぜウォレスは自殺したのか?」というホワイダニット的な謎解き話に傾くのかな、と最初は疑われるかもしれない。しかし、本作はそれはあくまで刺し身のつま程度の扱いというか、言ってしまえば観終わったところで稀代の文人の自殺理由など判明しない。そこではない、この映画はそこではないのだ。
では、本作の主眼といいますか楽しみどころは、といいますと、「才能はあるけど、自意識過剰でめんどくさい文学青年」と「才能はあんまりないけど、やっぱり自意識過剰でめんどくさい文学青年」、彼ら二人のめんどくさい自意識のぶつかり合いと交流にある。
インタビュアーとインタビュイー、傍目から見たら彼らの関係はそれだけでしかない。しかし重要なのはインダビューする側であるリプスキーもまた数年前に小説を発表した駆け出しの小説家であることで、当初はなんでもないように振る舞ってはいたものの、四つほど年上の成り上がり者に対して常に嫉妬と尊敬が入り混じっている。そう。リプスキーの感情に尊敬が含まれている、というのが事をやっかいにしていて、彼はウォレスの大ファンで、『Infinite Jest』を不世出の大傑作だと思っている。
だから、「こんな偉大な作品を書けるやつは何か人として偉大な部分があるに違いない」と考えてしまう。
ところが、実際に会ってみるとウォレスは孤独で偏屈な田舎者だ。友達といえば大学時代の知人以外には一緒に暮らす犬くらい*4。かかってくる電話にいらついて電話線を切り、しかし人並みに虚栄心はあり、女好きで、なぜか部屋には九十年代のアイドル・ロック歌手アラニス・モリセットのポスターが貼ってある。「なぜアラニス?」とリプスキーが尋ねると、「うーん、影響を受けたからかな」と言う。
「アラニスが好きなの?」
「うん、一番好きな歌手だ。テレビの向こうの人間って日常があんまり想像できないでしょ。うんこしてるとことか、飯食ってるとことか。でもアラニスに関してだけではそういうとこも一挙手一投足想像できるんだ」
フツーにアイドルファンみたいなことを言う。
「『ローリング・ストーン』に記事に『ウォレスがアラニスに会いたいって言ってる』って書けば、会談をセッティングしてもらえるかもよ?」
「マジで!!!?? やろうやろう」
うーん、俗っぽい。
極めつけはテレビ中毒。ウォレスの家にはテレビが置いていないのだが、それは「テレビがあると何もなくても無際限に観ちゃうから」。
そして、彼は実際にツアー先でどうでもいい三文ドラマばかりを視聴しまくる。カウチにねそべって、知人に「この俳優、大学時代の知り合いでねえ」などと話す姿はどうしようもなくおっさん丸出しだ。連れ立って映画に行こうとするとチョイスはジョン・ウー監督のアクション大作『ブロークン・アロー』。観終わった後に女性陣が口々に内容を dis るのだけれど、ウォレスだけは「いや、トラボルタは世界を救ったんだよ!」と徹底的に擁護する。とても九十年代以降で最も重要な作家の一人に数えられる人物とは思えない親しみやすいボンクラっぷりだ。
そして、器も小さい。
リプスキーの彼女がウォレスの作品のファンだと知るや、リプスキーにかかってきた電話をなかば横取りして三十分も話し続ける。リプスキーは当然イラつくが、ウォレスに対しては文句を言わない。ところが、リプスキーの方がウォレスの元カノと話すと、「おれに隠れてメアド交換しやがっただろ! もう彼女に話しかけるな!」とぶちキレてしまう。
変人といえば変人だけれど、ウィリアム・バロウズほどに振りきれたクレイジーさもなく、ブコウスキーほどのすがすがしさもなく、どちらかといえばセコい欲望と見栄に忠実なアメリカの小市民だ。
こんな人間があの『Infinite Jest』を書いたのか? あの1000ページ超えの大作を? あのディストピア・ポストモダン文学の最高峰を?
リプスキーはそんなはずはないと考え、はぐらかれされつづけたインタビューで溜め込んだフラストレーションとともに「おまえ俺のことバカにしてんだろ!」とウォレスに思いのたけをぶつける。曰く、ウォレスは自分より年下で頭の悪い(で、もちろん売れない小説家でもある)リプスキーのことを低く見ていて、わざと凡人のように韜晦しているのだ、と。
対してウォレスは「いや、僕は平凡な人間だよ。他の人とあまり変わらない」と反駁する。
リプスキーは認めない。「平凡な人間は1079ページの偉大な文学作品を生み出せなどしない! おまえはどこか他人と違ってるはずだ! それを教えろよ!」と叫ぶ。*5
商業的にも批評的にも認められていない「平凡な作家」であったリプスキー*6のはがゆさが伝わってくる名シークエンスだ。
かたや、ウォレスも寂しさや不安を抱えている。彼には翳が多い。薬物中毒の噂やデビュー直後の鬱病などを聞こうとすると、露骨にいらだちを見せる。リプスキーと親しく接しながらも、折々で「でもお前はビジネスでついてきているんだろ?」と確認し、距離を保つ。出版ツアーの終わりごろ、彼は孤独を吐露する。「ツアーの最中は毎日のように人に会えたが、それで友達が増えたわけじゃない。家に帰るとまた知り合いは二十人と犬二匹だけに戻る」。
売れないころは成功しさえすれば自分の書くものに自信を与えてくれるものと信じていたが、売れて賛辞や好評がやまほど送られてくるようになっても、その不安が打ち消せない。雪に閉ざされた一軒家、くすんだ居間、クリップボードに留められた家族写真、トイレの壁に貼られた聖書の言葉、冷蔵庫に貼られたジョークの書かれたネタ記事、本の山……ウォレスの住居は言葉やイメージに埋めつくされて、しかし外とはつながれない。十二年後、彼は自ら死を選ぶ。
アメリカン・ドリームが本質的に救える人間は、実のところ限られているのだ、とこの映画は教えてくれる。成功を手に入れられない人間も不幸なら、成功を手にした人間も不幸だ。それでも、とこの映画は言う。
人と人とが交わることで希望めいた何かが生まれることもある。それが結果として幻だったとしては、その瞬間瞬間にはおそらく嘘はない。ジェームズ・ポンソルト監督が手持ちカメラの狭いフレームにおさめる二人の姿はうじうじしていて、惨めったらしいけれど、どこかほんのり暖かい。ロード・ムービー特有の「失われていく青春の一場面」感がよく捉えられている。
めんどくさいすべての人類が観るべき作品だと思う。
ジェームズ・ポンソルトは日本で前々作にあたる『スマッシュド』もDVDで出ている。こちらはアル中の小学校教師が自分がついた些細な嘘と夫婦関係に翻弄されまくる話で、『人生はローリングストーン』とおなじく全編通じて特に大きな事件が起きるわけではないんだけれど、地味に嫌で人間臭い人々の挙作や機微を非常に明敏に切り取っている。
次作はエマ・ワトソンやトム・ハンクスといったスターを迎えてデイヴ・エガーズ『ザ・サークル』の映画版を撮るそうで、実に良くマッチした人選ですね。

- 発売日: 2016/01/13
- メディア:Amazonインスタント・ビデオ
- この商品を含むブログを見る
2. 菱田正和『KING OF PRISM BY PRETTYRHYTHM』
劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」トレーラー(本編ver.)
なにしろ映画として異形である。
アニメ映画とは通常の商業映画とは異なる文脈で発展してきた文化であり、往々にしてアヴァンギャルドで破格な作品に仕上がることも多い。今公開されているアニメ映画なら『傷物語』や『ガールズ・アンド・パンツァー』もそのひそみのうちだろうか。
だが、キンプリはその文脈すら超越している。
破壊でも逸脱でもない。
超越している。
「観客の感情を物理的に殴り続ける」とはななめちゃんさんの言葉だが、我々に残された最後の抵抗手段はただその意見を張り子の虎のごとく肯いつづけるだけである。
まず、主人公らしいけれど主人公のオーラがまったくない青い髪(純潔の象徴)のパンピー男子が OVER THE RAINBOW(以下OTR)なる三人組のアイドルグループのコンサート会場に現れる。OTRはハートを物理的に振りまいている以外に一見なんの変哲もないアイドルグループで、土曜朝の少女向けアニメにありがちなしょっぱい3Dモデリングでせこせこカクカク奇妙な踊りを踊っている。観客は知りも知覚もしないだろうが、この踊りにはおそらくポケモンで言うところの「どくどく」みたいな効果があり、一ターンごとにHPが倍々で減っていく。しかし、今のところそれはどうでもいい。
主人公はおもむろにペンダントめいたものを取り出し、スイッチ的な何かを押す。
その瞬間に世界が変わる。現実が侵食される。
文字通り、改変される。
ここからの記憶は定かで無い。
まず三人が空を飛んだような気がする。デイヴィッド・ボウイ以後、いまどきのアイドルは空くらい飛べて当然で、これ自体はなにも驚くに値しない。しかし、彼らのうちの一人にカメラが寄ると、キリストの十字架刑のイメージのように両手を広げ、そして四方八方に分身する。なんだこれは……と浮き足立っているところに、鳥山明が書きそうな髪型の色黒やんちゃキャラっぽい少年が竜に乗って現れる。その竜がカテゴリエラーを起こしている。あきらかに『遊戯王』の世界にでも生息してしかるべき赤い、ごつごつしたテクスチャの竜で、まず女性向けアイドルアニメに出てきていいような面構えではない。とっさに、女性向けアイドルアニメに出てきてしかるべき竜とはどのような竜なのか、という疑問が浮かぶがそれに飛びついては駄目である。罠だ。正解は「ここには竜がいるのだ」という現実を受け入れることだ。竜は火を噴いたような気がする。少年は必殺技名を叫んだような気がする。そういう頼りないおぼろげな記憶も、普段なら「そんなもん、あるわけないでしょう」と脳のデフラグが速やかに否定してくれるはずだが、キンプリに限ってはあり得るからタチが悪い。
そう、そこは「何でもあり得る」空間なのだ。キンプリとは何でもあり得る映画なのだ。
なんでもあり得る映画とは、いかにおそろしい映画であることか。
それはすなわち、あらゆる映画のシーンが、あらゆる映像的記憶がそこでは可能だということだ。
たとえば、『オデッセイ』は『インターステラー』や『スター・ウォーズ』ではない。何を言っているんだと思われそうだが、この当たり前を事実を確認することが大事だ。これらには我々の考える以上に厳格な線引がなされている。火星をさまようマット・デイモンはそこでマシュー・マコノヒーと出会ったりなどしないし、カイロ・レンくんとライトセーバーを交えたりなどしない。絶対にしない。なぜなら各作品ごとに世界観やリアリティのレベルが異なるからだ。『インターステラー』は異常気象により人類が存続の危機にさらされた未来の話で、『オデッセイ』は現代にそれなりに近い未来の話で、『スターウォーズ』はほとんどファンタジーだ。ファンタジーは何でも許されてそうな気がするが、しかしスタートルーパーたちは火星でじゃがいもを科学的ロジックに基づいて地道に育てたりしない。設定レベルでしていたとしても、画面にはそれを映さない。それが映画のルールというものだ。
キンプリにはそのルールがない。型がないせいで、型なし、という話でもない。型はある。アイドルアニメという型は厳然と存在する。しかしそれを絶妙なタイミングで、絶妙な箇所で外してくる。
途中である人物がこう叫ぶ。
「まさか……自爆する気か!?」
女性向けでも男性向けでも女児向けでもいい。誰がアイドルアニメを観に行って「自爆」という単語を予測できるだろうか。我々は映画を見に行く時に各々で見えない辞書をたずさえていく。その辞書にはその映画の見た目、あらすじ、ジャンルなどから期待しうる語彙が並べられており、その期待が外れることなどまずありえない。俳優の喋る未知の台詞は、実は一言一句「想定内」なのだ。辞書はあいまいに広くとれるように作られていて、製作者側が想定外のワードを繰り出すのは難しい。『オリエント急行殺人事件』でロシア語の話が出てきても、『アントマン』で量子力学の話になっても、我々は当然の有様として受け取る。そして当然『白鯨との闘い』では白鯨との闘いが語られるのだ。
だが、アイドルアニメで「自爆」とは。
言葉によって我々の意識の盲点をついてくるのは、キンプリにおけるアナログハックの一手段にすぎない。
彼らはもちろん視覚によっても、音によっても、映画という概念を崩しにかかる。
キンプリはまた「感動」の常識を覆す。
通常、ある作品において観客が味わえる総体的な感動は一回だけだ。いわゆるファースト・インプレッションの衝撃というやつである。
初めて鑑賞した作品で、「こんなの観たの初めて!」というフレッシュな感動を味わう。あたりまえの話である。
しかし、キンプリは初めて鑑賞した作品で味わった初体験の感動を、同一作品内で『思い出させて』くれる。四十分前に初めて味わい、しかし四十分後に忘れていないはずなのに忘れてしまった初心をもう一度呼び起こしてくれるのだ。何を言ってるかよくわからないと思うけれども、観ている間もよくわからなかった。だがたしかに感じた。私はあのとき、忘れてしまったピュアな感動をもう一度味わうことができたのだ。
これはもはや映画なのかわからない。アニメなのかすら疑われる。ジョルジュ・メリエス以来のこれまでのどの映像・動画とも似ていない。どう定義すればいいのだろう? 我々の語彙に存在しない異物を、なんと言い表わせばよいのだろう。
いや、実は観さえしたならすでに知っているのだ。激動の六十分を乗り切って、観客の半数が立ち上がることもすらできない七番スクリーン前、我々は知らず、呆然と、その言葉をつぶやく。
「これがプリズムショーか……」
3. 水島努『劇場版ガールズ・アンド・パンツァー』
ニッポンのセックス、って感じ。
キンプリもそうなのだけど、ガルパンも「作り手と受け手がほしいと思ったシーン以外は全オミット」的な作り方で、してみるとウンベルト・エーコが提唱したポルノの定義はもはや賞味期限切れなのかもしれない。
それにしても公開から三ヶ月近く経っているのにまだ日三回上映してるなんて……。
4. ロバート・ゼメキス『ザ・ウォーク』
私にまだ心というものがなかった時代に読んだ円谷英二の伝記漫画によれば、円谷英二は『キング・コング』の上映から出てきた観客がパンフレットをくしゃくしゃに握りしめているのを見て、「こういうふうにさせる映画を作らなければダメだ」と決意したらしい。で、その後『ゴジラ』の観客も同様の反応を示したのを見て、彼は溜飲を下げたとかなんとか。
「圧倒的な体験」の作用として人間の無意識下の行動や生理へダイレクトに働きかけてくる映画というのはある。キンプリの話ではない。
3Dだとか IMAXだとか 4DX だとかはそういう圧倒的な体験としての映画の効果を最大限にアンプリファイしようという涙ぐましい努力が産んだ装置で、ところがこれまで十全にその賜り物を活かしきった映画はあんまりなかった。
『ザ・ウォーク』もスクリーンの表層だけなぞればそういう映画のひとつみたいに思える。題材からして落ちる落ちないの系ドキドキハラハラサスペンスアクションかとおもいきや、途中から主人公が人間を超越して綱渡りの神みたいになってしまって、「こいつはおちねーだろ」というモードに入ってしまう。ウリだったはずの「地上411mからの眺め」も IMAXですらなんだか物足りない気がする。それもそうで、我々は「実際」に東京タワーやエッフェル塔からの眺めをその眼でその手でその脚で直に味わってしまっている。ジョゼフ・ゴードン=レヴィットが命をかけたつなわたりを行っているあいだ、観ているこちらの肌は風ひとつ感知せず、眼は前の席に座った客の頭を捉え、「これは映画だ」と絶望めいた安心感を得ている。興奮などしようがないではないか?
なのに、なぜだろう。
途中から手のひらが湿っているのを感じた。そもそも自分が指を曲げて拳を握っていたことにそれまで気づかなかった。手汗だ。普段まったく手汗なんて、ましてや映画を観ている最中にはまず何も分泌しないはずの自分のアポクリン腺が、静かにかつしたたかに、「これはヤバい」と囁いていた。いつもなら脳が担当するはずの裁定を、この作品に限っては手の平が行ったわけだ。
もしかしたら、それは初めて味わった「圧倒的な体験」だったのかもしれない。
5. スコット・クーパー『ブラック・スキャンダル』
スコット・クーパーという人はなんだかよくわからない映画監督で、あらすじと俳優とルックスから期待される「えげつないノワール」を脱臼させて後味が良いようなそうでないような、面白いようなつまらないような映画を作る。
前作の『ファーナス』もそういう感じで、個人的には大好きだったんだけど、世間的には「重いし長い」、六十点くらいの評価だった。今後もそういう見た目は重厚長大なんだけど終わってみればなんか微妙……な失敗したアンドリュー・ドミニクみたいな(ドミニクが成功しているかはさておき)作品を作り続けていくんだろうし、そうあってほしいとホント思う。
一方で『ブラック・スキャンダル』は映画の題材として複雑すぎた面もある。この映画はサウスボストンをシめていたギャングが情報屋としてFBIとつながっていて、FBIは見返りに人殺しや強盗を見逃していたという実話を元にしている。だけれど、同じ題材を扱ったドキュメンタリー『ホワイティ容疑者を捕まえろ』(ネットフリックスで観られる)を見るにつけ、実際はこんなシンプルな図式ではなかったようだ。事件を担当した弁護士らの調査によると、ギャングがFBIに提供したとされる情報は実はFBI側で捏造されたもの(他のチクり屋の情報のコピペ)で、実はギャングは情報提供者ではなかったというのだ。すると、FBIはなんの見返りもなしにギャングを野放しにしていたことになる。そんなことをして、FBIに何の利益があるんだろう? もちろん、FBI自身がそんなこと認めるわけもなく「ギャングは実際に情報提供者だった」「報告書が混乱するのはよくあること」と言い訳している。真相は藪の中。
『ブラック・スキャンダル』のほうでは不可解な「捏造」にある一定程度の理由付けを行っている。ギャングと(同じアイルランド系として)幼なじみであるFBI捜査官の憧れまじりの友情だ。
その捜査官は劇中「世の中には法律なんかより大事なことがある。地縁や血縁に基づいた『仲間』だ」と述べる。
ちょうど今公開されているスピルバーグの『ブリッジ・オブ・スパイ』ではトム・ハンクス演じる弁護士がアメリカの国家精神の基盤として「君はドイツ系、僕はユダヤ系。異なる出自を持つ民族を同じ『アメリカ国民』たらしめているのは法なんだよ」と唱えたのと対になっているように思える。どっちかが、というより、どっちもアメリカなんだろう。
6. パトリシア・ハイスミス『キャロル』(河出文庫)

- 作者:パトリシアハイスミス,Patricia Highsmith,柿沼瑛子
- 出版社/メーカー:河出書房新社
- 発売日: 2015/12/08
- メディア:文庫
- この商品を含むブログ (13件) を見る
イヌが殺される映画について
これ読んで、そういえば犬映画について考えをまとめとく機会を持っていなかったな、と思い出す。
メモ代わりに軽く整理しておきたい。このエントリは性質上、映画の展開のネタバレを孕みます。
最近の映画で「イヌが死ぬ話」といえば、『ジョン・ウィック』がまず挙がる。
引退した伝説の殺し屋ジョン・ウィックは亡き妻が遺した仔犬をチンピラに虐殺され、復讐を決意。ロシアン・マフィアをまるごと敵に回して大立ち回りを繰り広げる。あまりに殺しまくるので敵から「たかがイヌのためになんでここまで……」と突っ込まれる。
実のところ、チンピラが殺したのは「たかがイヌ」などではなく、「ジョン・ウィックの妻が遺したイヌ」であり、彼岸に旅だった妻(とその思い出)との架け橋となる存在だった。ともすればジョン・ウィックにとっては亡き妻そのものの象徴だったわけで、観客はそれをわかって観ているから「たかがイヌ」とはあなどらない。
ここで見当はずれな疑問を呈することを許してもらいたい。:「では、『ジョン・ウィック』の物語はイヌ以外では成立しえたのか?」
妻がジョンに遺したのがネコだったとして、ピラニアだったとして、ツチブタだったとして、観客は復讐に走るジョンに感情移入できただろうか?
『ジョン・ウィック』の序盤では本当に簡素ではあるが、仔犬とジョンが日常生活を通じて交流を深めるシーンが描写されている。これがイヌ以外であったなら、妻を亡くしたことによる心の傷が癒されていくジョンの姿にあれほど心打たれただろうか?
そう、『ジョン・ウィック』で殺されるべき動物はイヌでなければならなかった。ネコやツチブタでは亡妻とつながれなかった。なぜならイヌは映画において、人間の依代となるように描かれてきた文脈があるから。
いかさま、映画におけるイヌの第一義とは人間の身代わりだ。
身代わりと言ってもその形態は多用で、「友人としてのイヌ」というオーソドックスな役回りから、「(現在はいない)ある人の思い出のよすがとしてのイヌ」、そして文字通り「主人公の代わりに犠牲になるイヌ」までまあ色々いる。ここでは特に詳しくカテゴリ分けしない。
で、漠然と挙げたこれらのうち、このエントリで扱うのは最後のタイプのイヌ、人間のスケープゴートとしてのイヌだ。
映画の中で死ぬイヌは多い。劇中で動物が虐待を加えられているシーンの有無を調べることのできるウェブサイトDoes the Dog Dieもサイト名を訳せば「イヌ、死んじゃうんですか?」で、映画におけるイヌのパブリック・イメージがよくわかる。暴力的な映画で善良な人物がイヌを伴って出てきたら、まずそのイヌは百二十分以内に何らかの逢難にみまわれるものと覚悟しておいたほうがいい。
反面、ハリウッドの大作ムービーではなぜか「なんだかんだでイヌと子どもは殺しちゃダメ」という強い風潮というか暗黙のコードが共有されている。いちばんわかりやすいのは『アルマゲドン』の冒頭だろうか。制作予算の多寡で生き死にが左右されると思うとイヌも大変だなあ、とあわれをもよおしますね。
まあ死ぬにせよ暴力に晒されるにせよ、直截的にそうしたシーンが描かれることはめったにない。『俺たちポリティシャン!』でウィル・フェレルがイヌ(『アーティスト』で脚光を浴びた俳優犬アギー)をドアップかつスローモーションで殴りつけるシーンを観た時はフェイクとわかっていたとはいえ、「え? これ、大丈夫なの? 怒られない?」とひとり勝手に冷や汗をかいた。『25時』でのスパイク・リーや、『ファニーゲーム』のハネケですらそこまではやらなかったのに!
www.youtube.com
『ライフ・アクアティック』より、「イヌに危害を加えるシーンは直截的に描かない」という不文律の例。*1
それはさておきつ、スケープゴートとしてのイヌである。
いまさら述べるまでもなく、イヌは有史以前から人類と偕老同穴の契りを結んできた特別な家畜だ。時代や地域によって扱いがピンキリだったネコ*2と異なり、イヌは一貫して人類の忠実なパートナーでありつづけた。イヌのほうも家畜化の過程でジェスチュアに関する認知能力を高めていき*3、飼い主と高いレベルでのコミュニケーションをとれるように進化していった。そうして人間にとって特に親密な家畜としての地位を築いたイヌは、いつからか飼い主たる人間を映す鏡として機能するようになった。川端康成の形容するところの「犬は人なり」*4というやつ。
そういうイヌ-人の関係の歴程をふまえれば、今日のフィクションにおいてイヌが強い擬人化傾向をほどこされるようになったのも大した不思議に映らない。いくつかの映画において犬が人間と同等の役割を演じるようになった*5のは、ごく自然な流れだったわけだ。犬映画史を丹念に調べたことはないので断言はしかねるけれど、犬は映画のわりあい初期の段階から優れた俳優として重用されてきたのではないかと思われる。
そうして、「頼れる相棒」としてのイヌたちが映画の陽の部分で活躍する*6一方で、陰の部分では薄暗い役割も押しつけられきた。暴力をふるわれたり、無残に殺されたり……。では、具体的に、どういった場面でイヌたちは人間の代わりに犠牲となるのか。
例を指折り挙げていこう。
トマス・ヴィンターベアの『偽りなき者』では、幼い少女を強姦した疑惑をかけられた主人公が居住する田舎の村で壮絶な村八分を受ける。村民たちは表立って襲いかかったりはしないものの、主人公を非難がましい目でみつめ、彼の生活を外縁からゆっくりじわじわとしめつけてくる。中盤、主人公の家の玄関に黒いゴミ袋が出現する。おそるおそる開けてみると、中に入っていたのは主人公の愛犬の変わり果てた姿だった。
ミヒャエル・ハネケの『ファニー・ゲーム』では、サイコパスじみた謎の二人組により幸せな一家の団欒が破壊されるのだが、そのとき真っ先に殺されるのは一家の飼い犬である。
ヒッチコックの名サスペンス『裏窓』では動けない探偵役である主人公の代わりに近所のイヌが重要なヒントを探りだす。このイヌがうろうろ嗅ぎまわっていた花壇で何者かによって惨殺されたことで、主人公と観客は花壇に何かがあるのだと推理する。
ホラー映画のジャンルはイヌの屠殺場といってもいい。現代アメリカン・ホラーの旗手ジェイムズ・ワンが手がけた『死霊館』では、誰よりもまず主人公家族の飼い犬が犠牲となる。
人間に飼われていなければ安心かといえばそうでもない。『フルートベール駅で』では野良犬が路上で轢かれて放置される。
これらの映画に共通しているのは、イヌの死がやがて主人公に襲いかかるであろう受難の先触れとして描写されている点だ。たとえば『偽りなき者』では犬の死体はメタファーであると同時に、敵対者からの強烈なメッセージ(「お前もこんな目にあわせてやる」)でもある。悪意に対して真っ先に捧げられる供物としてのイヌをどう扱うによって、その後の人間の扱いも決まってくる。そして、犬が遭難するまさにその瞬間から物語はクライマックスに向けて加速していく。ホラー作品では特にこの傾向が顕著で、おそらく作り手のほとんどは犬を転調のための句読点くらいにしか考えてない。
敵として描かれる場合はちょうど視点が逆転する。敵としてのイヌは、ラスボスにたどり着く過程における最初の中ボス的存在だ。
典型例は番犬である。番犬とは戦闘的な警報装置のことで、鼻が利き気配にも敏感な彼らはひそやかに目的地へ潜入したい泥棒やスパイたちにとって厄介な障壁だ。『ファンタスティック Mr. Fox』でも鶏どろぼうを働くミスター・フォックスの前にビーグル犬が第一の敵として立ちはだかる。
スナイパー映画『山猫は眠らない』では海兵隊のベテランであるベケット上級曹長が彼らを嗅ぎまわるイヌを回避するため、自分の身体にイヌの糞を塗りたくる。
どちらも大した知恵ではないが、クライマックスに向けて高まるテンションを段階的に盛り上げる役目を果たしている。そして、彼らもまた、敵の人間の身代わりとして捧げられたイヌなのだ。
レバノン内戦を経験したイスラエル兵士たちのドキュメンタリー『戦場でワルツを』の冒頭で描かれる監督アリ・フォルマンの同僚の夢――パレスチナの村を襲撃する際に「おまえは人間を殺せないから」と村内の犬の鏖殺を命じられた彼は、毎晩二十六匹の猛犬に追いかけられる悪夢にうなされる――が監督自身のドキュメンタリー制作のきっかけとなったのは、偶然以上の意味がある。
ちなみにメタファーとしてではなく、マジに人間の代わりとして殺されるイヌもいる。『地獄の逃避行』で殺されるイヌは罪を犯した飼い主の代わりに罰せられる。*7
まとむるに、イヌは動物俳優として異例ともいえるほどの厚遇を受け、ときに人間と同等の役割と人格を賦与されてきた。が、同時にイヌはやはりどこかで人間より若干落ちる存在であり、そのせいで「後に人間へ降りかかる受難を予告するもの」として酷い目にあったりする。そうしたイヌたちのことを、ここでは「スケープゴートとしてのイヌ」と呼ぶ。*8ここで何かしらの神話や民俗の引用など挿入するとカッコいいのだが、特に何もおもいつかない。
イヌを死なせたままにするのは、飼い主が無力だからだ。愛犬が死んでとりあえず悲しいけれど、これから自らの身にふりかかる艱難辛苦やサイコキラーを思えばなんぼのもんでもない。こうしてイヌの死は舞台の後景へ退いていく。
だがしかし。死なされた犬の飼い主が一定レベルの殺人術の持ち主であり、かつ殺した主体が明確に殺せる対象である場合、『ジョン・ウィック』や『極大射程』といった「イヌを酷い目に合わせたやつは死んでもいい」系の映画*9が爆誕する。人間未満の声なき嬰児としてイヌをあわれんで、マッチョな人間様が復讐を代行するのだ。*10そこにはまだ人間の犬に対する優越性、そんな傲慢が読み取れる。
2015年最強のイヌ映画である『ホワイト・ゴッド』はそこから一歩進んで、イヌ自身の手(という牙)で酷い目にあわせた人間どもに対して復仇を果たす。『ホワイト・ゴッド』を観た政治的に意識の高い観客はおそらく擬人化度合い高めなイヌたちの造型について、ある種の反撥を抱く。が、『ホワイト・ゴッド』は単なる犬の反逆暴動映画ではない。あの映画は、そんな小さな作品ではない。ああした擬人化を行うことで「スケープゴートとしての犬」を形成してきたイヌの映画史に対するイヌたちによる壮大な反逆、それこそが『ホワイト・ゴッド』の本質だった。今はそう思います。たぶんね。

- 作者:四方田犬彦
- 出版社/メーカー:集英社
- 発売日: 2015/06/26
- メディア:単行本
- この商品を含むブログ (2件) を見る
*1:どうでもいいが、本作にかぎらずウェス・アンダーソン作品ではよくイヌが虐待される。『ファンタスティック Mr.Fox』では毒入りブドウを食べさせられ、『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』では車に轢かれて死に、『ムーンライズ・キングダム』では矢で射られて殺される。『ダージリン急行』では犬顔のエイドリアン・ブロディがいじめられているし、まあ似たようなもんだろう。『グランド・ブダペスト・ホテル』ではついにネコにまで手をのばしはじめる。盟友たるノア・バームバックも悪い影響を受けたのか『マーゴット・ウェディング』ではWアンダーソンの某作を想起させる酷な目にあわせている。もしかしてウェス・アンダーソン、犬が嫌いなんかな、と思っていたら次回作は「日本の話にインスパイアされた犬の映画」(忠犬ハチ公?)を撮るそうで、これまでの所業はむしろ愛がありあまった結果なんだろうなと推察される。
*2:特にドイツは酷い
*3:ブライアン・ヘア『あなたの犬は天才だ』
*4:「愛犬家作法」
*5:冒頭に挙げた記事をひくなら「ほとんど主演を張れるだけの器」
*6:『アーティスト』や『ウォレスとグルミット』など
*7:ちなみについでに脱線するが、スケープゴートの役割は別に犬の寡占物と決まっているわけではない。そもそもの語源が羊なのだし、他の動物が担当することも少なくない。たとえば、白雪姫の物語を翻案した『ブランカニエベス』。虐待されている主人公の少女は鶏を親友とたのむが、いじわるな継母に目をつけられたこの鶏はある晩、丸焼き姿で主人公の食卓に供される。少女はもちろん大きなショックを受け、絶望する。ともすればカートゥーン的ですらある描写だけれど、鶏のイメージに着目した秀抜な起用だと思う。
*8:よく考えたら「スケープゴート」の用法が微妙な気がするのですが、他に適当なアレも思いつかないので今回はさしあたってこれですませとこう。
*9:『キングスマン』も入るかな
*10:『ジョン・ウィック』の場合はほとんど奥さんの敵討ちだけど。
エラリーベイベーは死んだのか
去年のいつだったかエラリー・クイーン『ギリシャ棺』の読書会を担当した。

そのとき資料として参照したフランシス・M・ネヴィンズによる伝記『エラリイ・クイーンの世界』の増補改訂版『Ellery Queen: The Art of Detection』の最後のほうに、「なぜアメリカ人はエラリー・クイーンを読まなくなったのか?」という半分嘆きのような考察が記されていた。『エラリイ・クイーンの世界』の原著はダネイの生前に出されたものなので、おそらく改訂前にはなかった箇所。
戦前戦中にかけて一世を風靡したベストセラー作家クイーンは、没後数年のうちに米国文学界の記憶から抹殺されてしまった。*1その事実にショックを受けた生粋のエラリアン、ネヴィンズさんは風化の原因を探るべく、同じくクイーン愛好家であるジョン・L・ブリーンによる「アメリカでクイーンが忘れられた五つの理由」を引く。
(1)探偵作家の「性分業」
ハードボイルドやノワールがハメットやチャンドラーといった男性作家とイメージ的に強く結び付けられた一方で、クラシックな推理パズル*2がクリスティーやセイヤーズなどといった女性作家のものとみなされるようになった。
こうしたミステリにおける「性分業」の構図が、そのどちらにも属さない黄金期本格の偉大なる巨匠たち、すなわち男性のパズラー作家であるジョン・ディクスン・カーやクイーンらを「文化的な裂け目」へ陥れてしまった。
(2) クイーンの文体
クイーンの散文的な文体*3はこんにちの読者にとって読みづらい。
(3)「コンビ作家」に対する偏見
なぜだかアメリカでは「コンビ作家」の地位が相対的に低い。
(4)60年代におけるゴーストライターによるクイーン名義作品の濫造
執筆担当のリーがスランプに陥った時期に、そのへんの三文ペーパーバック作家に「クイーン」の名義を貸して、探偵エラリー・クイーンの登場しない単発作品を書かせた。
これらの作品は同じくリー以外の作家が執筆を担当した探偵エラリー・クイーン・シリーズの作品とは違い、本家の手がほとんど入っておらず、質的にもかなり落ちる。
しかし事情を知らない読者からすればどちらも「クイーン」なわけで、このことで相当な失望を生んでしまった。
(5) アメリカ人の知性や文化リテラシーへのリスペクトが減退した結果
アメリカ人が頭を使って自分で推理するような知的でゲーム的な小説を好まなくなったため。
要するにアメリカ人がバカになったから。
ネヴィンズさんはこれら五つの理由に「そうだそうだ」と頷きまくってるわけだけど、読んでる方はほんとかよと思ってしまう。あくまで一ファンの肌感覚として挙げられたものなのでエビデンスがあるかといえば、ちょっとあやしい。特に五番目の理由なんかは「なんで俺の好きなものの良さがお前らにはわからないんだ! バカか! バカだからか!」と駄々をこねるオタクのやつあたりに近い。
それでも一番目の「探偵作家の性分業」なんかは、真偽はどうあれ、文化論の切り口として興味深い。ハードボイルド的な行動派の探偵たちがアメリカ男性のマッチョ信仰をくすぐり、かたや、ねちねちと証拠や人間関係を探って思慮をめぐらせる探偵たちを筋肉のたりない女子どものものとみなすようになった。これだけだとなにかにつけ性差を語りたがるおっさんの戯言に見えるけど、『ステロイド合衆国』などのドキュメンタリーでアメリカ男性における筋肉信仰のすさまじさを目撃したあとだと、けっこう説得的に映る。「男は強くあれ」という教義が小説読者の強迫観念に作用して、一ジャンルの文化を形成していったわけだ。
こうした考えを敷衍させていけば、アクション=男性的な技法、モノローグ=女性的な技法というテクニック単位での「性分業」まで行き着くのかもしれない。行き着いたところで、政治的にまったく正しくないんで使えないんですけど。
忘れられた理由はわかったとして、じゃあぼくらのエラリー・ベイベーはもう二度と生き返らないのか。
ネヴィンさんは「生き返る」と断言する。悲しみの弔鐘は鳴り止むのだとアジる。
具体的にどうやって?
そこはまあ、今年邦訳の出る本だし、書くのはやめときたいんだけど、はっきりいって耄碌したノスタル爺さんのうわごとにしか見えない。やっぱりエラリー・クイーンは死につづけるのかもしれない。

- 作者:エラリー・クイーン,越前敏弥,北田絵里子
- 出版社/メーカー:角川書店
- 発売日: 2013/06/21
- メディア:文庫
- この商品を含むブログ (11件) を見る
今週のトップ5:『第三の魔弾』、『世紀の空売り』、『死刑台のエレベーター』、本格ミステリ大賞評論賞部門、『キャロル』、『Empire』
レオ・ペルッツ『第三の魔弾』

- 作者:レオ・ペルッツ,前川道介
- 出版社/メーカー:白水社
- 発売日: 2015/07/08
- メディア:新書
- この商品を含むブログ (3件) を見る
呪いめいた予言の出てくる話が好きだ。たぶんシェイクスピアによって植え付けられた嗜好だと思う。
『第三の魔弾』では、絞首台に立たされたエルナン・コルテス麾下の凄腕狙撃手がその原因を作った主人公グルムバッハに対して呪いを吐く。
「神の呪いを受けるがいい。それ(銃と三発の弾)はお前に苛立ちと惨苦をもたらすだろう。一発目がお前の異教の国王に命中するように、二発目が地獄の女に、そして三発目が――お前――自身に」
このときグルムバッハが本来的に標的にしていたのはアステカをだまし討にし、自分の部下を皆殺しにした残酷な征服者コルテスだ。だが、予言はグルムバッハがコルテスではなく、彼の撃つはずない三人を標的として照準した。そして、物語はそのとおりに動く。予言とはそういうものだから、それはわかりきっている。読者の興味となるのはグルムバッハの意に反する予言が成就するように、「どう」動いていくかで、ここの見せ方が作者の知性と腕にかかっている。そして、レオ・ペルッツがその両方を備えた作者だということは読めばわかる。
部下を次々と失い、満身創痍でコルテス率いる立ち向かうグルムバッハの姿はどこかニュー・シネマ的というか、主人公であるにもかかわらず、亡霊っぽい。そして、軽やかだ。コルテスに監禁された部下を助けるために、大胆不敵にも単身で真正面からコルテスの陣幕に潜入したかと思えば、異母兄弟の公爵にハメられてあっさりと捕まってしまう。コルテスを殺し、脱走するための銃が必要なので自分で魔法陣を書いて悪魔を呼び出し、その悪魔を口八丁でカモってしまう。機知を備え腕っ節も強いが、どこか抜けている。
そんなトリックスターの素質を持つグルムバッハが、忌まわしい予言を境に重苦しい悲劇に巻きこまれていく。爵位を失い、故郷を失い、片目も、部下も何もかもなくしてしまった男、そんな男にたったひとつ残された「自分」すらも呪われた銃弾は撃ちぬく。
Nさんは『第三の銃声』を『マッドマックス2』*1に重ねていたけれども、個人的には同じ『マッドマックス』でも最新作の『怒りのデスロード』のある台詞を思い出した。「ワイブス」の一人がこんなことを言う。
「銃弾は死の種よ。これを植えられたものは死んでしまう」
銃は運命論的な凶器だ。発射されたときから予定された一点に向かい、殺すためだけにまっすぐ飛ぶ。*2
これもそういう話だ。定められた運命の話で、まっすぐ飛来する避けられない憎悪と死の物語だ。
マイケル・ルイス『世紀の空売り』

- 作者:マイケル・ルイス,東江一紀
- 出版社/メーカー:文藝春秋
- 発売日: 2013/03/08
- メディア:文庫
- 購入: 1人 クリック: 30回
- この商品を含むブログ (12件) を見る
マイケル・ルイスのキャラ描写の手法を眺めていると、冨樫義博を思い出す。ある程度まで物語を進めたところで、唐突にそのキャラの過去(だいたい現在の人格形成に影響したエピソード)をナレーション付きの三人称視点で語る。この手法の便利なところは、読者のためにわかりやすく誇張・類型化されたキャラクターに対して独自の深みや人間性を出せるところだ。もちろん、類型的なキャラクターに類型的なエピソードを当てただけでは深みどころか浅薄になってしまうので、想起されるエピソードはオリジナルかつ刺激的かつ端的である必要がある。このハードルをクリアできるフィクション作家はなかなかいない。
そこに来るとノンフィクションや伝記作家は便利なもので、本の題材にできるほど面白い人物はたいがい面白いエピソードに事欠かない。そういうものを取捨選択して、キャラクターのプロフィールに組みこめばいい。
問題はそうやって出来上がったキャラクターが実在の人物と対応関係を持ってしまうことだ。『マネーボール』で主人公ビリー・ビーンの補佐として描かれるポール・デポスタは、人間を人間とみなさないハーバード卒の嫌味なガリガリギーク野郎として描かれたことをあまりおもしろく感じてなかったも聞く。
つまりは作家としてのモラルの問題なんだけれど、残酷な事実として、そういうメソッドで書いてくれたほうがノンフィクションというのは面白く出来上がる。このフィクションとしてのノンフィクションの面白さと、ジャーナリストとしての誠実さのあいだでうまくバランスをとれる人間がいるとしたら、それは自らを「主人公」としてノンフィクション内に持ちこみ平等におもしろなさけなく描写する、ジョン・ロンソンのようなゴンゾ・ジャーナリストと呼ばれる人種くらいなのかもしれない。
映画がたのしみ。
ルイ・マル『死刑台のエレベーター』
映画『死刑台のエレベーター』予告編
「不安げな瞳のアップから始まる映画は名作」という誰が作ったかよくわからない法則があって、『死刑台のエレベーター』もその例に該当する。
凡百の映画ならカフェの軒先でクロワッサンをかじってるモーリス・ロネ*3で幕を引き、ちょっと気の利いた短篇ミステリみたりみたいなオチにしていただろうけど、その先を奇妙な公正さでもって描くというのが食えない。
色々な映画を思い出しますよ。それも最近の映画を。
マイルス・デイヴィスが紡ぐ即興的なBGMはイニャリトゥの『バードマン』おける緊迫感に満ちたジャズドラムに、暗室で「美しい思い出」が浮き出されていく様子はヘインズの『キャロル』にそれぞれ重なるんですね。
本格ミステリ大賞評論賞部門候補発表
昨年、浅木原忍という人が連城三紀彦の全レビュー同人誌『ミステリ読者のための連城三紀彦全作品ガイド増補改訂版』を出して、それが評論賞の候補作にノミネートされたという。過去に同人誌がノミニーにのぼったことがあったかどうかは寡聞にして(だって誰も本ミス大賞の歴史なんて興味ないでしょう?)存じあげないけれど、考えてみれば飯城勇三の『エラリー・クイーン論』だって元はエラリー・クイーン専門同人誌に掲載されていたものの集成だし、去年の受賞作『アガサ・クリスティ全攻略』だって商業出版されるまでは翻訳ミステリシンジケートのブログで連載をすべて読めた。それでも商業ルートを通さない自費出版本が候補作になるのはやはり特別なことのように思われる。
なぜなら、そこにはストーリーがあるからだ。
それまで評論家でもなんでもなかった無名の若き趣味人が、ある日突然連城に魅了されて全作品を読み、全レビューを書き上げ、それが本ミス大賞にノミネートされる。ストーリーとしてはありえないくらいに完璧にドリーミィで、『ロッキー』大好きなアメリカ人ならこの時点でオスカー確実だと思う。
ノミネート作を一冊も読んでない*4人間の無責任さで言ってしまうと、個人的には連城全レビュー本にこそ受賞してほしい。そうなれば、二匹目のドジョウじゃないけれど、「おれもおれも」と続く人間がきっと出てくる。アマチュアによるミステリの評論活動が活性化する呼び水になるかもしれない。
もちろん、最初から受賞ありきで受賞させろと言ってるわけじゃない。*5ただ、夢がないところに人は集まらない。ミステリ評論界というのは、あんまり夢のない開拓地だった。当たり前だ。そもそも大多数の人間からすれば、評論というものがそんなに華々しく魅力的なわけがない。
ところが、今年はちょっとした夢の萌芽が生まれている。結局はミステリ読者のごくごく狭い一部の内輪で終わる夢かもしれない。あるいは三度咲く菖蒲は無理だとしても、いずれ菖蒲か杜若くらいには花開いてほしい。
(RT言及)『ミステリ読者のための連城三紀彦全作品ガイド【増補改訂版】』が本格ミステリ大賞の候補作となったことは、優れた同人誌とその書き手に正当に評価されるべき場が与えられたという意味で、この賞の歴史上画期的なことだと思います。
— 千街晶之 (@sengaiakiyuki) 2016, 2月 14
千街先生は良いこと言うなあ、の図。
トッド・ヘインズ『キャロル』
白状すると開始一時間くらい寝てた。もちろん、映画が退屈だったわけじゃなくて、体調がちょっと芳しくなかったのだった。それでも、原作をあらかじめ読んできたおかげで正気に還ったとき自分がどこの地点にいるのかは即座に了解できたし、わりかし素直に楽しめた。
原作との比較で言うと、と原作を読んでいるといつも原作との比較をやってしまうのでシネフィルの人たちに怒られそうだけど多分ここを読んでいるシネフィルの人などいないので安心して原作との比較を言うと、原作にあった要素やキャラやシーンを結構ざっくり切っていたにもかかわらず、ちゃんと映画的にそこらへんを補完していて、豊潤さにおいてハイスミスにひけをとっておらず、こういう「映画化」もあるのかとちょっと驚かされた。
原作では主人公であるテレーズは老い(=若さを失うこと)を漠然と恐れるふわふわしたサブカルクソ野郎として描かれている。彼女は幼少期を過ごした孤児院*6のシスターへの淡い恋慕(未満の感情)から抜け出しきれず、恋人である画家志望の男性とはあいまいでプラトニックな関係をつづけ、かつてはデザイナーとして活躍しながらも現在は落ちぶれているバイト先の同僚女性に嫌悪に近い感情を抱く。
幼少期のピュアネスを象徴するシスターと老いへの恐怖を象徴する同僚はどちらもテレーズにとってのトラウマであり、「今まで出会った男性の中では一番好きだけど、どうしても愛することができない」恋人は彼女自身の不定形の感情を映す鏡でもある。
このなんとも言い表しがたい不安を描く序盤はサスペンス作家としてのハイスミスの技巧が遺憾なく発揮されている。テレーズが過去の栄光にすがる同僚を冷ややかに内心で批評しながら同時に自分へ直結する絶望に気づいてとても嫌な気持ちになるシーンは読んでて「いつものハイスミスじゃん!」としか思えない。
そこへキャロルが現れて何もかもが鮮明に塗り替えられる。
「キャロルに出会うまでは誰も愛したことがなかった。シスター・アリシアに対する想いさえも愛ではなかった。」*7
そうして、彼女は幼き日の淡い思いを捨て、老いた同僚に対する仏心を持つようになり、恋人を捨てる。視界がはっきりしてくる。そこからはピュアで美しいラブロマンスだ。前半と後半では同じ作者の作品とは思えないほどにトーンが違う。もっとも、意地悪さはどうしてもついてまわるんだけれども。
ところが映画ではシスター・アリシアも老いた同僚もいなくなっている。テレーズのキャラクターを構成する重要な要素をばっさりカットしておいて、どうして原作と同様の機微を描ききれようか。ところが、ヘインズは、それができてしまった。シスターも同僚も抜きで、ぬるま湯的な若さへの逢着と醜い老いへの不安、ひいてはぽんやりしたテレーズの内奥を完全にビルドインできてしまった。
それらはテレーズを演じるルーニー・マーラの繊細な演技と演出、そして巧みな衣装術*8によって達成されている。いかんせん寝ていたせいですべては拾いきれてないんだけれど、まあたぶん週末にはまた観に行きます。
『Empire 成功の代償』
「Empire/エンパイア 成功の代償」Trailer 2016年3月レンタル配信/2016年4月DVDリリース
Huluで配信しているものをシーズン2から観始めた。
「余命宣告を受けたヒップホップ界のスターであり、有名レーベル『エンパイア』の社長でもある主人公のテレンス・ハワードが自らの『帝国』を三人いる子どものうちのどれに継がせるかで悩む、『リア王』ベースの家族ドラマ」という程度の前提知識でいきなり観始めても物凄く面白い。
アメリカでは金があるやつのが強いんだなあ、ということがよくわかる。
ちなみに第一話ではテレンス・ハワードの麻薬売人時代の元締めである大物ギャングが出てくるんだけど、それがクリス・ロックなんで全然強そうに見えない。ご愛嬌。
今月買うべきかもしれない新刊プロスペクツ・10+20冊
今月出る&出た本のうち、個人的な興味の範囲で面白そうなのを何冊か見繕ってみました。
『珍獣の医学』以外はまだ一冊も買ってません。
海外小説
1.ジョン・スラデック『ロデリック』河出書房新社ストレンジフィクション

- 作者:ジョン・スラデック,柳下毅一郎
- 出版社/メーカー:河出書房新社
- 発売日: 2016/02/26
- メディア:単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
だって、ロデリックですよ、ストレンジフィクションですよ。
死んだと思われていたあの<ストレンジフィクション>シリーズが、永遠に出ないと思われていたあの『ロデリック』が、
ついに帰ってくるッッ!!! ついに出るッッ!!!!
この奇跡が河出と柳下毅一郎からの最高のバレンタインプレゼントですね。
2.オルハン・パムク『黒い本』藤原書店

- 作者:オルハン・パムク,鈴木麻矢
- 出版社/メーカー:藤原書店
- 発売日: 2016/02/25
- メディア:単行本
- この商品を含むブログを見る
紹介文的にはパムク・ミーツ・ジョイスみたいな感じらしい。「パムク最重要」とか書かれたらフカシだとしても買うでしょう。
あらすじ:
主人公のガーリップは、イスタンブールの弁護士である。幼なじみであり、伯父の娘であり、友人でもあり恋人でもあったリュヤーを妻とするが、ある冬の日、リュヤーは忽然と行方をくらます。ガーリップは、妻を捜しもとめてイスタンブールの街へ出かける。同じくいとこで新聞の人気コラムニストであるジェラールも姿を消すが、彼のコラムはその後も新聞に掲載され続ける。ガーリップが子どものころから愛読してきたその奇想天外なコラムが、彼の探索を方向付ける同行者となり、イスタンブールの裏通りや、歴史の片隅へと導いてゆく――。

- 作者:ウンベルト・エーコ,橋本勝雄
- 出版社/メーカー:東京創元社
- 発売日: 2016/02/22
- メディア:単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
知の巨人、ウンベルト・エーコ待望の最新刊。ナチスのホロコーストを招いたと言われている、現在では「偽書」とされる『シオン賢者の議定書』。この文書をめぐる、文書偽造家にして稀代の美食家シモーネ・シモニーニの回想録の形をとった本作は、彼以外の登場人物のはほとんどが実在の人物という、19世紀ヨーロッパを舞台に繰り広げられる見事な悪漢小説(ピカレスクロマン)。祖父ゆずりのシモニーニの“ユダヤ人嫌い"が、彼自身の偽書作りの技によって具現化され、世界の歴史をつくりあげてゆく、そのおぞましいほど緊迫感溢れる物語は、現代の差別、レイシズムの発現の構造を映し出す鏡とも言えよう。
またエーコが山風やるのか、といった感じ。シオン議定書がらみのピカレスクロマンなんて絶対面白いに決まってますやん。
4.リュドミラ・ウリツカヤ 『陽気なお葬式』新潮クレスト・ブックス

- 作者:リュドミラ・ウリツカヤ,奈倉有里
- 出版社/メーカー:新潮社
- 発売日: 2016/02/26
- メディア:単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
5.ジョイス・キャロル・オーツ 『邪眼 うまくいかない愛をめぐる4つの中篇』

- 作者:ジョイス・キャロル・オーツ,栩木玲子
- 出版社/メーカー:河出書房新社
- 発売日: 2016/02/26
- メディア:単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
6.ジョン・ヴァーリイ『さようなら、ロビンソン・クルーソー 〈八世界〉 全短編2』創元SF文庫

さようなら、ロビンソン・クルーソー (〈八世界〉全短編2) (創元SF文庫)
- 作者:ジョン・ヴァーリイ,浅倉久志,大野万紀
- 出版社/メーカー:東京創元社
- 発売日: 2016/02/22
- メディア:文庫
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者:殊能将之
- 出版社/メーカー:講談社
- 発売日: 2016/02/11
- メディア:単行本
- この商品を含むブログを見る
異能のミステリ作家殊能将之の未発表短編をみんなの頼れる講談社が絞りとってきてくれたぞ。感謝だ。
8.イーユン・リー『黄金の少年、エメラルドの少女』河出書房新社

- 作者:イーユンリー,Yiyun Li,篠森ゆりこ
- 出版社/メーカー:河出書房新社
- 発売日: 2016/02/08
- メディア:文庫
- この商品を含むブログ (1件) を見る
9.岸本佐知子編訳 『楽しい夜』

- 作者:岸本佐知子
- 出版社/メーカー:講談社
- 発売日: 2016/02/25
- メディア:単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
10.アルフレート・デーブリーン『たんぽぽ殺し』河出書房新社

- 作者:アルフレート・デーブリーン,粂田文,山本浩司
- 出版社/メーカー:河出書房新社
- 発売日: 2016/02/24
- メディア:単行本
- この商品を含むブログを見る
その他ピックアップ
オルハン・パムク『僕の違和感 上・下』早川書房
ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア『あまたの星、宝冠のごとく』ハヤカワSF文庫
スティーヴ・エリクソン『Xのアーチ』集英社
ノンフィクション
1.ナシア・ガミー『一流の狂気 心の病がリーダを強くする』日本評論社

- 作者:ナシア・ガミー,山岸洋,村井俊哉
- 出版社/メーカー:日本評論社
- 発売日: 2016/02/29
- メディア:単行本
- この商品を含むブログを見る
社会が平穏なときには「正常のリーダー」が活躍する。
しかし普通でない大きな危機に対しては、狂気の指導者が必要とされる。
実際に、偉大なリーダーの多くが精神の病を抱えていた。
だからこそ、彼らは非凡な決断と行動で人々を導き、歴史に残る偉業を成し遂げることができたのだ。
できたのだ! と言われても……。
チャーチルの「黒い犬」なんかは昔から有名だけれど、ポジティブな人物評論の切り口としては珍しい。
今月のマスト。
2.スヴェトラーナ・アレシクエーヴィチ『戦争は女の顔をしていない』岩波現代文庫

- 作者:スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ,三浦みどり
- 出版社/メーカー:岩波書店
- 発売日: 2016/02/17
- メディア:文庫
- この商品を含むブログを見る
第二次世界大戦のソ連のいわゆる「大祖国戦争」に従軍した女性たちの証言を聞き取ったもの。
『ボタン穴の戦争』も同時出版。
何? 元々出してた出版社はどうしたのかって?
3.ユーディット・シャランスキー『奇妙な孤島の物語 私が行ったことのない、生涯行くこともないだろう50の島』河出書房新社

奇妙な孤島の物語: 私が行ったことのない、生涯行くこともないだろう50の島
- 作者:ユーディット・シャランスキー,鈴木仁子
- 出版社/メーカー:河出書房新社
- 発売日: 2016/02/29
- メディア:単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
島は天国だ。地獄でもある――古今東西、かくも風変わりなエピソードをもつ島々を史実に基づいて綴り、美しい地図とともに収録。「ドイツのもっとも美しい本」賞受賞。各国で絶賛を博した書。
どこのサイトの紹介をのぞいてもこれしか書いてないので詳細はよくわからないのだけど、おそらくイラストレーション中心の民話集だと思われる。イラストを前面に押し出す本は話自体弱い傾向にある気がするので少し不安をもよおすものの、みてくれは大変よい。定価3000円オーバーだけど。

- 作者:日外アソシエーツ
- 出版社/メーカー:日外アソシエーツ
- 発売日: 2016/02/20
- メディア:単行本
- この商品を含むブログを見る
5.阿部和穂『危険ドラッグ大全』武蔵野大学出版

- 作者:阿部和穂
- 出版社/メーカー:武蔵野大学出版会
- 発売日: 2016/02/25
- メディア:単行本
- この商品を含むブログを見る
6.デイヴィッド・フィンケル『兵士は戦場で何を見たのか』

兵士は戦場で何を見たのか (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ II-7)
- 作者:デイヴィッド・フィンケル,古屋美登里
- 出版社/メーカー:亜紀書房
- 発売日: 2016/02/11
- メディア:単行本
- この商品を含むブログを見る
イラク戦争で心と身体に傷を負った兵士たちを取材する。
7.『人外娘の描き方と発想テクニック 身近な生物から発想しよう』玄光社

- 作者:玄光社企画編集部
- 出版社/メーカー:玄光社
- 発売日: 2016/02/29
- メディア:ムック
- この商品を含むブログを見る
しかし、人外娘用のマニュアルは日本ならでは、ってかんじかしら。
Zトン先生といい、ちょっとしたトレンドなのかね。
8.淺井カヨ『モダンガールのススメ』原書房

- 作者:淺井カヨ
- 出版社/メーカー:原書房
- 発売日: 2016/02/25
- メディア:単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
浪漫ですよ。
9.ルーカ・クリッパほか『アウシュヴィッツの囚人写真家』河出書房新社

- 作者:ルーカ・クリッパ,マウリツィオ・オンニス,関口英子
- 出版社/メーカー:河出書房新社
- 発売日: 2016/02/19
- メディア:単行本
- この商品を含むブログを見る
10.中尾政之『続々・失敗百選 「違和感」を拾えば重大事故は防げる-原発事故と“まさか”の失敗学』森北出版

- 作者:中尾政之
- 出版社/メーカー:森北出版
- 発売日: 2016/02/27
- メディア:単行本
- この商品を含むブログを見る
11.萩野恭子『ロシアの保存食』WAVE出版

- 作者:荻野恭子
- 出版社/メーカー: WAVE出版
- 発売日: 2016/02/10
- メディア:単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
アマゾンレビューによれば、「ロシアの国民的発泡飲料「クワス」の収載は著者の本だけでしょう」でしょうことなので、ご家庭でクワスを楽しみたいロシア料理ファンは見逃せない。
……調べてみたらクワスって「アルコール度数は1‐2.5%」だそうなので、ご家庭で作ったらフツーに酒税法違反では……
12. 『東欧の想像力』松籟社

- 作者:奥彩子,西成彦,沼野充義
- 出版社/メーカー:松籟社
- 発売日: 2016/02/23
- メディア:単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
先月のリストでも見た記憶があるので、延期されてたのかな?
13.アレックス・メス―ディ『文化進化論 ダーウィン進化論は文化を説明できるか』NTT出版

- 作者:アレックス・メスーディ,竹澤正哲,野中香方子
- 出版社/メーカー:エヌティティ出版
- 発売日: 2016/02/08
- メディア:単行本
- この商品を含むブログ (4件) を見る
近年、人間行動の進化に対する関心が高まっている。単に遺伝子の影響からのみ進化を説明するのではなく、人間の「文化」についての学習や継承の影響を科学的な手法で検証する分野が成長してきた。本書はこうした諸潮流を、「進化」を軸にして展望する。
本気かよ、うさんくさいなあ、と思ってしまうのは優生学のトラウマでしょうか。いちおうちゃんとした訳書なのでそういうアレはイジェクトされてるんでしょうが。
HONZに書評がございます
14.ビルギット・アダム『性病の世界史』草思社文庫

- 作者:ビルギットアダム,Birgit Adam,瀬野文教
- 出版社/メーカー:草思社
- 発売日: 2016/02/02
- メディア:文庫
- この商品を含むブログ (1件) を見る

増補 大江戸死体考: 人斬り浅右衛門の時代 (平凡社ライブラリー)
- 作者:氏家幹人
- 出版社/メーカー:平凡社
- 発売日: 2016/02/13
- メディア:単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
江戸時代の処刑人(死刑場で罪人の首を落とす人)山田浅右衛門一族を中心に江戸時代の死体利用事情を解説。
誰に対して売ればいいのかわからないのか、amazonの紹介文に投げやり気味に「刀剣女子必読!」と書いてある。
良い評判をよく聞きます。

- メディア:
- この商品を含むブログを見る
消されないかしら。
17.更科功『宇宙からいかにヒトは生まれたか』新潮選書

- 作者:更科功
- 出版社/メーカー:新潮社
- 発売日: 2016/02/26
- メディア:単行本
- この商品を含むブログを見る
人間を中心とした地球史観を排し、宇宙創成のビッグバンから地球の誕生、そして生命が生まれ進化していく様を、生物と無生物の両方の歴史を織り交ぜながらコンパクトに描いた初めての試み。
だそうで、素人にもやさしい正統派の生物史でしょうか。
18.田向健一『珍獣の医学』扶桑社

- 作者:田向健一
- 出版社/メーカー:扶桑社
- 発売日: 2016/01/31
- メディア:文庫
- この商品を含むブログを見る
もともと人気のある作家なのか、それともどこかで紹介されたのか、発売日まもないのにもう14個もamazonレビューがついている。
田向健一は今月はもう一冊ちくまプリマー新書(ティーン層向けの新書レーベル)から『生き物と向き合う仕事』が出る。獣医の仕事の紹介だろう。
19.ジョナサン・ゴッドシャル『人はなぜ格闘に魅せられるのか 大学教師がリングに上がって考える』青土社

人はなぜ格闘に魅せられるのか――大学教授がリングに上がって考える
- 作者:ジョナサン・ゴットシャル,松田和也
- 出版社/メーカー:青土社
- 発売日: 2016/02/24
- メディア:単行本
- この商品を含むブログを見る
「男の闘い」が人類社会で果たしてきた
意外な役割とは何か?
教室を飛び出して総合格闘技の門を叩いた著者が、
迫真の体験記と膨大な科学的・歴史的知見から
驚きの真実を明らかにする!
それは「教室を飛び出して総合格闘技の門を叩」かないと得られない真実だったのかどうかという疑問は湧くものの、内容は意外と真面目そう。
『暴力の哲学』のビンカ―先生が推薦コメント出してた。
20.ジャイルズ・ミルトン『レーニン対イギリス秘密情報部』原書房

- 作者:ジャイルズ・ミルトン,築地誠子
- 出版社/メーカー:原書房
- 発売日: 2016/02/25
- メディア:単行本
- この商品を含むブログを見る
今週のトップ5:『サウルの息子』、『レモン畑の吸血鬼』、『スティーブ・ジョブス』、『SHERLOCK 呪われた花嫁』、ウンベルト・エーコ、アニメを全部観た人
ネメシュ・ラーズロー『サウルの息子』
絶滅収容所は、親衛隊が中心となって運営されていたが、その末端で働かされたのは、収容されたユダヤ人のなかから選ばれたユダヤ人特別労務班員であった。このユダヤ人特別労務班員(「ゾンダーコマンド」。行動部隊の下部単位の「特別行動隊」と同じドイツ語)は、ユダヤ人のガス殺が円滑に行われるよう巧みに誘導し、ガス殺後の遺体の片づけ処理を迅速に行うことを強制されていた。彼らもまた不必要となれば抹殺された。戦後、生き延びたとしても、ナチ親衛隊側の協力者としての烙印を捺され、隠れるように暮らすことになる。
(中略)
だが、こうした優遇を受けても、人体実験を含む「医療」に従事させられたユダヤ人医師ミクロス・ニスリは、「ユダヤ人特別労務班員が担わされた恐るべき任務は、自らの人格の放棄と想像を絶する絶望感によってはじめて行うことができた」と語っている。
多少の期間、生命を保障されたとはいえ、つねに仲間たちが死に追いやられるのを見るのは耐えられない重圧があった。奇跡的に生き残った後も、自殺に駆られたり廃人になった者も多かった。
はじまるとこれ以上ないくらいに死んだサウルの双眸と、彼のジャケットに大きく描かれた×マークが観客の目にとびこんでくる。そして、それから百二十分のあいだ、ずっとこの二つにつきあわされつづけることになる。死んだ目で見つめ続けられるうちに、観ているほうの心も死んでくる。いい意味で。
アウシュヴィッツ=ビルケナウ絶滅収容所。約一千百万名のヨーロッパ・ユダヤ人の「最終解決」を目指して建設されたこのナチ最大の絶滅収容所で、主人公のサウルはゾンダーコマンドとしての労務に従事している。
各地から送られてきた自分の同胞を、シャワー室と偽って毒ガス室へと導き、閉じこめ、待ち、ガス室を掃除し、回収した金品を選り分け、死体を運び出し、焼き、大量の骨灰をスコップで河へ捨てる。それを三ヶ月か四ヶ月ほど繰り返したのち、自分も殺される。
それは労働だろうか。黒田硫黄の『茄子』に「生きるために働くのであって、働くために生きるのではないだろ」という台詞があるけれど、順序がどうあれ働くことは生きることと結ばれる関係にある。死ぬために働く人間などいない。死ぬために働くのなら、それはもう人間ではない。
だが、1942年には、第二次大戦下の世界にはそういう式がありえた。人間でない人間が多く存在した。それは殺すほうも殺されるほうもおなじだった。ガス室とは、そもそもが虐殺の執行にあたる兵士たちの精神的な不安を軽減するために考案されたものだ。それまでは裸にひん剥いて、埋めるための穴の前に立たせて、ふたりがかりで後頭部と心臓を一発ずつ撃つ。それを何千人分も繰り返す。そんなんで、どうにかならない方がおかしい。
だから、虐殺対象であるユダヤ人たちを「部品」と呼び、人間でないように装った。サウルたちゾンダーコマンドのジャケットに書かれた×印もまた、非人間化処置のひとつだ。パンフレットによるとそれは脱走されたときのために狙う用の的、ということになっているのだが、映像としてこのマークが突きつけてくるメッセージはもっとシンプルかつ直截的。サウルは人間でないのだ。
そのサウルの死んだ目が、にわかに見開き輝く瞬間がいくつか訪れる。「息子」の死体に近づいたときだ。「息子」、とかぎかっこつきなのは、それが本当に息子であるかわからないからで、しかしサウルだけは固くそうだと信じている。無数の屍の山から息子のものと信じる死体を見出したそのとき、それまで予定された死の短い猶予期間でしかなかった生が意味をおびはじめる。この死体を、息子の死体をただしくユダヤ式に埋葬さえできれば、そうすれば――。結局のところ、そうしたところでなにがあるはずわけでもないのだが、サウルは囚人仲間が企てていた蜂起計画など脇目もふらず、ただ「息子を正しく埋葬する」という目的一点に向けてつきすすんでいく。
映画の感想サイトには「サウルは自分勝手なやつだ。自分の仲間の邪魔すらしている」と彼を非難する論調がすくなくない。道理だと思う。途中、どっからどうみてもサウルの自分勝手のせいで計画の重要な一部分が頓挫してしまう。
しかし、サウルは蜂起など、脱走などには興味はない。そこに彼の人間としての生はない。奪われた人間性を取り戻す、与えられた死への労働を生への冒険に塗り替える、そういう古典的なダイナミズムが内包されているからこそ、『サウルの息子』はエンターテイメントとして確実に面白い映画でもある。
劇中、ストーリーレベルで観客に""""圧"""""をかけつつ、初めからずーっとむっつりしてたおっさんが最後にカメラに向かってニコッと微笑むとそれだけでハッピーエンドに見える現象を『セッション』効果と名付けよう。
— nemanoc (@nemanoc) February 17, 2016
カレン・ラッセル『レモン畑の吸血鬼』

- 作者:カレン・ラッセル,松田青子
- 出版社/メーカー:河出書房新社
- 発売日: 2016/01/26
- メディア:単行本
- この商品を含むブログ (3件) を見る
「お国のための糸繰り」でいきなり社会派なテーマを語りだしたな、と思ったら、「帰還兵」では物語をマニピュレートすることの罪悪に焦点をあてた、ちょっとした物語論小説みたいなものも展開される。見どころも文彩も非常に豊かな短編集です。
カレン・ラッセルの『レモン畑の吸血鬼』、ひとつだけ堀骨砕三みたいな設定の話があった。
— nemanoc (@nemanoc) 2016, 2月 21
@nemanoc「お国のための糸繰り」という題名。明治初期に貧しい農家から製糸工場に売られてきた女工の話なんですが、その労働内容がエグい。連れてこられるとまず、変な茶を飲まされる。その茶には不思議な力があって、飲んだ人間は腸内で生糸を製造する蚕人間に変化する。
— nemanoc (@nemanoc) February 21, 2016
@nemanoc蚕人間となった少女たちの体からは高品質な生糸が吹き出してくる。それを工場は搾取していくわけです。で、そんなキチガイじみた生活に耐えきれなくなった少女のひとりが、ある日キレてストライキを始めるんですね。
— nemanoc (@nemanoc) February 21, 2016
@nemanocところが、ハンストで腸内に溜まった糸を吐き出さないもんだから、お腹がパンパンになって衰弱死しちゃう。死んだ少女を見て、工場の人は「うちの糸を盗みやがって」と吐き捨てる。で、彼女の抵抗と死を垣間見ることで自由の価値を知った主人公はある凄まじい決意をする……という話
— nemanoc (@nemanoc) February 21, 2016
@nemanoc設定だけ聞くと悪趣味なゲテモノに思われそうだけど、この蚕人間たちの日々が米国屈指の作家による透明な美しい文体でつづられていきます。なにより恐るべきは富岡製糸場で実際に起こったある事件をベースにしていることで、ちゃんとそのテーマにも訴えている。非常に山風力が高い。
— nemanoc (@nemanoc) February 21, 2016
ダニー・ボイル『スティーブ・ジョブス』
オープンか、クローズドか。
途中の回想シーンで、ジョブズとウォズニアックがアップル社最初の製品である Apple IIの仕様について言い争う有名なエピソードが挿入されている。
根っからのギークであるウォズニアックはオープンシステム、つまり拡張性を高めるために拡張スロットをたくさん用意したほうがいい、その方が売上にも繋がると主張する。だが、ジョブズは独自の美的観点から「二つしかいらない」と言い張ってきかない。
ジョブス曰く「顧客の要望なんて知るか。脚本家が上演の最中に脚本を書き換えるか? ディランは曲を作る前に客の意見を聞くか?」。対してウォズニアックは「コンピュータは芸術品じゃないんだよ……」と呆れる。
ジョブスは結局ウォズニアックをチームから外して初代マッキントッシュを作る。マックは閉ざされたブラックボックスだった。筐体は芸術品として完成されたものであるから、「オタクどもが勝手に中身を開けていじれないように」特殊な工具がないと開けないようにさえした。
で、その箱を自分らでも開けなくなって、右往左往するはめに陥る。『スティーブ・ジョブス』はそういうふうにはじまる。
1984年の初代マッキントッシュ、1989年のNeXT*1、1998年の iMac、この三つのプロダクトの発表会の舞台裏を描いただけあって、全編がほぼ密室劇といってもいい狭苦しさで展開される。
鏡の並ぶ控室で神経質に発表会のリハーサルを繰り返しながら常に何事についてキレまくるジョブス。その部屋に、認知を拒否しつづけた娘を含む、彼の関係者が間断なく尋ねてくる。
密室内でのジョブスは彼の設計思想と同じくクローズドに凝り固まっている。まず他人の意見など聞かず、説得されるということを知らない。一度、自分で思い込んでしまったらそれが間違っているなどまず考えない。*2かつて愛した女性を侮辱し、娘を蔑ろにし、一番の親友だった人物を切り捨てる。彼は低迷期のアップル社を支えた Apple IIのチームに献辞を言ってくれとせがむウォズニアックに度々言う。「これは新製品の発表会なんだ。未来を語らなきゃ。過去の製品の話なんて……」
古くからの知人は過去を思い出させる。娘でさえも例外ではない。娘がいるということは、自分が父親だということだから。自分もかつては息子だったということだから。「実の親から捨てられた」と思い込んでいるジョブスにとって向き合いたくない記憶だ。彼の完全に閉じられた世界には過去など入り込む余地はなく、よって初代マッキントッシュも人気作である Apple IIを含めた旧機種との互換性を排した。彼は未来だけを向こうとした。
だが、友人たちに会う度にフラッシュバックする過去こそがジョブスの幸福な時代だったのではなかったか。
アップル社立ち上げ前夜、ガレージでウォズニアックと Apple IIの仕様について議論を戦わせていた夜。
一度はジョブスの精神的な父親として全幅の信頼を得るも、のちにジョブス追放劇の立役者を演じてしまうジョン・スカリーを、洒落た地中海レストランに招きアップル社の社長就任を要請した夜。
そのどちらとも「開かれた」場所での出来事だった。そこにこそ未来があった。
ラストシーン手前で、ジョブスは建物の最上階へ、抜けるような蒼天の屋上へと登り、彼にとっての未来を手に入れる。彼は(おそるべきことに)初めてそこで、ユーザーのための製品開発を誓う。まあもちろんジョブスはジョブスなので、「そんな製品ダサいから、おれがもっといいもん作ってやるよ」というアレな審美性が入るのだけれど、それでも彼にとってはたいした進歩だ。ジョブス時代のアップル社が真にユーザーに支持される、偉大なアイディアを生み出し始めたのはまさにこのときだったのだ、と指摘してこの映画は終わる。
そういうわけで、マックユーザーは現在もクソありがたいことに大衆の都合などまるで考えないサドッ気溢れるクソプロダクツを享受できているのでした。めでたしめでたし。
ウルトラサイコパライノアクズ野郎としてのジョブス
高橋: 小津の映画の登場人物って、物語的にはごく当たり前のホームドラマの人たちのようなのに、モラルが完全に崩壊している、得体の知れない生物のように見えるんですよ。塩田さんが〈底〉という言葉を通して言っていることにも通じていると思う。「モラルの完全な崩壊」というのは、フッテージで出て来た『ハンナ・アーレント』(2012)で、アイヒマンやそれに追随したユダヤ人指導者に向けて言われる言葉ですけど、そこに編集で『マブゼ博士の遺言』(1932)の「犯罪の支配」のつぶやきを重ねたのは、ハンナ・アーレントの言葉を茶化したいからじゃなくて、モラルの完全な崩壊こそ、実は映画の本質を突いているんだと思ったからですね。
loc.789, 『映画の生体解剖×映画術 何かがそこに降りてくる』
「モラルの完全な崩壊」
そう、僕たち私たちは底の抜けた道徳倫理が見たくて映画を観ている。人間がどこまで非人間的になれるかということが観たくて映画を観ている。
『セッション』が好きだ。『最後まで行く』が好きだ。『ナイト・クローラー』が大好きだ。
ジョブスはクズさという観点において突出している。ナイト・クローラーさんやフレッチャー教授など所詮フィクションの産物で、実在にしても例えば『ウルフ・オブ・ウォールストリート』のジョーダン・ベルフォードなど単なる雑魚にすぎなかったのだと『スティーブ・ジョブス』のジョブスさんは教えてくれる。この怪物はほんとうにいて、しかも未だに理想の経営者、時代の革新者と讃えられているのだ。
映画『スティーブ・ジョブス』と同じ伝記をベースにしているヤマザキマリの漫画『スティーブ・ジョブス』には基本的にジョブス先輩のパない悪逆非道しか描かれていない。
技術面を丸々になっているウォズニアックを搾取し、さらには嫉妬から使い捨てるに至るまでは序の口として、ゼロックスに押しかけて初代マッキントッシュのたたき台となるデータを半ば強奪に近いかたちで盗む。捨てたはずの娘の名前をつけたプロジェクト(Lisa)を立ち上げて「こいつにも人の心があったんやなあ」とほんわかさせといて、人間関係のこじれ(主にジョブスの嫉妬)から初代マッキントッシュの開発に移籍するや娘の名前をつけたプロジェクトを全力で邪魔しにかかる。日夜粉骨砕身で開発に勤しむ社員の前にふらっと現れては「くだらねえことやってんな」と一言罵声をあびつけて去っていく。アップル社設立の功臣で、大学時代からの友達であるダニエル・コトケ*3に株式を一株もやらない。エトセトラエトセトラ。*4
それでも経営者として才覚があったんだからいいんだろう……と思っていたら、むしろ若い頃の(劇中での)ジョブスは致命的なまでに経営者としてのセンスに欠けていた。技術者でもデザイナーでもないくせにやたら「芸術的」な細部に拘っては無駄にコストを上げていき、それが販売価格に跳ね返って初代マックの失敗を招く。*5にマックだけならまだしも、前述の Lisa や Aplle II といった自分の関わっていないプロジェクトを dis りまくって足をひっぱる。解雇されるのも当然の仕儀である。
映画版でもそうしたジョブスの人柄はあますところなく描かれている。特に自分を一度裏切った(ジョブス視点)人間は何が何でも許さない。というか、それはお前が許す話じゃなくて、相手が許すかどうかって話だろう、みたいなことでも自分が許す立場だと思い込んでいる。すごい。一度、敵となったら唯一の武器といってもいい鋭い舌鋒で相手を社会的に抹消しようとする。ヤバい。
映画のジョブスさんは一度会ったら二度と会いたくない人物なのだが、それでもなぜかウォズニアックが友人として何度も発表会に来たり、アップルをやめてもついてくる人間がいたり、幼い娘に求められたりしている。この不可思議さが、ジョブスのカリスマを納得させてくれる。確信させてくれる。こいつは幸せになる資格などないが、何かを手に入れられる才覚はあるのだ。そして、それは、積み上げてきたすべての悪行を振りきって、映画にハッピーエンドをもたらせるだけの何かだ。モラルの完全なる崩壊。
『SHERLOCK 呪われた花嫁』
そもそもからしてドラマ版のシャーロックがそこまで好きかと言われれば、そこまででもないんですけれども、なんだか見てしまう。飽きない。面白い。
観客が「こ、こんなアホな犯人が今時いてたまるかぁーッッ!」とキレかけた最高のタイミングで最高のキャラが「こんなアホな犯人いるわけねえー!」とセルフツッコミ入れてくるので作ってる人はホント視聴者心理の扱いに長けている。
— nemanoc (@nemanoc) February 21, 2016
ネタバレに類さないと思うので言ってしまいますが、ラストシーンは『幕末太陽傳』の実現しなかった幻の某バージョンみたく「19世紀のロンドンと21世紀のロンドンはつながっているんだよー」という感じのオチなんですね。
ただなんもなしにそれをやったら「なんのこっちゃ」と白けちゃいますけれど、『呪われた花嫁』ではくどいまでにちゃんと現在と過去を対比させまくるから、ラストが「時代を超えて愛されるシャーロック・ホームズは永遠の名作であり偉大なるキャラクターなのだ!」というある種のテーゼめいたものを発して立ち上がってくる。
くどすぎなのがたまに傷。
ウンベルト・エーコ死す。
絶滅してしまったのか……。[不謹慎]*6
よく考えたら、小説よりそれ以外の本(論文の書き方とか読書本とかもうすぐ絶滅するなんとかについての本とか)のほうが読んでる数多い気がする。
10年くらい前、たまたま手にとった TIME にエーコのインタビュー*7が掲載されていた。
そのなかに「ユーモアってなんで必要だと思いますか?」(うろおぼえ)という質問があり、エーコは「つらい現実に対抗しうる唯一の武器だから」(うろおぼえ。なんかもっと明確に鋭く良い感じのこと言ってた気もする)と答えていた。知らん人だけどいいこと言うなあ、と思いましたよ。
『オデッセイ』を観てて丁度そのセリフを思い出したところだった。

- 作者:ウンベルト・エーコ,和田忠彦
- 出版社/メーカー:岩波書店
- 発売日: 2013/02/16
- メディア:文庫
- クリック: 5回
- この商品を含むブログ (15件) を見る
アニメを全部観た人
foxnumber6.hatenablog.com
「量や数を誇るのは未熟な証拠」だとか「どのくらい観たかよりも何を読み取ったかが大事」だとかいう使い古された金言など、実際にすべてを覧じた人間の前にはカスにも等しい。それを思い知らされた。
今週のトップ5:『ヘイトフル・エイト』、『キャロル』、『劇場版探偵オペラミルキィホームズ』、『サタデー・ナイト・ライブ/アダム・ドライバー回』、『スティーブ・ジョブズ』、ベルリン国際映画祭
クエンティン・タランティーノ監督『ヘイトフル・エイト』
南北戦争の傷もまだ癒えきらない時代のワイオミングで、
雪中の小屋に閉じこめられた個性豊かな八人の面々が織りなす丁々発止の会話劇。
タランティーノということで色々言われたりもするんだろうし、それでこそのタランティーノ映画なのだと思うけれど、見ててフツーに面白かった。
三時間近い長尺で、しかも舞台が狭い小屋の中にほぼ固定されているにもかかわらず、終始、観客を飽きさせない。この一点だけでも物凄い。
特に中盤から終盤にかけては「いつ発砲する/されるのかわからない」というサスペンスの緊張感がほどよく使用されていて、ミステリというよりは端正なホラーのよう。
キャストもそれぞれにいい味を出していて、特にウォルトン・ゴギンズ演じる南部軍の愚連隊の生き残りがおいしい。
最初はタフでバリバリレイシストな南部ガイを演じてたのに、段々とヘタレで日和り見的な本性が露見し、「その場面における強者」に付和雷同するようになっちゃう。はては犬猿の仲だったはずの黒人北軍兵(サミュエル・L・ジャクソン)にまで尻尾をふって、最初に言ってた南部連合の誇りはどこへいったのか(しかもこの時点のジャクソンは南部軍人に対して割と最悪な行為をしていたと明らかになっているのに、ゴギンズはまるでどこ吹く風)。
そんな彼が一箇所だけ、意地というか媚びない態度を見せるシーンがある。なぜそういう選択をしたのか、その理由がいい。合理性でも情でも愛でもなく、「おまえは俺を殺そうとした」という憎しみから。
前二作の『ジャンゴ』と『イングロリアス・バスターズ』にあったわかりやすいテーマや正義はここにはない。個人の欲望と嘘と憎しみと疑念と相互不信と不可解な信念と関係性だけで時間が駆動している。日本だとそのまま百年は続きそうな桎梏だけれど、さいわいそこは十九世紀のアメリカなので、銃弾がめんどくさい何もかもを爽快にぶち壊してくれる。それがいいことかわるいことは知らないけれど、とりあえず観ているぶんには面白い。
トッド・ヘインズ監督『キャロル』
二回目。一回目は寝ていた部分も今回はチェックできた。
劇中で「観ること」「視線」「目」がやたらにフィーチャーされているのはよく言われているところではあるけれど、それ以外の要素として「目覚め」も挙げておきたい。
テレーズはよく寝る。寝て、起きる描写がやたら入る。冒頭のキャロルとの別れから、ストーリーの起点部分(キャロルとテレーズの出会い)へと戻っていくところでも、テレーズの起床シーンから語りが再開される。つまり、映画のストーリーを時系列順に並べると一番最初に来るのはテレーズの目覚めの場面ということになる。
そうしてテレーズが目覚める度に何事かが展開していく。
キャロルとの愉しい旅行でも、ある日目覚めると同じベッドにいたはずのキャロルがいなくなって、代わりにキャロルの古馴染みがソファに座っている。
その古馴染みにNYへ送り戻してもらう車中でも、テレーズは不意に寝て、また起き、そして吐く。
NYに帰ると、彼女は以前の迷える乙女ではなくなっている。
森脇真琴総監督『劇場版 探偵オペラミルキィホームズ〜逆襲のミルキィホームズ〜』
劇場版探偵オペラ ミルキィホームズ〜逆襲のミルキィホームズ〜
ミルキィホームズはそもそもミステリファンなど眼中になかった。どこかのインタビューで制作陣が「ミステリファンではなかった」と答えていたように憶えているけれど、なるほど、一部取り入れられていたミステリパロディもどこかカタかった。ミルキィホームズの四人の名前はそれぞれ古今の名探偵から採られているのだけれど、そのチョイスが: シャーロック・ホームズ、ポアロ、ネロ・ウルフ、コーデリア・グレイ。ネロ・ウルフまでならまだしも、コーデリアは明らかに時代的にも格的にも浮いている。ミルキィホームズの一期はスラップスティックなパロディに満ちていたけれど、そこで真剣に「ミステリ」をやるつもりはあまりなかったはずだった。
ところがなぜかミステリファンにウケた。深夜の萌えキャラアニメで「探偵」をフューチャーした作品がよほど珍しかったのだろうか。とにかく、ミステリファンにとってとっつきやすかったのは確かだ。翌年にはハヤカワの『ミステリマガジン』で特集が組まれ、芦辺拓の短篇にもミルホが「出演」したのだった。
それに伴ってかは知らないが、二期以降、制作陣のミステリ意識は向上していく。その傾向がよく現れているのが各話タイトルの変遷だ。ミルホでは各話タイトルが有名ミステリ作のパロになっていて、第一期ではルパンやホームズや乱歩といった古典中の古典しかピックアップされていなかったものの、二期からはエルロイやキャロル・オコンネルといった時代やジャンルに幅が出てきて*1、四期では『インシテミル』と言った最近の国内の話題作から『九マイルは遠すぎる』や『深夜プラス1』といった国外のオールタイム・ベスト、はては都筑道夫の『黄色い部屋はいかに改装されたか?』といった評論本まで組み込む域にまで到達した。
本編でも「探偵」と「怪盗」という予め用意された設定(偵都ヨコハマで争い合う二つの陣営的なナニ)を意識的に自問するようになり、二期では「探偵」と「怪盗」の関係性についてよりシリアスに深く意識されたストーリーが語られるようになった。
ところがでこれでファンが喜んだかといえば、むしろどんどん盛り下がっていったように思う。
交代した監督の資質とかまあ一概に理由を特定できはしないんだけれど、とにかく、制作陣のミステリ理解がレベルアップしていくのに反比例して、観測範囲内でミルホについて語るミステリファンは減少していった。まああくまで観測範囲内での話なので、あるいはどこでは大盛り上がりだったのかもしれないが、そういうふうに見えた。
しかも真剣に「探偵」や「怪盗」について語るようになったからといって、それが傾聴に値するほど新規性や迫力に富んだものだったかどうか。探偵がいるから怪盗がいて、怪盗がいるから探偵がいるんだよね、というだけはよくある俗流陰陽理論みたいでテンションさがるのもむべなるかな。
結局ミルキィホームズとはなんだったのか。
一期は面白かった。それは間違いなく感触として残っている。視神経がそう記憶している。夏休みスペシャルには未来のにおいがあって、それでミルホは「何か」なのだと確信した。新しい何かであるはずだった。二期ははじめの方は良かったんだけど、スラップスティックコメディをとりがえる様子が見えてきてラストはよくついていけなかった。主人公が交代した三期は二三話観ただけで視聴を取りやめた。ふたたびミルキィホームズがカムバックした四期はそれなりに楽しく観たおぼえがあるけれど、内容はほとんど覚えていない。
気が付くと第一期から五年が経っていた。
未来だったはずのミルキィホームズは十二話で一枠一クールを大過なく埋めるだけの平凡な深夜アニメに成り果てていた。一話ごとにそこそこ視聴者を楽しませ、二十数分後には一切の記憶から消え去る。そのサイクルを十二回繰り返すだけの作品。初期のころの狂躁めいた情熱はすっかりと冷えきり、なかば義務感で定時にチャンネルを合わせる。動画を眺める。ストーリーも何も頭に入ってこない。それはアニメなのかもしれない。しかし未来ではない。何かではない。
あるいはミステリとおなじなのかもしれない。消費のプロセスが。初撃に未知の驚きがあり、魅了され、継続的に摂取していくうち刺激が失われて、それでも初恋の味が忘れられず惰性で読みつづける。自己を鍛錬し、レベルアップできるタイプの読者はそれでも自分なりに未知の驚きを発見ないし発明しつづけていけるのかもしれないが、不幸なことに、自分はそのタイプではない。
そうして、やがて悟る。もうミルキィホームズという土壌には何も残されてはいないのだと。
だから今回の劇場版がアナウンスされたときも何も期待しないことにした。
公開されれば喜ばしいし、観に行く。しかし期待はしない。今までの五年間でミルホに「その先」などないと知っていた。
森脇監督が総監督して戻ってくるということで、せめて一期の破天荒なギャグが多少なりでも戻ってくればよいと思っていた。
劇場版ミルホは二月二十七日に公開された。
もぎりの兄ちゃんに導かれるがままに三番スクリーンに入ると、絶望的に少ないというほどではないが、同じ劇場で上映中のガルパンやキンプリや『同級生』なんかに比べると客の入りも熱量もなんだかそこそこといった感じ。
本編がはじまると、どことなくぎこちなかった場内の雰囲気がすぐに和らいだ。序盤から矢継ぎ早に繰り出されるギャグに場内から絶え間ない笑いが巻き起こる。この時点でおおかたの期待はクリアしていたかもしれない。第一期みたいな放送禁止ギリギリのパロディネタはさすがに避けられていたが、それでも映画館で可能な範囲内で最大限笑いを獲りに行っていた。四期に出てきた変な妖精キャラも、三期の主役だったよくわからない二人組もオミットされていて、「私たちの観たいミルキィホームズ」が帰ってきた印象だった。
もっとも、ストーリーのほうは酒のつまみ程度にしか見なしていなかった。三度目か四度目となるトイズの喪失。映画限定であろう新たなる敵ボス。ライバルである怪盗帝国とのからみ。筋から道具立てまでこれまで何度も見てきたようなものばかりで、そういうところから察するに、まあ最後にはそこそこのところに落ち着くんだろう。敵ボスをやっつけ、トイズを取り戻し、怪盗帝国とはこれからもルパン三世と銭形のとっつぁんみたいなゆるいライバル関係を継続していく。そういうオチ以外には考えられないし、事実そのように展開も収斂していく。ツイストもなにもない、平和な深夜アニメのロジック。
そうして、佳境にさしかかる。ミルキィホームズのリーダー、シャーロックはライバル怪盗帝国のリーダーであるアンリエットからこう問われる。今回の相手は時間を巻き戻すという強大な力を持っている。かたやミルキィホームズは超能力であるトイズも失って、勝てる見込みがまったくない。どうするのか。
シャロの答えは単純だ。「何度負けても立ち上がればいいんです」。
これまでも、何度もそう主張してきた。倒されてもそのたびに立ち上がり、前に進めばいい。しかし、今回の敵は根性だけで勝つにはあまりに至難の相手だ。世の中には精神論だけではどうにもならないことはある。アンリエットは無言で立ち去りかける。
その背中に、シャロはこんな言葉をぶつける。「七転八倒の精神ですよ」。祖父であるシャーロック・ホームズから習ったということわざだ。
アンリエットは呆れたように訂正する。「それをいうなら、七転び八起き、でしょう」
「いいえ、七転八倒でいいんです」
シャロは、にこやかにそう断言する。
そのときに観客は悟る。
七転八倒、それこそがミルキィホームズというシリーズ探偵のオリジナルさであり、また、ミルキィホームズというアニメそのものだったのではないのかと。
ミルキィホームズはシリーズ探偵だ。コナンやホームズや金田一耕助といった面々とおなじく、小出しに出来される事件を対症的に解決していく。シリーズ探偵がなぜシリーズ化していくかといえば、それは人気があるからで、商業的な要請としてシリーズ探偵は探偵でいることをやめられず、作品世界はその探偵に活躍の場を供給するために事件を無限に発生させる。よくネタにされる名探偵コナン世界のいびつさに象徴されるように、それは終わりのない地獄めいたゲームだ。事件を何度解決してもすぐに次の事件が起こる。シリーズ探偵とは七回転んだ時点で八回目も転ぶことが予定されている悲惨な存在なのだ。
その悲惨さに、これまでどれだけの探偵が真摯に向き合ってこれただろう。彼らに許されるのはせいぜい「行く先々で事件が起こるもんだから、他人から死神あつかいされるてるよ」といったメタ的な自嘲くらいだ。探偵個人の成長や変化ならいくらでもあるだろうけれど、自らがシリーズ探偵であることについての呪いについては揃って顔をそむけている。
その呪いをミルキィホームズは朗らかに肯定してみせた。
八回目の転倒があらかじめ組みこまれている世界でも、前に進んでみせると言ってのけた。だから、過去に戻って歴史を改竄しようとしている後ろ向きな敵ボスになど負けないのだと。
ミルキイホームズはそもそもが探偵にとって大事な超能力であるトイズを失うところから始まったアニメだった。一期の終わりで彼女らはトイズを取り戻し、そしてまた失う。そして、二期はまたトイズを失った地点から再出発する。ミルキイホームズの面々は基本的にあまり成長をみせない。それは、彼女らの努力が報われない世界設計に対する韜晦でもあるのだろう。
そのせいかしらないが、ミルキイホームズはトイズを失ったことを嘆いても、それを取り返す実質的な努力をあまり行わない。ただ刹那的に日々を生き、事件を場当たり的に解決したりしなかったりする。彼女たちは気づいていなかったかもしれないが、それはおそらくトイズを取り戻すのに一番正しいありかたなのだとおもう。探偵たちに対してサディスティックなその世界にあっては、一日一日を生き抜き前進することが何より探偵的な営為なのだ。だからシャロは転ぶことを恐れない。
そういうことを理解したときに、はじめてミルキイホームズが「名探偵」に映った。名探偵とはなんだろう。難事件を解決すれば、名探偵なのか。名推理を披露すれば名探偵なのか。違う。名探偵とは探偵として固有のアティテュードを有したもののことだ。
それまではミルキイホームズにアティテュードなどないと思っていた。いくら自分らで「私たちは探偵です!」と自己規定を繰返したところで、実質の伴わないむなしい叫びにしか聞こえなかった。事件を放置し、推理を放棄し、探偵であることを放擲した動物たちにしか見えなかった。その見方はある意味で正しく、ある意味で間違っていたのだろう。ミルキイホームズとは、「名探偵になる」物語だったのだ。
おそらく最初からそうやろうとして作られた話ではない。パンフのインタビューを読む限り、現在ですら意識されていない。
ところが、ミルキイホームズは五年四シーズンかけて、名探偵にふさわしいだけのオリジナルなアティテュードを独力でさぐりだした。テレビシリーズ数十話とTVスペシャルは、劇場版でシャロが「七転八倒」の世界を肯定するあの瞬間のためにあった。
ミルキィホームズはたしかに観るに値したアニメだった、と今なら疑わない。
『サタデー・ナイト・ライブ/アダム・ドライバー回』

ドライバーがカイロ・レンを演じた『スター・ウォーズ フォースの覚醒』のパロディスケッチがいっとう面白い。
アメリカに『Undercover Boss』というリアリティ番組があって、普段偉そうにして社員をこき使ってる大企業のCEOとかそのへんの重役たちを下っ端新入社員として身分を詐称させて現場へもぐりこませ、最底辺の社員やバイトたちと交流をさせるといった内容なのだけれど、それをSNLでは『スターウォーズ』のカイロ・レンにやらせている。
そこで描かれてる彼がネットで「中二病」だとか「エモ」だとか小バカにされているカイロ・レン像まんま(社員食堂で飯食ってる最中に「同僚」たちに「カイロ・レンさんって脱いだらムキムキマッチョで腹筋が6つに割れてるらしいよ!」と無駄にアピールしたがったり)で、作ったスタッフは心得ているなあ、と思います。
そういえば、マーティン・フリーマンがホストを務めたときの『The Office』×『ロード・オブ・ザ・リング』のマッシュアップもふるっていた。こういうネタはハズレないのかも。
『第66回ベルリン国際映画祭』
受賞作はジャンフランコ・ロッシ(ロージとも)監督の『Fire at Sea』。
ロッシは2013年のベネチアでも『ローマ環状線』で金獅子賞を獲っているから、これで二冠を掌中に。ベネチアとベルリンで二冠といえば、チャン・イーモウ、アントニオーニ、ジョン・カサヴェテス、ゴダール、ロバート・アルトマン、アン・リー、ジャハル・パナヒ(昨年の受賞者)、といった錚々たる面子が並んでいるわけで、ここにドキュメンタリー監督であるロッシが加わることになる。
filmneweurope.comが映画祭ごとに毎回出している採点まとめ表を見ると『Fire at Sea』は唯一の平均四点代(五点満点)を叩き出していて、前評判通りの受賞ということになる。2014年には四点台を叩きだした二作品(『六歳の僕がオトナになるまで』と『グランド・ブダペスト・ホテル』)をさしおいて三点ジャストの低評価だったディアオ・イーナンの『薄氷の殺人』が金熊賞というフロックはあったものの、2015年はコンペ作中平均最高点(3.6)だった『Taxi』が順当に獲っているので、基本的には評論家の評価と受賞作が一致する傾向にあるのかもしれない。
ちなみに今年のコンペ全十八作品の平均点は約三点(2.9967)。それで基準にするなら、個人的に楽しみにしているトマス・ヴィンターベアの新作(3.33)やミア・ハンセン=ラブの新作(3.60/最優秀監督賞)はまずまずに収まった印象か。逆に『Mud』のジェフ・ニコルズの『ミッドナイト・スペシャルは2.47、題材で興味をひかれる『ジーニアス』は2.60と北米・英国勢は総じてやや辛め。唯一、A・ギブニーのドキュメンタリーが安定の風格。
ウォルター・アイザックソン『スティーブ・ジョブズ』

- 作者:ウォルター・アイザクソン,井口耕二
- 出版社/メーカー:講談社
- 発売日: 2011/11/05
- メディア:単行本
- 購入: 3人 クリック: 14回
- この商品を含むブログ (9件) を見る
町山智浩がラジオで「ジョブズという人は若いころは反権力の革命家だったのに、アップルでビッグになると自分が独裁者になった」と言っていたけれど、ある意味でジョブズという人は一環していて、そもそも Apple I を作っていたころから「ユーザーはなにもわかっていない! だからあいつらには何もいじらせない! おれがデザインしたものだけを使わせる!」と主張するコントロール欲求の強い人で、それが無名だったころには単に狂人の戯れ言だったってだけのこと。姿勢としてはずっと「独裁者」だった。
いまのところ得られた知見は「人類は、役に立つキチガイと役に立たないキチガイを見分ける技術を一刻もはやく手に入れなければならない」と「周囲が上手に扱うとよく働くキチガイもいる」というところか。
*1:特にオコンネルは前年度のミステリランキングで上位になった新刊『愛おしい骨』を使用
フィクションにおける切腹の偽史のためのメモ
木下昌輝の幕末怪奇連作短編集『人魚ノ肉』を読んだ。読書会の課題本です。
そういうわけで近頃、切腹についてよく考える。
『人魚ノ肉』には切腹メインの話が二編、収録されている。
片方は唐突な切腹死を遂げた山南敬助の謎を沖田総司が探偵役として(?)追う話。もうひとつは横領の疑いで切腹に追い込まれた新選組勘定方の河合耆三郎、その彼の相棒役だった男の話。どちらも新選組の話としてはポピュラーな題材で、そこに作品全体を貫くガジェットである「食べたら不老不死になれる人魚の肉」がからまってくる。しかしまあ、ここでは人魚の肉などさておく。切腹の話です。
そもそもなぜ武士は腹を切るのか。
史実において切腹の持つ意味合いは、時代によってゆるやかに変遷している。
切腹が認知されだしたのは、武士の権力基盤が確固たるものとなった鎌倉初期だ。源義経の最期に見られるように、最初は戦場で進退極まった武士の自害手段の一種に過ぎなかった。*1罪を犯したり、戦に負けたりした武士には斬首をもって罰するのが適当とみなされていた。
その後、戦国時代には、切腹は敵味方に認められた「立派な武士」の「自主的な誇りある死」として(武士社会内での)特権的な性格が賦与されるようになった。*2要するに、武士の死に様として斬首よりワングレード上に据えられたのだ。
江戸幕府が成立し、二代将軍家忠の治世に入ると、切腹は武士の基本的な刑死手段に定められる。斬首、磔刑を基本とする町人や農民らとは異なり、他人の手を借りず自分で立派に死ねる武士の優越性を強調したわけだ。
一方で引責と結びつけられるようになった切腹は、トラブルにおける安易な綴蓋として乱用されるようになる。喧嘩両成敗はもとより、恥をかかされたというので腹を切る、公金横領がバレたので腹を切る、不祥事の責任を押しつけられて腹を切る、とりあえず上司に腹を切れと言われたから腹を切る。本来なら死に値しないような事由でも、藩や上役に類を及ぼすようなケースであればぐっと飲みこんで腹を切る。そういうことをできるのが、まことのサムライである、ということになった。刑死としての切腹とは別に殉死というものもあるが、あれもまあ見栄の張り合いの一種です。
それはそれとして、ではフィクションにおける切腹の機能とはなんなのか。
効用は千差万別なのだけれど、ひとつはまあ、人が死ぬ以上は謎がついてまわる。謎があればミステリーになる。
『人魚ノ肉』でも切腹はミステリーとして扱われる。特に沖田総司が主役の「肉ノ人」。なぜ山南敬助は切腹においこまれたのか。それは山南が隊から脱走しようとしたためだが、そもそもなぜ脱走しなければならなかったのか。その謎が沖田の前につきつけられる。
おそらく本邦における切腹ミステリー、切腹ホワイダニットの嚆矢は森鴎外が大正元年に発表した「興津彌五右衛門の遺書」だろう。鴎外の歴史ものの第一号だ。
亡き細川忠興*3の墓前で「明日年来の宿望相達し」「首尾よく切腹いたし候事」を報告する衝撃的な書き出しからはじまる。
一体なぜこの遺書の主ーータイトルから察するに興津弥五右衛門ーーは殿様の墓前で切腹などするのか。勘のいい読者ならちょっと考えれば殉死だと察せるだろうけれども、その所以はどういうわけか。単に御主君が死んだので自分も追腹を切ることにしました、というだけではドラマにならない。なにか特別な「御恩」があるはずだ。
そういう興味から森鴎外は一流の筆致で読者の興味をひっぱっていく。一行目で、私は死ぬことにしました、という宣言をしておいて、二行目からは主人公の祖父の来歴から話しだす迂遠っぷり。核心となる事件のあらましは全体の三分の一を超えたあたりでようやく語られ始める*4。
鴎外は意識的にサスペンスの話法を使ったわけではないだろう。しかもミステリーといっても、あくまで興津の死が謎なのは読者にとってだけであって、物語内のレベルでは謎でもなんでもない。
鴎外はその後、「興津」から殉死テーマを掘り下げて「阿部一族」、ドキュメンタリックな手法をつきつきめて(これも切腹譚である)「堺事件」などをものにしていく。
物語内の人物たちが切腹の裏に隠された謎を巡って、トリッキーにかけずりまわる本格的な切腹エンターテイメント小説は、昭和十三年の吉川英治『夏虫行灯』*5を待たねばならない。待たなくても、その間に岡本綺堂*6の半七シリーズもあったことだし、探せば何か本格切腹ミステリが出てくるかもしれない。
切腹文学のはじまり
では他の切腹ミステリ以外の切腹フィクションではどうなっていたか。
鴎外は大正二年に「阿部一族」を発表する。「阿部一族」はたぶん日本人の九割が読んでいる作品なので、好き嫌いはどうあれ、いまさら説明はいらないと思う。読んでいない人は残りの一割であることを心底恥じながらこれからの生を生きてほしい。
おそらく「阿部一族」を含めこのころの一連の鴎外の切腹小説群(鴎外いわく「阿部一族」は「殉死小説」だったらしい)で日本の文芸における切腹のイメージをある一定の地平へ固着させたのではないか。
翻訳家の須賀敦子はエッセイ集『遠い朝の本たち』で、「阿部一族」をこんなふうに読解している。
日本の過去に置くようになったのは、彼が日本の現状に愛想をつかしたからだという論旨をよく目にするが、読んでいて、『阿部一族』の底流にある、西洋臭さのようなものに私はふと気づいたのである。『阿部一族』は殉死―切腹という武士たちの慣習が、西洋人をふくむ部外者が考えるように、ただ野蛮な風習なのではなくて、確固とした哲学や美学に支えられていたという一面を明らかにしている。しかし、最後にこの一族が苛酷な滅亡に追いつめられていく過程を、共同体の論理に従わざるを得なかった社会への批判と読むことは可能だけれど、それと同時に、ギリシア悲劇的な運命の桎梏としても読めるのではないかという考えが浮かんだとき、鷗外の晩年の作品への解読の扉がすこし開けたように思えた。人間の不条理ということが、ここでひとつの中心的な命題として克明にたどられていることは確実で、その捉え方は日本/東洋的というよりはより西洋的と思える。
またプロレタリア作家の宮本百合子(「鴎外・芥川・菊池の歴史小説)にいわく、
作者はこの事件をめぐる総ての人々の心理を、その時代のそのものとして肯定して描き出している。阿部一族の悲劇は悲劇として深い同情をもって映されていて、そこに作者の人間性においての抗議や批判は表現されていないのである。これは特に私たちの注意をひく点ではなかろうか。鴎外が、この時代の悲劇はその時代のものとして、人々の感情行動の必然のモメントをもその範囲において描いたということは、鴎外が歴史というものを扱った態度の正当な一面であったと思う。誤った近代化や機械的な現代化はちっとも行われていない。
須賀の「西洋的」と、宮本の「その時代のものとして」という表現は言葉だけ見ればそれぞれ相反しているように見えるかもしれないが、実のところ両者とも「今日・此処の論理とはかけ離れたところにある何か物凄い力」によって人物が荒波に揉まれる葉舟のように翻弄されていく物語世界の枠組みを指摘している。
してみると、明治から三十余年ほどしか経ていない大正初期でも、「江戸」や「侍の論理」への距離感は、現代からのそれとさほど変わらなかったのかもしれない。
大正七年には、鴎外のドキュメンタリックな語りの技法を受け継いだ芥川龍之介が、旗本板倉勝該による熊本藩主細川宗孝の誤殺事件を、主君の精神異常を憂う板倉家臣の視点から描いた「忠義」を発表する。「忠義」で切腹するのはお殿様である板倉勝該であるけれども、そこには「今」にはない不可解な人物を描き出そうとする芥川の努力があったりなかったりするのじゃなかろうか。
切腹の論理を、現代人には不可触の強烈な何かとして保存していこうとする努力は芥川以降の世代にも継承されていく。
十蘭と切腹
明治生まれの小説家である久生十蘭が戦中(昭和十八年)に発表した『亜墨利加討』。
『亜墨利加討』の主人公は馬鹿囃子の太鼓の名人で、戊辰戦争末期の各地の戦場をのんべんだらりと旅をする。
旅を終えて大好きな伯父の待つ江戸の長屋まで戻ってくると、伯父の娘から伯父が切腹したと聞かされる。なんでも、伯父は湯屋の帰りに運悪くぶつかってしまったアメリカ人水兵からボコボコに殴られた。最初はなんでもないように済ませていたが、娘から「なぜそのような侮辱を受けたのに父上は死なないのですか」と難詰されて、「それもそうだな」と腹を切ったという。
主人公は娘を恨む。娘が強く当たらなければ伯父は無理に死なずに済んだはずだ。しかし、終わってしまったことはしょうがない。それより許せないのはアメリカ兵で、現地へ帰国した仇どもを討とうと決意した彼はなんと訪米する楽団の一行に紛れ込む。
最終的には、楽団に属する友人たちの支援を受けて、見事本懐をとげるわけだが、その後即座に自分も屠腹して後始末つけることにする。かくして彼は日本男子らしい見事な切腹を果たす。なんだか華々しい終盤のように思われるかもしれないが、肝心の仇討本番の場面も主人公切腹の場面もスッと飛び越えていきなり「行ってきます」→「やりました」の超高速展開で終わるので、見た目以上にかなりイレギュラーな構成である。
ともあれ、この伯父に切腹を強いる娘とやらが実に酷い。主人公としてはこの娘に恨みを向けてもいいはずなのに、娘はいつのまにか舞台から退場してしまい、物語は渡米仇討劇という時代小説に類をみない珍展開へと集約していく。切腹に足るだけの理由があるならば、それを実行するまでのプロセスはどうでもいいのだ。十蘭はそういう結果主義で切腹を理解していたのではないだろうか。一度武士が切腹すると口にしたら、論理や理由はどうあれ、誰もそれを止められないし、止めようとすらしない。
十蘭作品に出てくる切腹はどれも思い切りが良い。「ボニン島物語」では極貧の津軽侍が町人と喧嘩している最中、相手に差料を竹光と看破され、たまたま居合わせた武士の一行に爆笑される。それを恥じて当たり前のように切腹を決意するが、刀を買い戻す金もないので割った茶碗だかとっくりのかけらだかで腹を切ることに決める。さっそく腹を切るのかなあ、と思っていたら、見送りにきた朋輩と津軽藩の貧窮事情についてとくとくながながと嘆きあう。もしかしたら、こいつ死なないんじゃないかなと危ぶみかけたところでやはりあっさり死んでしまう。この緩急のつけかたが、モダンボーイ十蘭なりの「武士のロジック」との間合いの取り方なんだろう。
戦後の切腹
敗戦は理想化された日本という国もろとも、理想化された武士像まで地べたへひきずりおろした。
坂口安吾の「堕落論」に言う。
歴史という生き物の巨大さと同様に人間自体も驚くほど巨大だ。生きるという事は実に唯一の不思議である。六十七十の将軍達が切腹もせず轡を並べて法廷にひかれるなどとは終戦によって発見された壮観な人間図であり、日本は負け、そして武士道は亡びたが、堕落という真実の母胎によって始めて人間が誕生したのだ。
これが「五月の歌」という戦時中のエッセイで、機雷にふれて沈没した商船の責任の取って切腹した船長に対して、その妻が捧げた和歌を「美しい歌だと思つた。」と讃えたのと同じ人物の筆によるから戦争というのはわからない。
日本の敗北を武士道の敗亡と直列につなげた人間はなにも安吾だけではなかっただろう。鴎外以来、聖域に置かれてきた切腹という不可解な何かに対して、切腹の俗化、つまり理性や道理をもってアプローチしようという試みがはじまったのはこの頃からではないかと言いたいところではあるが、前述のとおり、昭和十三年には吉川英治がある一定のレベルで達成してる。
まあ、しかし、切腹のパラダイムシフトが起こったのはやはりこの頃からではなかったか。安吾は敗戦から二ヶ月後には早速、切腹の脱神話化に乗り出した。短篇「露の答」だ。
明治のころ、痴情のもつれで内縁の妻に追い掛け回されて逃げていた政治家が、宿屋で腹を切って死んでいるのが発見された。いったい特に死ぬ理由もないだろうに何故だろう、内縁の妻が怖くて死んだのだろうか、などと憶測を呼んだが、真相はなんということもない。
内縁の妻に居場所をつきとめられて、彼女ともみ合ってるうち、彼の所持していた脇差しが腹にささってしまったのだ。政治家は当初傷が浅いと思い込んで、気が大きくなり、逆ギレして内縁の妻を説経し、離縁を告げた。ようやく悪妻を追い出した政治家だったが、傷が悪化し、すぐに死んでしまったのだった。
なんとも情けない話だ。ここには「ギリシア悲劇的な運命の桎梏」や「その時代のものとして、人々の感情行動の必然のモメント」もない。いつでもどこでも見られそうな、下世話な痴話喧嘩があるだけだ。こういうふうにして安吾は、戦時中に崇拝されてきた武士道に後ろ足で砂をかけた。
サラリーマン化していく武士と切腹
武家社会というシステムにすり潰されて死ぬ男たちの不条理をあからさまに悲劇として捉える視点。そういう視点ができたのは、わずかここ五十年ばかりの間のことのように思える。
(浅野内匠頭の切腹などとは明らかに一線を画する)、下っ端武士の切腹がなぜ悲劇として受容されるようになったかといえば、戦後十数年のあいだにある回路が形作られたからだと思う。
すなわち、「武士」を「サラリーマン」と等号で結ぶ回路が。
そうした悲劇性をメインに据えるようになったのは、映画でいうと多分『切腹』(小林正樹監督、滝口康彦原作、62年)、『武士道残酷物語』(今井正監督、南條範夫原作、63年)あたりから。高度経済成長期の日本で会社に使い潰されるサラリーマンたちの悲哀をたくみにくみ取り、当時まだ軒昂だった左翼運動とも呼応したこれらの諸作は、切腹という現代人からかけ離れた行為に一定のリアリティを与えた。『武士道残酷物語』などは、江戸時代の切腹を、第二次大戦中の特攻隊員、さらには戦後のサラリーマンとエピソードをフラットに繋いでいくことで、勤め人としての武士を通じて、切腹を意図的にモダナイズしようと試みている。
そこでもやはり、切腹とは武士や武家社会というシステムの行きつく終着点なわけだ。なかば自動化されたシステムでもある。そこに目的を求めるのはむしろ不純ですらある。
たとえば、『切腹』(原作題は「異聞浪人記」でプロットはほぼ同じ)の食い詰め浪人・千々岩求女は井伊家の江戸屋敷の軒先で狂言切腹を演じて、井伊家から厄介払いの小遣い銭をせびろうと企むものの、彼の真意を見ぬいた井伊家家臣に狂言を逆手に取られ、切腹を強いられてしまう。
いわば千々岩求女は切腹という行為を合目的的に用いようとしたために、無残で無意味な死に追いやられてしまったと言える。そして、そもそも切腹とは無残で無意味な死にざまなのだ。
ところが『切腹』にはその先がある。
江戸時代の論理に照らして受け止めるならば、千々岩求女の死もそこで完結するものでなくてはならないはずだが、『切腹』では千々岩求女の仇を取ろうとする人間が出てくる。『武士道残酷物語』が切腹を特攻と重ねたのと同様に、そこには切腹に(この場合はネガティブな)意味を求める現代性が滲んでいる。
山田風太郎と切腹
学生運動を中心とした日本の左翼革命運動は七十年前後を境に求心力を失い、急速に衰亡していく。その断末魔ともいえる浅間山荘事件から半年後の七十二年七月に発表された山田風太郎の短篇「切腹禁止令」では、六十年代的なウェットで苛烈な切腹作劇から離れ、むしろ無意味で無様な前近代*7の象徴として、切腹がとことんコケにされていく。
主人公である小野清五郎*8は幕末の混乱期に、所属している香月藩で尊王の志を同じくする同僚、尊敬する勤王派の巨魁、佐幕派のトップの三人それぞれの切腹現場に居合わせる。その有様がいずれも武士の尊厳とはかけ離れた、あまりにどうしようもなく情けない死に様だったことに清五郎は愛想を尽かす。
時代が明治へ移り、議会の前身である公議所に公儀人(議員)として奉職するようになった清五郎は、昔垣間見た三者の凄惨な死に様を思い出し、「切腹禁止令」法案を公議所に提出する。それが守旧派の侍たちの反撥を呼び、よってたかって清五郎を切腹させようと工作しはじめる……という奇怪な筋。
「切腹禁止令」で清五郎が遭遇する三つの切腹シーンはいずれも長い。無駄に長い。そして、グロい。
たとえば、清五郎の尊敬する香月藩勤王派の領袖江崎帯刀の切腹シーンはこういう感じ。
「ククククク……チチチチチチチ……くわーっ」
そんな奇怪な声をあげながら、江崎帯刀は酔っぱらいみたいにそのあたりをよろめき歩いた。おしひらかれたその下腹部に、血まみれの皮下脂肪や腹筋や腹膜や大網などがむき出しになりーーいや、それより、そこからだらだらと灰色の大腸がたれ下がって畳にひきずられているのに、みな全視覚を奪われた。
あとで知ったところによると、帯刀は奥の書院の机に墨痕粛然たる遺書をしたため、ひとり従容として作法通りに切腹を図ったらしい。ーーところが、左腹部に刀を突き刺し右へひいてから、そのあまりな超痛苦に意識錯乱におちいって、そのまま跳ねでてきたらしい。
(中略)
「チチチチチ……イイイイイ……くわーっ」
彼はまったく狂乱状態でそんな苦鳴をしぼりだしつつ、凍りついたみなの視線の中で、そこの柱に抱きつき、裂けた腹をおしつけ、最期には交接運動みたいな腰つきを二、三度繰返したのち、柱の根もとに血だらけの蛙のようにへたばって、凄まじい痙攣とともに息絶えた。くいしばられた歯のあいだから、はみ出した舌が食いちぎられて垂れ下がっていた。
あまりにも明るい晩夏の残光の中でに、それは夢魔としか思われない光景であった。
なんだ「ククク」「チチチ」って。
ここで描かれている小林泰三じみた切腹描写は完全にスプラッタホラーの領域で、他の切腹フィクションにありがちな潔さやカッコよさなどは微塵もない。
現在でも時代小説を書く作家はだいたい侍だとか刀だとか切腹だとかが好きで書いている節があるので、意識的にか無意識的にか、麗々しく荘厳な切腹シーンを演出しがちだ。だが、山田風太郎作品にはそうした傾向に対する悪意しか嗅ぎ取れない。
作中、山風は福沢諭吉の口を借りてこんなアンチ切腹論をぶつ。
「腹なんぞ切っても人間なかなか死ねるものではなく、大苦しみは当たり前のことだが、いったいいつから日本にこんな理屈に合わない風習が生じたものか。おそらく魂はハラに宿っておるという医学に無知蒙昧な迷信から発したものでしょう。このごろ王政復古というが、しかし古えの王政のころーー奈良時代や平安時代、いわんや神武天皇さまのころにはそんな怪習俗はなかったようだ」
と、首をかしげてにがにがしげにいった。
「西洋人ーーいや、まともな頭を持つ文明人から見れば、土人の首狩りの儀式と同様でしょうな。人の首を切るのじゃなく、自分が痛いのだからいっそう馬鹿げておる。それは、是非、法律でやめさせなさい」
「切腹禁止令」は笑劇としての性格が色濃く、一時の悪乗りで書かれたのかとも思われそうだけれども、山風的には思うところあって執筆したものだったらしい。
「切腹禁止令」に先駆けて同年五月に発表したエッセイ「斬首復活論・切腹革命論」(『死言状』収録)でもこんなことを述べている。
もう一つ切腹刑を作ってもいいと思う。
ただし、名誉あるサムライの伝統として復活するのではない。逆に、その伝説をひっくりかえすために復活するのである。 こんな伝統は昭和二十年八月以来消滅したかと思っていたら、なかなかどうして存外しぶとく生きながらえていて、例の市ケ谷台上、一作家の壮絶な実演となった。この分ではまだなかなかこの風習は日本の地上から絶滅しないだろう。
これを壮絶と形容するのは、なお伝統にとらわれている観念からで、実際は、その苦痛たるや絞首刑斬首刑の比ではない。腹なんか切っても人間は容易に死ねるものではない。この伝統の淵源は、魂はハラにあると信じていた時代の医学的無知にある。こういう科学的誤解から発した酸鼻な死の儀式がいつまでも伝えられて、日本の男が名誉ある自決をとげなければならないときはハラキリをしなければ恰好がつかないということになっては、これまた量刑不当といわなければならない。不合理な伝統はなるべくその糸を絶った方がいい。
だから、私のいう切腹刑は極悪人の最重罪として行わせ、サムライのハラキリを永遠に払拭するためである。
ごらんのとおり、前述の福沢諭吉の切腹批判とかなり重複している。
山風のこうしたニヒリスティックな態度は七十年代以前の切腹描写へのアンチテーゼというよりは、青年期に敗戦を経験した戦中世代である彼の心性や個人的資質に帰すべきだろう。山風にとって武士の不条理とは戦時中の日本人の不合理さと地続きであり、切腹などは最も唾棄すべき、野蛮な情緒趣味でしかない。総合的なオブセッションでは明らかに山風のほうが勝っているだろうが、創作において切腹の神聖さを無効化しようと試みたという点では安吾の「露の答」と似ている。
(ここで四十年くらい一気にすっ飛ばす)
ちかごろの切腹
近年を代表する時代小説作家、葉室麟の直木賞受賞作『蜩ノ記』は切腹を主題に据えた切腹ミステリーだ。
幼なじみである同僚とのつまらないいさかいから職を解かれた若い武士、庄三郎は藩の家譜を編纂している戸田秋谷を監視する任につく。秋谷は七年前に前藩主の側室と密通し、それを見咎めた小姓を斬殺した罪で十年後(物語開始時では三年後)の切腹を言い渡されていた、という設定。
庄三郎でなくとも誰だって不審を抱く。殿様の側室を寝どった上に小姓を斬り殺した男がなぜ即刻切腹にもならず、家譜の編纂などに従事しているのか。切腹するにしても、なぜ十年という猶予が切られているのか。読者は、秋谷が巻き込まれた事件をまず額面通りには受け取らない。視点人物たる庄三郎もそうしない。もちろん、事件には裏があるのだけれど、ここではまあ詳しく触れないことにする。ひとつだけ言っておくならば、もちろん秋谷は無実だ。
『蜩ノ記』は切腹にミステリー要素をからませているという点では『人魚ノ肉』と似通っているかもしれない(どっちもカタカナのノがタイトルに混じってるし)。しかし『蜩ノ記』では実のところ切腹の原因、その真相は実のところ物語上あまり重要ではない。この真相は小説がだいたい三分の一程度進んだ段階で明かされ、それがわかったところで秋谷の切腹を差し止めるのは不可能だ。
ではなんのために腹を切るのかーーそれが作中起こるある事件をきっかけに変化していき、ラストへと至る。
『蜩ノ記』において秋谷は、上の都合で簡単に下を切り捨てる武家社会の力学を批判しつつも、最終的に従容として切腹の座につく。その死に様を、美しいものとして描く。それは六十年代のように戦闘的な社会批判にも、江戸時代のリアリズムを突き詰める方面にも振れない、ある種今世紀的な玉虫色の結論であるように思われる。身勝手な上司の理不尽には啖呵を切りつつも、構造的な理不尽には逆らいきれない。そうした中途半端なリアリズム、中途半端なファンタジーの折衷をもってオトナの小説と呼ぶんだとしたら、こんなに悲しいことはないよね、と思わないでもないけれど、まあ今はどうでもいいです。
やはりこの作品でも切腹についての意味付けがなされてる。切腹が主題なんだから切腹に意味があるのは当たり前なのだけれど、『蜩ノ記』では一旦目的性を失った切腹に再度ポジティブな意味付けがされているのであって、そこには「意味や目的のない切腹などあってはならない」という強いヒューマニズムがうかがえる。
山田風太郎のところでも述べたように、だいたい時代小説とか切腹とか書く人は悲劇として書くにしろなんにしろ、それを美しく書きたがるものなので、これからもまあそうなんでしょう。『無限の住人』のウルトラマンもなんかそういう清々しさを拭えなかったし。あ、そうだ。漫画も混ざるとさらにややこしいことになってくるなあ……。
そろそろ眠くなってきたのでやめます。
何の話しようとしてたんだったかな……。
まあ、切腹の描き方にも色々あるけれども、個人的には無理やり目的性をもたせた切腹よりは、久生十蘭みたいな切腹のやりかたが好きです。
切腹が象徴するもの、切腹に託されるものは時代によって変化していく。そういうフィクションにおける切腹の精神史みたいなものを詳細にたどっていけばそれなりに興味深い仕事になるんだろうけれど、私はめんどうくさいのでやりません。
付録:切腹パターン集
要素:理由(切腹の罪状や理由が周知されているかどうか。物語の進行具合によって状態変化しやすい)、罪(その罪状や理由が事実と一致しているか)、実行(切腹が最終的に完遂されるかどうか)+自主性(みずから切腹を望んで、あるいはすすんで受けれて刑にふくしたかどうか)
1.理由(明白)、罪(有罪)、実行(完遂)
→有罪の人間が普通に切腹した。物語内の通過点 or 一要素。(e.g. 五味康祐「勘左衛門の切腹」等多数)
2.理由(明白)、罪(有罪)、実行(未遂)
→有罪の人間がなんらかの理由で切腹を遂げられなかった。(e.g. 杉浦日向子の(多分)『東のエデン』に収録されていたタイトル思い出せない短篇)
3.理由(明白)、罪(無罪)、実行(完遂)+自主性(ナシ)
→濡れ衣を着せられて死亡。ミステリ的には「真犯人は誰か?」「彼を陥れたのは誰か/なぜか?」ということが焦点に。ドラマ的にはここから彼の無念を晴らす存在が出てこなきゃいけない。『必殺仕事人』なんかで多そう。
4.理由(明白)、罪(無罪)、実行(完遂)+自主性(アリ)
→濡れ衣を着せられていることを了解しつつ切腹。真相が提示されてない場合は真相を探るミステリに(e.g. 「肉ノ人』)、真相が提示されてもなお死を切腹した場合は「なぜあえてすべてを呑み込んで従容と切腹を選ぶのか?」が焦点になる(e.g. 『蜩ノ記』)
5.理由(明白)、罪(無罪)、実行(未遂)
→濡れ衣の罪が晴れてよかったね、というパターンというか一場面というか。(e.g. 「夏虫行燈」)
途中まで「有罪」だったのがある要因で「無罪」に変化するパターンもここか。(e.g. 冲方丁『天地明察』)
6.理由(不明)、罪(有罪)、実行(完遂)
→何かの刑罰でなくて、自主的に切腹を選んだパターン。理由を知りたい人間は事後に捜査しなければならない(e.g. ある時点までの「亜墨利加討」)。理由があきらかになれば1へ転化。
7.理由(不明)、罪(有罪)、実行(未遂)
→自主的に切腹しようとして実際いいとこまでいったんだけど、なんらかの理由で死ねなかったパターン。当事者の口から理由が語られる。語られたあとは2へ転化。
8.理由(不明)、罪(無罪)、実行(完遂)
→無実の罪やある勘違いの理由をひっかぶって勝手に死んだ。あるいは、上からの圧力で殺されたが、そもそもの罪状すら明らかにされないケース。
9.理由(不明)、罪(無罪)、実行(未遂)
→勝手に切腹しようとしたがなんらかの理由で死ねなかった。理由が明らかになれば5へ転化。
思いつきで指標を作ってみたけれど、うまく運用できない。

- 作者:山本博文
- 出版社/メーカー:光文社
- 発売日: 2014/03/12
- メディア:文庫
- この商品を含むブログを見る
*1:なぜ自殺するのに喉や胸でなく腹を突くのか、については、「お腹の中に魂が宿っている」と考えたから、ということらしい
*2:籠城戦で追い詰められた城主が部下の助命と引き換えに自分だけ切腹するのもこのパターン
*3:といっても書き出しでは「妙解院殿(松向寺殿)」としか書かれていないので、よほどの歴史マニアでないかぎり誰のことだかわからない
*4:といっても、これ自体かなり短めの短篇なのだが
*5:あらすじ:番衆を務める平四郎。ある日、彼は同僚から恋敵である図書係の甚三郎が役目で不祥事を起こし、四日後に切腹すると聞かされた。なんでも、甚三郎は管理を担当していた殿様大事の歌仙本を紛失してしまったらしい。城中では甚三郎が金に眼がくらんで盗みだしたのではないかと噂がたつ。身の潔白を主張する甚三郎だったが、家老たちは四日後までに歌仙本が出てこないかぎりは彼に詰め腹を切らせる処置を下した。結局、四日たっても紛失した本は見つからず、甚三郎は白洲へひったられる。にっくき恋敵の死を見物するつもりで城へ上がった平四郎は、折悪しく家老と遭遇し、剣の腕を見こまれて介錯役を命じられる。一介の侍である平四郎に否も応もない。介錯役の準備を進めていると、突然、甚三郎の許嫁であった娘に押しかけられる。彼女こそ、平四郎が恋い焦がれたものの、最終的に甚三郎にかっさらわれてしまった女性であった。甚三郎の潔白を信じる彼女は、平四郎が個人的な恨みから彼をハメたのではないかと糾弾。愛しさ余ってにくさ百倍、売り言葉に買い言葉で平四郎はつい彼女の疑いを認めてしまう。それを真に受けて彼女がお城へ訴え出てしまったからさあ大変、一転平四郎は「歌仙本盗難の真犯人」として総出で追われることに……
今週のトップ5: 『ハウス・オブ・カード』Netflix配信開始、「Moth to the Flame」 、『マネー・ショート』、『ズートピア』全米公開、『ロデリック』発売、「Kiddy Pool Dreams」
今週は特に何もしなかった。
Chairlift「Moth to the Flame」(『MOTH』)
Chairlift - Moth to the Flame (Audio)
なぜMVを作らないのか。
Chairlift のMVといえば分岐未来ものSFっぽい「Met Before」が好きです。
Chairlift - Met Before
もちろん、「I belong in your arms」日本語ヴァージョンのカラオケデモっぽさ溢れるMVも好きです。
I Belong In Your Arms (Japanese Version)
『ハウス・オブ・カード』、Netflix で配信開始
![ハウス・オブ・カード 野望の階段 SEASON1 ブルーレイ コンプリートパック [Blu-ray] ハウス・オブ・カード 野望の階段 SEASON1 ブルーレイ コンプリートパック [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/517WA1tLFgL._SL160_.jpg)
ハウス・オブ・カード 野望の階段 SEASON1 ブルーレイ コンプリートパック [Blu-ray]
- 出版社/メーカー:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
- 発売日: 2015/10/07
- メディア:Blu-ray
- この商品を含むブログを見る
このところアメリカドラマのクオリティの上昇具合がやばいよねみたいなことよく聞きますけれど、本当にイッキ見が止まらないクラスだったのは『ハウス・オブ・カード』くらいですよ。あと、『ファーゴ』。
主役のフランシス(フランク)・アンダーウッドさんはとりあえず目の前の目的のために誰かを陥れたり、仲間を切ったりして勝利をつかむんですけれども、それはその場限りのもので、陥れられたり切られたりした人たちがあとで意趣返しにやってくる。で、それを抑えるためにまた誰かを犠牲に……というのを繰り返すツイスター(遊具の)ドラマで、フランクさんは基本サイコパスな人ですから他人から向けられるヘイトを軽視してるんですね。だから問題が起きたときも権力や金で解決しようとするんだけど、それが通じない相手っていうのが出てくる。それをいかに力技と詭計でひねりつぶすかというのがアツい。このへんの駆け引きの妙は、プロデューサーのフィンチャーというよりかは、『スーパー・チューズデー』の脚本家ボー・ウィリモンの功績でしょう。
『マネー・ショート』
社会的な意義と意識は大変に高いものがあるし、専門用語の飛び交う難解な金融システムをなんとか観客に伝えようとあらゆる努力を尽くす様には敬意すらおぼえるんだけれど、いかんせんそのための「クール」なメタ手法(キャラが画面に向かって語りかけてきたり、マーゴット・ロビーやセレーナ・ゴメスが本人役で説明に出てくるとこ)が小慣れてないせいとバリー・アクロイドの躁的なカメラワークとの噛みあわなさで作品全体のリズムを殺してしまっていて、もうちょっとそこらへんなんとかならなかったのかなあ、といいますか、じゃあ正攻法にしとけばよかったのかといえば、アダム・マッケイさん昔から何やってもトロいところがあって、資質としてどうしようもないのであればどうしようもないんじゃないかな。なんだかんだ言うて、スコセッシは偉大です。
ただ原作がべらぼうに面白いのと、クリスチャン・ベールのアスペルガー演技(原作に「この人はアスペルガー」って書かれてるんだからしょうがない)がやたら気合入ってるのとであらかじめ底上げというかブーストかかってるおかげで、130分の長丁場を飽きさせないつくりにはなっている。
『ズートピア』全米公開
日本では四月公開。
予測では『ロラックスおじさんの秘密の種』(いつ見てもキチガイじみたタイトルだ)を抜いて「三月公開のアニメ映画でオープニング興収全米歴代ナンバーワン」*1というすごいのかなんだかよくわからない記録を達成する見込みだとか。『ロラックスおじさん』に勝ちましたと言われてもなあ。
ちなみに、このまま推移するとWDAS作品としては『ラプンツェル』(2.22b)を抜いて歴代二位の成績をあげそうな気配。
批評家のレビューもなべて好評で、社会問題に対する意識の高さが主に評価されてるっぽい。善きことを高いクオリティで真っ当に描くことで広く支持される『スポットライト』パターンか。
純エンタメ的にはバディ・ムービーとポリティカルサスペンスを巧く融合させた、ディズニーらしからぬダークなプロットが好意的にうけいれられたみたいですね。:
「今年のベストアニメ映画」*2、「ディズニー最高傑作のひとつ」*3、「現状今年のベスト作品」*4、「現時点での今年ベスト映画であり、間違いなく今年のアカデミー長編アニメ賞にノミネートされる作品」*5、「まず間違いなくオスカー候補」*6、「『アナと雪の女王』に比する子どもたちにとってのヘビロテ映画になるポテンシャルがある」*7、「今現在こそがアニメの黄金期なのだと強い確信を抱く出来」*8、「私にとってのベストアニメ映画。ここ一、二年のベストでも、ここ十年のベストでもなく、人生通じてのベストという意味で」*9。
待ち遠しい。
『ロデリック』発売。

ロデリック:(または若き機械の教育) (ストレンジ・フィクション)
- 作者:ジョン・スラデック,柳下毅一郎
- 出版社/メーカー:河出書房新社
- 発売日: 2016/02/26
- メディア:単行本
- この商品を含むブログ (2件) を見る
今週のトップ5:『ハウス・オブ・カード』シーズン3&4、『バタード・バスタード・ベースボール』、『愛しのグランマ』、『Punch Club』、『セッション』、『マネー・ショート 華麗なる逆転』
『ハウス・オブ・カード』シーズン3&4
シーズン3はまるごと回り道みたいな話で、ロビン・ライト演じる奥さんが前に出てきたぶん、彼女の心理的不安定さがドラマを不合理に乱していた。『ハウス・オブ・カード』も人気シリーズ化に伴う足踏みグダグダ化を免れ得なかったのだなあ、などと思っているとところがどうしてシーズン4にそのグダグダがちゃんと活きてきて、至高のラストカットへ繋がるのだから、やはり上手い。
ウェイ兄弟『バタード・バスタード・ベースボール』
The Battered Bastards of Baseball - Official Trailer - Netflix [HD]
Netflix 限定配信のドキュメンタリー。
アメリカの野球は数々の神話に彩られている。小説よりもなお信じがたい逸話たちに。アルバート・グッドウィル・スポルティングの「アラウンド・ザ・ワールド・ツアー」、連勝をもたらす不具の少年、ブラックソックス事件のアンラッキー・エイト、野球発祥の伝説をめぐるクーパースタウンの興亡、バンビーノの呪い、「マネー・ボール」。だから、アメリカの偉大な作家たち、ロバート・クーヴァー(『ユニヴァーサル・プロ野球協会』)、フィリップ・ロス(『素晴らしいアメリカ野球』)、ドン・デリーロ(『アンダーワールド』)、マーク・トウェイン、ケン・カルファス、ホイットマン、W・P・キンセラ(カナダ人だが)、チャド・ハーパックといった人々は、神話について書くのと同じ態度で、ベースボールについても書いてきた。
1970年代の数年間にだけ存在したチーム、ポートランド・マーヴェリックスは今もアメリカ球界に燦然と輝く神話のひとつだ。
事の発端は、1971年にポートランドから3Aに所属していたビーバーズというチームが退去した事件だった。メジャーとまでは言わないものの、確かな実力をもった3Aチームのフランチャイズであった事実は西海岸の地方都市にとってはちょっとした誇りだった。それを親チームであるパドレスは無慈悲にも別の街へ移籍させてしまったのだ。
メジャー球団の下部組織であるマイナー球団は親チームの意向に逆らえない。1970年代初頭はメジャーリーグ組織がちょうど今の形みたく成熟してきたころで、メジャーはそれまで地方にあふれかえっていた独立球団をマイナーリーグチームとしてどんどん吸収していった。メジャーにとっては一球団で多数の選手を抱えるよりも、若手をマイナーで育成したほうが効率がよかったのだ。気がつけば、往時には数百チーム存在した独立球団は1970年にはゼロになってしまっていた。
そこにビング・ラッセルが現れた。西部劇映画やドラマを中心に活躍した脇役俳優で、かのカート・ラッセルの父親だ。彼は長らく出演していた西部劇ドラマ『ボナンザ』が終了し、半隠遁生活に入っていた。
そんな彼がいきなりポートランドに球団を設立したいと言い出した。少年時代にルー・ゲーリックやヨギ・ベラの居たヤンキースに随伴して選手たちから可愛がられ、自身も一時期独立球団のプレイヤーであったビングは、人一倍野球への情熱を持った男だった。役者に転じてもその情熱は衰えず、自分の子どもであるカートを起用し、野球の教習ビデオを制作してプロ選手からも「使える」という評価を得た。
「殿堂入り選手となり、アカデミー賞を受賞するのが夢だった」と語るビングのフッテージ映像。「そのどちらも叶わなかったけどね」
その彼がビーバーズ亡き後のポートランドで新球団を設立するという。ポートランドの住民たちは彼を懐疑の目で見た。役者だかなんだかしらないが、得体のしれないよそものが野球チームを作るって?
しかも、シングルAのチームだという。ビーバーズは3A。そんなレベルの低いリーグの球団に誰が興味を持つだろう。誰が誇れるだろう。名前はマーヴェリックス。ビングの出演したドラマの番組でもあるが、まさか?
あたりまえな話、野球チームには選手が要る。他のマイナーチームなら親チームのメジャーチームがドラフトやトレードで獲得した選手たちをあてがってくれる。しかし、マーヴェリックスは文字通りゼロから立ち上げた球団なので、選手も一から集めないといけない。
さっそくトライアウトが開催された。全米各地から四百から五百人の志望者が集った。誰も彼も個性的な面がまえで、元プロもいれば素性の知れない単なる野球好きまでいた。みな他のプロ球団なら獲らないような「はぐれもの」ばかりで、ただ野球がしたいという熱意だけで遠路はるばるやってきたのだった。
ビングはそこから三十人ほどの選手を選抜し、元マイナーリーガーの監督をどこからかひっぱってきて、ついに球団を作り上げてしまった。他球団のマイナーリーガーとして活躍していたカートもDHとして馳せ参じた。
何もかもが初めてずくしの球団だった。左利きのキャッチャー、女性のジェネラル・マネージャー、ボール・ガール、ボール・ドッグ……。
「80戦80勝できるチームができたよ」と大言壮語するビングは他の球団にとっての冷笑の的だった。しょせん素人にケが生えたような草野球チームじゃないか。うちは新人や若手が中心といえど、全米から選りすぐったトップ選手たちで成っているんだ。80戦で一勝もできれば御の字じゃないか。
しかもマーヴェリックスは勝つことではなく、「楽しんでやる(Fun)」ことを第一の目標として掲げているという。月給も300ドルぽっち。そんなお遊びみたいなチームが日々切磋琢磨している一流選手たちに敵うわけがない。誰もがそう思っていた。
ところが開幕戦、マーヴェリックスは勝ってしまう。それもただの勝ちではない。ノーヒット・ノーラン。そこから連勝に次ぐ連勝がはじまる。メジャースカウト陣お墨付きのプロスペクトを、つい数カ月前まで素人だった選手たちが軽々とさばいていく。
ポートランドの人々も何かただならぬ事態が自分たちの街で起こりつつあると気づく。その何かをたしかめるべく、球場に足を運ぶ。一試合あたりの観客動員数の平均は4000人を超えた。シングルAのチームとしてはもちろん異例の集客だった。選手に「楽しむこと」を薦めるビングは、当然ながら観客たちを楽しませることも好きだった。スター選手を盛り上げ、さまざまなパフォーマンスを考えだしては実行し、次第に街とチームは一丸となっていった。マスコミや野球雑誌もこの異色の「バスターズ」に飛びつき、特集を組んだ。気がつけば、全米一有名なマイナー球団になっていた。
創設初年度、ビングはシングルAの最優秀経営者賞を受賞する。成績は地区で二位。プレイオフに進出するも、惜しくも優勝はならなかった。
この勢いに誘われて、あるピッチャーからの入団希望が届く。名前はジム・バウトン。かつてヤンキースで活躍したスター選手で、球団をクビになったあとメジャーリーグの内幕を暴露した『ボール・フォア』という本を出版して、球界からの不興を買っていた。その後、ロバート・アルトマン監督の『ロング・グッドバイ』で主人公フィリップ・マーロウの友人テリー・レノックス役を演じるなど様々な道を模索していたが、やはり白球への未練たちがたく、36歳にしてマーヴェリックスで復帰したいとの言うのだった。ビングは即答した。もちろん、大歓迎だ。
名選手を得て、ならずものたちはさらに強くなる。リーグの連勝記録を塗り替え、三年連続でプレイオフに進出した。だが、どうしてもリーグ優勝の壁を乗り越えられない。これにはちょっとしたからくりがあった。メジャーでの大勢が決まる終盤戦になると、上のリーグから選手たちが降格してきて、マイナーチームがシーズン前半より強化されてしまうのだ。
しかもマーヴェリックスは他球団から忌み嫌われていた。メジャーチームから見放されたり見捨てられたりした選手たちが、メジャーの見込んだ選手たちをぶちのめす。その現実を認めることは、彼らにとって自分たちの目が節穴であることを認めるようなものだった。メジャーにはメジャーの誇りがある。その誇りが、マーヴェリックスのリーグ優勝を阻んだ。
1977年、球団創設五年目のシーズンに最大のチャンスが訪れる。マーヴェリックスは初となる地区優勝を果たすと、その勢いのままプレイオフの決勝まで勝ち上がる。決勝の相手はシアトル・マリナーズ傘下のベリングハム・マリナーズ。マリナーズには後にオールスター選手となるドラ一新人"ベイビー・M 's"ことデーブ・ヘンダーソンもいた。
ベリングハムで行われた第一戦はマリナーズがマーヴェリックスのエース・バウトンを打ち崩して制した。観客は575人。
ポートランドでの第二戦には4770人のファンが詰めかけ、マーヴェリックスが10-1の大差で勝利したのを祝いだ。
そして最終戦となった第三戦。ポートランドの球場は8000人近い観客で埋めつくされた。文字通り全ポートランド市民が見守るなか、マーヴェリックスは――。
1978年。ふいに、球団に危機が訪れる。ビーバーズがポートランドに帰ってくるというのだ。ルール上、ビーバーズがポートランドのフランチャイズ権を買い戻すといえばマーヴェリックスに否は言えない。
ビーバーズ、そしてメジャー機構の意図は明白だった。マーヴェリックス潰しだ。ビングはあまりに強すぎ、そして人気すぎた。ために、球界の「ビッグボーイ」たちの逆鱗に触れてしまったのだ。バカなことやってんなよ、たかがシングルAが。というわけ。
今や押しも押されもせぬ街のシンボルと化したマーヴェリックスの危機にポートランドは揺れた。そして、あまりにあっけなくマーヴェリックスは消滅するはこびとなった。ルールにはさからえない。ルールを決めるオトナにはさからえない。こうして、アメリカ球界に芽吹いたイノセンスがまたひとつ、摘まれてしまったのだった。
ところが、ここで終わらないのがビングだった。
ビーバーズ(と親チームのパドレス)はビングを前に不遜にもこんなオファーを出した。
「通常ならフランチャイズ権の買い戻しは5000ドルだ。だが、私たちは君とマーヴェリックスに敬意を払おう。2万6000ドル出す。破格だろう?」
事実、破格な提示額だった。だが、ビングは不満気にこう言い返した。
「ゼロがひとつたりないな。2と6の間に」
彼はビーバーズに対して20万6000ドルを要求したのだ。
裁判になった。
誰もがビーバーズ、そしてその背後に控えるメジャー機構の勝利を疑わなかった。どの分野の歴史をひもといてみても、ダビデが勝った回数よりゴリアテが勝った回数のほうが遥かに多い。メジャーレベルからシングルAまで百数十の球団を抱える機構と、最下部リーグであるシングルAの一球団。どちらの言い分が通りやすいかははっきりしている。子どもはルールを決めるオトナにはさからえない。
しかし、ビングがここでも奇跡を起こしてしまった。マーヴェリックス側の言い分が通ったのだ。ビングはビーバーズから20万6000ドルを満額奪取し、ここでも長年球界で信じられてきた法則を覆した。1978年、ビーバーズは居心地わるげにポートランドへ帰還し、マーヴェリックスはその短い歴史に幕を下ろす。通算221勝、158敗。地区優勝一回。プレイオフ出場三回。
伝説は伝説を派生させる。マーヴェリックスは消滅してなお、新たな伝説の枝葉を伸ばした。
エース、ジム・バウトンは40才にしてメジャーリーグで再デビューを果たし、勝ち星を挙げた。
投手兼コーチだったロブ・ネルソンはボールボーイだったトッド・フィールド少年と共同で短冊状にカットされたチューインガム「ビッグ・チュー・リーグ」を開発し、そのアイディアを菓子会社のリグビー社へ売った。「ビッグ・チュー・リーグ」はたちまち人気を呼び、1980年には6億枚を売る大ヒット商品となった。――このガムの売り込みにはバウトンも一役買っている。メジャー球団に対して「(当時問題視されていた)噛みタバコの代わりになる」と営業をかけたのだ。
トッド・フィールド少年は長じて映画業界に身を投じ、2001年には長編監督デビュー作『イン・ザ・ベッドルーム』で作品賞と脚本賞にノミネートされた。その後、06年に『リトル・チルドレン』を撮ったのちは長らく新作から遠ざかっていた(一時期はコーマック・マッカーシーの『ブラッド・メリディアン』の映画化をリドリー・スコットの代わりに担当するはずだったが、いつのまにか立ち消えに)が、どうやら最近はボストン・テランの『暴力の教義』の映画化プロジェクトを進めているらしい。
若き二塁手ジェフ・コックスはアスレチックスでメジャーデビューを果たし、現役を退いてからはピッツバーグ・パイレーツやフロリダ・マーリンズでコーチとして活躍した。
夢破れたマイナーリーガーだったラリー・コルトンは現役引退後、ノンフィクション作家へと転身し名を上げた。
カート・ラッセルの俳優としてのキャリアの充実ぶりはいまさら語るまでもないだろう。彼はマーヴェリックスについてこう語る。「俺には四人の姉妹がいたけれど、実の兄弟はいなかった。でもマーヴェリックスに入団して千人もの兄弟ができたんだ。得難い経験だったよ」
そのカートの四人姉妹のうちの一人がマットという子どもを産み、彼は祖父であるビングの薫陶を受けてメジャーリーガーとして大成した。日本でもロッテで活躍したマット・フランコその人だ。
そして、現在、独立球団はアメリカ全土に存在している。リーグの規定によりマイナーリーグには参加できなくなったものの、独立球団同士で独立リーグを運営して、メジャーに見放されたり見捨てられたりしてもなお夢を追う選手たちを受け入れている。
ニューヨーク・タイムズ紙のダニエル・M・ゴールドは本作を評してこう言っている。
「ビング・ラッセルが造った。そして、彼らは来た」
『フィールド・オブ・ドリームス』のセリフをもじったこの評言は、アメリカの野球界がそれこそ『フィールド・オブ・ドリームス』のごとき嘘みたいなドラマに満ち溢れていることの証左でもある。最近でもハリウッドは野球映画を作るにあたって『マネーボール』、『42』、『ミリオンダラー・アーム』と実話ネタにことかかない。
なぜアメリカ人はそんなに野球が好きなのだろう。より精確には、なぜそんなに野球の話が好きなのだろう。
詩人の平出隆は『ベースボールの詩学』(講談社学術文庫)で寺山修司を引いてこう分析している。
たとえば寺山修司は、「キャッチボールは好きだが野球はきらいだ」と、対談相手のシカゴの詩人、ネルソン・オルグレンに語ったという。 その理由はといえば、「キャッチボールにはホームがないが、野球にはホームがある」からであった。寺山修司のレトリックのめざしているところは明快である。彼はベースボールの「ホーム」を文字どおり「家庭」に見立てて、戦後社会の家庭の喪失が、虚構の「ホーム」に帰還したがる男たちのメロドラマとして、ベースボールをかつてない隆盛にみちびいている、といったことをいいたいのである。
「ホーム」タウンである球場に地元ファンたちが、「ホーム」に還ろうとする選手たちを応援する。そういう素朴な家族的連帯感、あるいはそういうものへの熱望が彼らの郷愁をかきたてるのかもしれない。
チームができればそこはホームになる。
東海岸バーモント州生まれのビング・ラッセルは、晩年を西海岸のポートランドとカリフォルニアで過ごした。
ポール・ワイツ『愛しのグランマ』
Grandma Movie CLIP - Money (2015) - Lily Tomlin, Julie Garner Movie HD
若い恋人と喧嘩別れしたばかりの老年レズビアン(リリー・トムリン)のもとを、だしぬけに18歳の孫(ジュリア・ガーナー)が尋ねてきてこう告げる。
「妊娠しちゃった。お金ないから中絶費用の600ドル貸してくれない?」
グランマは大学で教鞭を取る著名なフェミニスト詩人だ。ふだんならそんな小銭はわけなく払える。が、この日はたまたま巡り合わせが悪かった。恋人とのゴタゴタでイラついていたグランマは、一時の激情に任せてクレジットカードを破ってまっていた。すぐに引き出せる現金もない。
孫の側も、妊娠を母親に内緒でグランマのとこにやってきた手前、親の金は頼れない。かといって、他にあてがあるわけでもない。
堕胎医の予約はその日の夕方。
グランマは長年のフェミニズム運動と詩作で鍛え上げられた毒舌を無尽に発揮しつつ、孫をひきつれ中絶費用の工面にでかける。
『愛しのグランマ』における家族関係は、その他大多数の映画に出てくるような家庭と較べてかなり毛色が異なる。
まずグランマはおそらく60年代から70年代にかけてのセカンド・ウェーブ・フェミニズムに参加したであろう人物で、一旦ヒッピーっぽい男性と結婚していたもののすぐ離婚して女性のパートナーと結ばれた経歴を持つ。この長年連れ添ったパートナーを喪ったことがサブストーリーのラインに影響してくるわけだが、ともかくこのパートナーとの間に子どもを欲しがったため、他の男性から精子を提供してもらって娘を産んだ。その娘は男性と結婚し、できた子どもが今そこで妊娠している孫、というわけ。
観客はそういう家族のなかへ何の説明もなしに放り出され、80分と短尺の物語を眺めているうちになんとなく上記の関係を理解していく。
明かされていくのは家族構成だけではない。グランマの人生の履歴もだ。
グランマは手っ取り早く現金を捻出するために本棚から数冊の分厚い学術書を抜き出して、「高く売れるわよ」と自信満々に嘯く。目玉はフェミニズムの古典中の古典『女性らしさの神話(The Feminin Mystieque)』だ。しかも著者ベティ・フリーダンのサイン入り。
ところが孫がイーベイで調べてみると、同様の出品に数十ドルの値しかついていない。
グランマは委細構わず旧知の友人へ本を売りに行く。ところが友人の運営するカフェで働く恋人と鉢合わせし、つい感情的になって商談もこじれてしまう。
グランマと孫は今度はグランマの最初の夫へ会いに行く。三十年か四十年ぶりの再会だ。老いてなおプレイボーイの面影を残す彼にグランマは高いプライドを削って金策をたのみこむが、中絶の費用と聞いた元夫は「それだけはだめだ」と断ってしまう。あまり多くの説明はされないのだが、後に出てくる病院のシーンでグランマが何気なしに中絶経験の告白を行うとこから察するに、堕胎したのは彼との子どもだったのだろう。
結局、万策尽きたグランマと孫は孫の母親、グランマにとっての娘の仕事場訪れる。そこでもグランマは罵り合う。グランマの娘にとって、グランマはあまり良い親ではなく、結婚してからはほとんど連絡もとっていない。そこへ唐突に孫を伴って現れて、彼女が妊娠したので中絶費用をくれと要求するのだから、もちろん対話は複雑な事態へと発展する。
要するにグランマはクソババアなのだが、真正直なクソババアなので妙に清々しい。その彼女が歩んできたそれまでの道のりが、孫の中絶費用を無心する過程で遡及され、終局的にグランマは自身の過去や未来と向き合わされることになる。
BGMを極力排した、抑制のきいた語り口による等身大のコメディ・ドラマだ。どうしても気張って描きがちな設定やテーマを、気負いも嫌味もなく描ききっている。必要以上には語らないし、逆に説明不足に陥ることもないギリギリのバランスで80分におさめてしまうのは、流石はベテラン、ポール・ワイツといったところ。これだけ女性しか出てこない映画もなかなか珍しい。

- 発売日: 2016/02/17
- メディア:Amazonビデオ
- この商品を含むブログを見る
『Punch Club』
ボクサーを育てるゲーム。……なんだけれども、映画を含めたポップカルチャーのリファレンスがとにかく膨大。『ロッキー』は当然として、『ファイト・クラブ』のタイラー・ダーデンっぽい男の双子の弟が『スナッチ』のミッキー*1だったり、ピザ配達のバイトで下水道にやってくるとハチマキマスクをしたミュータントワニ忍者に襲われたり、そのピザ屋の主人がどっからどうみてもスティーブン・セガールだったり、敵キャラがザンギエフっぽいロシア人だったりブルース・リーっぽいアジア人だったり……はては『ニンジャスレイヤー』なんかも引用している。そこまで広まっていたのか、ニンスレ。
ダミアン・チャゼル『セッション』
去年死ぬほど観たのがまた映画館にかかっていたのでもう一回観に行った。
テンポの話だ。主人公のテンポはいつもズレている。ちゃんと劇中で説明されているにも関わらずみんな誤解している節があるけれど、フレッチャー教授は気分でパワハラしているわけではない。いちおう主人公の成長を見越してその都度(彼なりに)戦略的にプレッシャーをかけている。
最初の練習で椅子を投げてきたのも、十代のチャーリー・パーカーがセッション中にドラムのシンバルを投げつけられた故事に因むし、主人公が以前所属していたバンドのメインドラマーを連れてきたのもフレッチャー自身で語っているとおり「主人公の発奮材料として」だろう。主人公がメインドラマーの座を手に入れるきっかけとなった大会での譜面の消失事件も、フレッチャーが仕組んだのではないかと思われる。フレッチャーは本気で主人公の素材に惚れこんでいたのだ。
ところが彼の戦略に主人公は同調しきれない。重要なところで寝坊しかけたり、事故で遅刻したり、無理やり舞台にあがろうとして大失態を演じたりしてしまう*2。そこまでならまだ挽回のしようがあったかもしれない。しかし、「もう終わりだ」と早合点した主人公は先生で割るフレッチャーを公衆の面前で殴り倒してしまう。ついに彼はフレッチャーの意図を理解できないまま(理解しろというほうが無理なのだが)退学処分の憂き目をみる。
いっぽう、フレッチャーも主人公の密告で学校を追われてしまう。フレッチャーは主人公を許せなかった。密告した事実のみによって憎んだわけではない。フレッチャーの教育理論を解せず、主人公がみずから素材を台無しにしてしまったことと、フレッチャーというジャズ界に必要とされている教育者のキャリアを未完のまま終わらせたこととで、二重にも三重にも度し難かった。フレッチャーはバーで主人公で再会したとき、「ジャズは死んだ」と嘆く。フレッチャー視点では、そのトドメをさしたのは主人公だった。主人公は一個人の人生ではなく、ジャズそのものを殺してしまった大罪人だ。
だから、というべきか。フレッチャーは捨て身となって主人公へ復讐しにかかる。あの復讐劇の後先考えなさは脚本の不備としてよく指摘されるところだが、実のところフレッチャーは後先なんてどうでもよかった。第二のチャーリー・パーカーを育てるという目標を潰されたその日に彼の音楽人生は死んだも同然だったのだ。彼はある意味で鬼教師を演じていたといえる。身体を鍛え、二の腕をたくましくし、黒い半袖シャツに黒のジャケット、黒の帽子という超絶ダサい三点セットに身を包んだ。その衣装でもって、生徒たちを威圧し、与えるプレッシャーを最大化してきた。
その彼が生の姿をさらけ出して全人生をぶつけた場があのラストの演奏会だった。主人公はフレッチャーの理論や理屈がとことん理解できない。理解できるふりをしたために、壊れてしまった。彼もまたフレッチャーの要求した「理想のジャズマン」を演じようとして、挫折した。
彼とおなじくフレッチャーの要求に答えようとしたある先輩は途中で自死を選ぶ。フレッチャーへの憎しみを内に抱えたまま、自爆してしまったのだ。
だが、主人公の憎しみは常に開いていた。フレッチャーに罵倒されながらドラムを叩くとき、彼は常にすさまじい凝視でフレッチャーを睨んでいた。先生の期待に答えようとしているのか、先生を殺したがっているのか、自分でもよくわからないままに睨めていたのかもしれない。
ラスト、彼はフレッチャーの要求した「理想のジャズマン」を捨て、生の己だけをもってドラムセットに復帰し、オリジナルな殺意でフレッチャーを睨む。フレッチャーも睨み返す。
とてつもなく強烈な視線の衝突が、彼ら二人の間、観客とスクリーンの間に憎しみだけない別の何かを生じさせる。そこで初めて、テンポが合う。それがこの映画の快楽なんだと思う。

- 発売日: 2015/10/21
- メディア:Amazonビデオ
- この商品を含むブログ (7件) を見る
アダム・マッケイ監督『マネー・ショート』二回目。
論理的な正しさは力だ。ところがそれはむき出しの力でもあるので、運用を間違えれば不幸になる。問題なのは、正しいんだから正しいはずだろうというトートロジーにいう陥ること。
劇中でサブプライムローンの崩壊を予測した人々は誰もが不安に陥る。「自分たちの予測は本当に合っているのか?」。論理や理屈でいえば、サブプライムローンはかならず破綻しなければいけないし、事実データも破綻の前兆を示しつつあった。しかし、ウォール街も世界もあいかわらず脳天気に回っていて、誰も世界が滅ぶなんて信じていない。滅ぶぞ、というと一笑に付される。創世記のノアの心持ちだ。
ところがメインのキャラのうち三人だけ滅亡を最初から確信している人間がいる。
一人はクリスチャン・ベイル演じるアスペルガーの天才トレーダー。もう一人はライアン・ゴズリング演じるドイツ銀行の保険担当者。もうひとりはブラッド・ピット演じるプレッパーの元モルガン・スタンレー証券マン。
ベイルは終始自分の予測の正しさを疑わない。誰も調べないサブプライムローンの返済率を逐一調べあげ、その他あらゆる努力を払ったすえに崩壊を確信する。それが論理だからだ。彼はその論理に絶対の自信を持っている。他人がグリーンスパンなどのビッグネームをひきあいにだして否定しにかかっても、彼は揺るがない。ベイルとグリーンスパンなら、間違っているのはグリーンスパンだから。
その正しさの確信を、彼は運営するファンドの顧客にもおしつける。だが、顧客はいくら説明されてもベイルの正しさがわからない。そもそも説明を聞く気がなく、世間の雰囲気が崩壊しないと言っているから、崩壊しないと思い込み、崩壊に賭けようとするベイルをキチガイ視する。いますぐ賭けをやめろとメールや電話でしつこく催促してくる。
ベイルは自分がなぜ拒絶されるのかわからない。自分は顧客のためになることをやっているのに、なぜ彼らは感謝するどころか自分を罵って資金をひきあげようとするのか。ベイルは、資金引き上げを阻止するためにヘッジファンド運営者としての権限を利用して、資金の移動を停止する。それはベイルにとって思いやりですらあった。しかし、顧客はますます激怒する。
すべてが終わったあと、ベイルはファンドをたたむことを決意し、顧客にむけて別辞のメールを書く。「私はこの二年間苦しんできました……」
彼が「苦しみ」は、未曾有の経済危機を逆手に取って大儲けしようとしたことについての罪悪感ではない。サブプライムローンの破綻を信じきるべきなのか、どこかで手をひくべきなのか悩みぬいたことでもない。
彼は自分が尽くしているはずの人間から、正しい愛情のレスポンスを得られなかった。関係を築けなかった。誰にも理解してもらえず、孤独だった。圧倒的に、絶対的に、正しかったはずで、現に正しかったのに。
元証券マンのブラッド・ピットも似たような孤独を抱えていた。彼は盗聴を恐れて複数の電話回線を所有し、間違った回線から間違った人物がかけてきた電話には絶対でない。食べるものは自分で育てた有機野菜だけ。世界は破滅しつつあると信じている。
彼は田舎から出てきた若いファンドマネージャーたちに助力する。空売りが成功したあと、ファンドマネージャーたちはブラッド・ピットにおそるおそる「しかしなんで僕達なんかに協力してくれたの?」と尋ねる。
ブラッド・ピットはぶっきらぼうに「大儲けしたかったんだろ?」と応える。
おそらく、そこにはシンパシーがあったのだ。世界が滅びつつあると叫んで、誰にも信じてもらえなかったもの同士のシンパシーが。ベイルと違い、彼には仲間がいた。一緒に世界の破滅を信じてくれる仲間がいた。そういう点では、確信をもてずにさまよいつづけたスティーブ・カレル演じる怒れるファンドマネージャーもおなじだ。
正しさそれ自体は世界との関係を保証してくれない。
それを銀行マン、ライアン・ゴズリングはよく了解していたので、あえて裏方に回り、わかってくれそうな人間にだけ利を説いた。
正しさとは力なり。力とは、うまく付き合っていかなくちゃ、ねえ。
今週のトップ5:『戦争は女の顔をしていない』、『アーロと少年』、『リリーのすべて』、『ビッグデータ・ベースボール』、『殺人を無罪にする方法』、『サンキュー・スモーキング』
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ『戦争は女の顔をしていない』

- 作者:スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ,三浦みどり
- 出版社/メーカー:岩波書店
- 発売日: 2016/02/17
- メディア:文庫
- この商品を含むブログ (3件) を見る
小話をしてあげるわ……泣き出さないために、話すわね。
(p.469)
たしか『ペンギンの憂鬱』の解説だったの思うのだけれど、スラヴ民族というのは小話(アネクドート)の民であるらしい。WWIIに参加した女性兵のインタビュー集である本書もひとつひとつがきちんと小話的な結構をもって語られている。著者による添削や編集を介しているであろうにしても、短編小説家*1二十ページ三十ページを費やしそうな話を、半ページから数ページ程度で語り尽くしてしまうのは神業以外のなにものでもない。
ソ連は第二次世界大戦において女性兵を前線に動員した唯一の国家だった。
その規模は百万人を越すという*2。『戦争は女の顔をしていない』ではインタビューを彼女たちの配属先が逐一記されてある。多くは衛生指導員や看護師、通信係、洗濯係といった支援任務(といっても戦闘になれば砲火をかいくぐって負傷者を運ばなければならない)だが、狙撃兵*3、戦車兵、高射砲兵、パルチザンの戦闘員、戦闘機乗り、爆撃機乗り、はては男装して軍艦に忍びこんでソ連初の海軍将校となったアン・ボニー*4みたいな人物までいる。
彼女たちのほとんどは志願兵だった。徴兵担当官たちは女性を軍にいれることを渋りがちだったため、彼女たちは何度も徴兵事務所を訪れて自分たちの希望を訴えねばならなかった。配属先も様々なら、志願する理由も多様だった。午後にスイパラに寄る高校生みたいなノリで友達とつれだってやってくる人もいれば、家族を虐殺したドイツに対する復讐心に身を焦がした人もいる。徴兵されそうになった知り合いの代わりに名乗りをあげた人もいる。愛国心から、国民としての義務感から素朴に飛び込んでくる人もいる。スターリンとレーニンを敬愛する熱心な共産主義者もいる。スターリンに父親を奪われた人もいる。出身も幅広い。モスクワ、ウクライナ、カリーニングラード、シベリア、聞き取りを行った著者自身はベラルーシの人。
悲惨な話もあれば、愉しい話もある。どちらかといえば後者が心に残る。彼女たちは「兵」でありつつも「女性」としての自分たちを譲らなかった。個人や個性が圧搾される戦場にあって、自分たちの核を忘れない人たちがいる。それは強さだ。切実さに負った強さだ。
飛行学校で女性は全員髪を短く切りそろえるように命じられたのにもかかわらず、断固として自分のおさげを守ろうとした後の英雄パイロット、軍隊の規律や軍独特の言い回しがどうしても身につかなくて上官に対して奇妙な言葉遣いをしてしまう兵士、ながらく手に入らなかった女性用下着が終戦間際にやっと支給されたのが嬉しくてわざと胸元をはだけて着こなす衛生指導員。
隠し持っていたイヤリングを上官に見咎められた通信班の軍曹はこう言う。
中尉は「戦争では兵隊が必要なんだ」と言っていました。兵隊であることが必要だったんです。でも、私たちはそのうえかわいい子でもいたかった……戦争中ずっと脚を傷つけられたらどうしようもないということばかり心配していました。私は脚がずっときれいだったの。男の人ならどうってことないでしょ? 脚がなくなったって、それほど恐ろしくはありません。それでも、英雄だし、立派にお婿さんになれます。でも、女性が不具になったら、もう将来は決まってしまうんです。女性としては終わりです。
(p.286)
1940年代のソ連を生きる彼女たちにとり、女性であるという自認を失うことは、物理的に死ぬことと同義だった。しかし同時に兵士であらねば物理的に死ぬ。その間で彼女たちは奇妙かつ巧みにバランスをとっていた。
ドイツのある村でお城に一泊した時のこと。部屋がたくさんあって、すばらしいものばかり! 洋服ダンスの中は美しい服で一杯。一人一人がドレスを選びました。私は黄色のドレスと長い上衣。言葉では伝えられないほどきれい、長くてふわっとしていて。綿毛のよう。もう寝る時間で、みな疲れ果てていた。それぞれ気に入ったドレスを着たままたちまち寝入ったわ。私はドレスを着てその上に長い上衣も羽織って横になった。
ある時は無人になった帽子屋で帽子を選んだこともあるわ。ちょっとでもかぶっていたかったので、座ったままで寝たり、朝起きてから……鏡をもう一度覗いたり。
それから、みんなは帽子を脱いで、また自分の詰め襟の軍服を着てズボンをはいたんの。何もとろうとはしなかった。移動には針一本だって重たいのよ。いつものとおりスプーンをブーツの脛のところに突っ込んで出発……
(p292)
もちろん、悲惨な話もたくさん載っている。愉しい話の十倍は載っている。そもそも戦場の笑い話なんて陰惨な悲劇と裏表だ。
しかし本当に悲惨だったのは戦後だ。男たちと戦友になり、国家を救ったはずだった彼女たちは男たちからも他の女たちからも「戦場に行った女」「どうせ売春婦まがいのことをしていたんだろう」と差別されるようになる。*5くわえて、戦場で負った心身の傷。多くの帰還兵たちは結婚できず、また結婚しても安定的な家庭を築けるものは多くなかった。彼女たちは戦場に行ったことを恥じるようになった。
女性兵たちは国家の記憶から忘れ去られ、彼女たち自身も恥の思いからそれに積極的に加担していった。
著者のアレクシエーヴィチが元女性兵たちの聞き取り調査始めたのは終戦から三十年以上経ってから、本が出版されたのはペレストロイカ期になってからだ。十六〜十八歳くらいだった少女たちも老年にさしかかっていた。
「わたしたちは消えていってしまいます。あとに続くのは誰なんでしょう? わたしたちがいなくなったら何が残るんでしょうか? わたしは歴史を教えています。年老いた女教師。わたしが憶えているだけでも、歴史は三回書き換えられました。わたしは三つの異なる歴史の教科書で教えてきたのです。
あたしたち*6が死んだあとでは何が残るんでしょう? あたしたちが生きているうちに訊いておいて。あたしたちがいなくなってから作り事をいわないで。今のうちに訊いてちょうだい。
(p.41)
『アーロと少年』
The Good Dinosaur Official US Trailer 2
ピクサー以前のディズニーのクリシェ(特に『ライオンキング』)*7を物語的及び技術的にものすごく洗練させて語り直したような感じで、プロット単位での新規性には欠けるものの、映像や細部はとにかく新鮮。特に雲と水の表現は「実写みたい」じゃなくて「実写だろ」レベル。恐竜アニメのくせに出てくる恐竜がせいぜい三種十数匹程度で、画面のほとんどはアーロと人間のガキが占めているんだけれど、それでも全然すっかすかで貧弱に見えない豪華さは地味に特筆に値する。予告で流れて『ルドルフとイッパイアッテナ』のカキワリ感溢れる背景と較べてしまってすこし哀しくなった。まあピクサーとかディズニーとかイルミネーションとかの技術と比べるほうがおかしいんでしょうけど。
主人公のアーロの家が西部劇によく出てくるような寂しい場所にある一軒家みたいだな、と思っていたら途中からほんとに西部劇になる。テーマ的にも甘ったれたガキが一匹で外の世界に放り出され、赤ん坊を守りつつロードムービーして一人前の「男」になって帰ってくる話だからそれっぽいといえばそれっぽい。親やオトナになる物語ってのは『トイ・ストーリー』以来、ピクサー作品の一貫したテーマであるけれども、ここまでハッキリと「家族! ファミリー! 強くたくましい男!」を打ち出したのは珍しい。そこの部分とプロットのマンネリズムがピクサーのはなかで相対的に低めの評価になっている一因なのではなかろうか(去年の『インサイド・ヘッド』の記憶があまりに強烈過ぎた、ってのもあるかもしれないけれど)。
器は使い古されていて中身も一見誰でも作れそうなシチューだけれど、具には信じがたいほど気を使っている。
外に放り出されてから中盤に至るまでは画面をほとんどアーロと人間のガキが占める。人間のガキは言葉が喋れない。最初はアーロが一方的に喋ってるだけなんだけれど、言葉が通じないことを了解しだして、段々とジェスチャーでのコミュニケーションへ重心を移していくようになる。互いの家族の話をするくだりはその白眉。砂と木の枝だけであそこまでもっていけるのはなかなかどうかしている。終盤の雲海を利用した逆さジョーズにいたっては衝撃すらおぼえました。
ただまあシチューはシチュー、どれほど美味しく作ろうが鴨せいろにはならない。基本的にはスカーの出ない『ライオンキング』であって、人間のガキとの関係のオチは80年代の某アレ。*8
ピクサーにとっては脚本面での冒険だった『インサイド・ヘッド』の反動で、映像実験を試みた作品なのかもしれないけれど、個人的にはずっと『インサイド・ヘッド』方面に振っていてもらいたいんですよね。
トビー・フーパー『リリーのすべて』
見世物小屋めいた娼館の個室でガラス越しにストリップを見るリリー(エディ・レドメイン)のシーンが卓抜している。
女装を通じてみずからの女性性を覚醒させたリリーが、女性の仕草をより深く研究するためにストリップを観にいく。そこで行われるストリップというのは女性の女性的なしぐさを強調することで、男性の性欲を掻き立てるものなので、AV観てセックスの技術を学ぶような微妙なずれた感がなくもないですが、「(完全な)女になりたい」という強い欲求が女体を持って生まれついた人間よりもむしろ女性的なイメージに執着し、それを模倣したがるというのはいかにもありそうな話で、そういえばジョン・ヴァーリイの<七世界>シリーズにもそういう描写があったなと思い出すわけですよ。性転換がスナック感覚で行われる世界観で、性転換初心者は映画や小説のイメージにおける異性を模倣しがちだから男性より男性的に、女性より女性的な一種カリカチュアを演じてしまう。完全なセックスという幻想は何時の時代、どこの国にも偏在している。
リリーもそういう「完全な女性のイメージ」をゲットするためにストリップを見物します。個室に椅子が置いてあり、その椅子の真ん前に据え付けられたガラスの向こうにストリップを演じるための別の小部屋が映っている。そこにリリーにとってのイメージがある。原理としては映画と一緒です。
ストリッパーは最初、ルーチン的にしなやかな四肢にエロティックな指先を走らせつつ、ガラスの向こうの男性(リリー)の情欲を煽っていく。リリーのほうではその動作をワンテンポ後追いでなぞっていく。
この時代には当然マジックミラーなんてものは存在しませんから、ストリッパーはガラスの向こうの客が尋常ではない反応を見せていることに気づいてしまう。リリーのほうも気づかれたことに気づいて、ハッとなる。
どうなるか、とリリーも観客もハラハラしていると、ストリッパーはやおらリリーの動作を模倣しだす。模倣されたのを、模倣しかえしたわけですね。
リリーもそれにつられて扇情的に身体をくねらせる。そうするうちに、ストリッパーの動きとリリーの動きが完全にシンクロしていく。
リリーはここで理想的なイメージと完全に同化することに成功します。それはつまり、それまで揺らいでいたリリーのアイデンティティが「彼」から「彼女」へと不可逆的に切り替わった瞬間でもある。
こういう繊細なイメージの経済が全編通じて豊か。

- 作者:デイヴィッド・エバーショフ,斉藤博昭
- 出版社/メーカー:早川書房
- 発売日: 2016/01/22
- メディア:文庫
- この商品を含むブログを見る
ビル・コンドン監督『Mr. ホームズ』
Mr. Holmes Movie (Official Teaser)
探偵論映画。
探偵に必要な才能とはなにか。推理力です。推理力を構成する要件はなにか。記憶力と論理力と想像力です。
このうち、記憶力を失くした場合、その探偵はあいかわらず探偵でいられるのか。そういう麻耶雄嵩的な引き算の名探偵論の興味で観られる作品。
個人的に「探偵未満の人間*9が探偵になる」探偵小説が好きなんですが、その逆をとって「名探偵が探偵じゃなくなっていく」プロセスを描く系というのはなかなかに新鮮でした。いっぽうで、名探偵から名探偵要素を剥ぎとっていくとそこに残るのは人間なんだよ、ラブなんだよ、人間の気持ちを慮らない本格探偵はクソなんだよ、という押し付けがましい現実讃歌も多々垣間見えて、まだ「そこ」なのかよと思わなくもない。

- 作者:ミッチ・カリン,駒月雅子
- 出版社/メーカー:KADOKAWA/角川書店
- 発売日: 2015/03/27
- メディア:単行本
- この商品を含むブログ (7件) を見る
『ビッグデータ・ベースボール』

ビッグデータ・ベースボール 20年連続負け越し球団ピッツバーグ・パイレーツを甦らせた数学の魔法
- 作者:トラヴィス・ソーチック,桑田健,生島淳
- 出版社/メーカー:KADOKAWA/角川書店
- 発売日: 2016/03/16
- メディア:単行本
- この商品を含むブログを見る
カネ無し、スター無し、人気無しの三重苦を背負った負け犬メジャー球団ピッツバーグ・パイレーツがビッグデータを活用し、既存の価値観から見放された隠れた優良選手を拾いまくって勝てるようになりましたって話。
ご覧のように、『マネーボール』とだいたい同じストーリーラインで書かれている。しかし、著者の生真面目さと時代的にデータの解像度を上げざるを得なかったせいとで読み物としてのエンタメ性は『マネーボール』に劣るだろうか。*10
それでも単なる惰性で続いてるだけの「伝統」が、データによる合理的な視点からハッキングされていくのは快楽的であり『マネーボール』に負けない俺TUEEEE感に満ちている。
『マネーボール』は打撃の指標における革命だった。アスレチックスのGMであるビリー・ビーンは多少守備に難があると言われている選手でも、打撃(=出塁率やOPS)の良い選手を登用した。
これはアスレチックスが守備を重視しなかった、というよりは、できなかった、というほうが正しい。守備に関しての指標が打撃面での指標ほどの信頼性に欠けていたからだ。野球において守備で数値化されるのはせいぜいエラーと捕手の盗塁阻止率程度。*11そのうえエラーは判定する審判の主観によって判断される欠陥指標だ。ことによったら「守備範囲が広いおかげで難しい捕球を行う機会の多い野手」が「守備範囲が狭いせいで平凡な打球しかさばけない野手」よりも過小評価されるおそれすらある。
しかし、基本セットプレーで測定しやすい打撃に比べて、守備は何をどういうふうに測ったらいいのかわかりにくい。すくなくとも『マネーボール』の出た2002年時点ではそうだった。
その後、『マネーボール』革命で野球におけるデータの重要性――セイバーメトリクスが認知されるようになると、より多くのデータを集めようとする企業が現れた。その会社はピッチに精密な測定機器を設置した。それによってグラウンドをグリッド化し、選手の動きを逐一捉えられるようになり、守備面でより多くのデータ収集が可能となった。
各球団に送られるデータ量も飛躍的に増大し、一年に送られるデータ要素は2000万*12から一気に数十億に膨れ上がる。送ってくるほうはデータの活用方法までは教えてくれない。どう活かすかは各球団のデータ分析部門にゆだねられる。ピッツバーグ・パイレーツはこのデータ分析に、未開拓の「守備の解析」に賭けた。
優秀な新選手を獲得する余裕のないパイレーツは、既存の選手を用いつつ勝つという無茶ぶりを通さねばならなかったのだ。
その結果生まれたのが極端な守備シフトだった。
野手の守備位置は長い野球の歴史の中でもほとんど手のつけられていない分野だった。ときどき状況や打者に対しては極端な守備シフトが敷かれることはあったものの、ほとんどの場合は見慣れた等間隔のシフトを野手は守った。
それをピッツバーグ・パイレーツは変革した。
極端に守備陣を右へ寄せ、三遊間をがら空きにすることなど日常茶飯事となった。特定の強打者対策としてではなく、普通ならシフトを必要としない十人並みのバッターに対しても千万変化の守備シフトを敷いた。
選手たちは困惑した。
なるほど、データ上はこのバッターは右方向にゴロを引っ張りやすいのかもしれない。しかし、シフトを見てうまうまと左へ流して打ったらどうする? ヒットを防ぐどころか、単打だった打球がツーベースになるかもしれないんだぞ?
特に不満をいだいたのは野手ではなく、投手たちだった。シフトのせいで失点したら、野手のエラーではなく投手の防御率に計上される。そのせいで査定が下がったらどうしてくれるんだ。
パイレーツのデータ分析屋たちと首脳陣はどうしたか。説得した。並の苦労ではない。せいぜい大学三部レベルでしかプレーしたことのないコンピュータ・オタクどもがいくら「相手がシフトに合わせて流し打ちしようとしたとしたら、ゴロではなく凡フライになる可能性が高い」と理を説いても、プライドの高いメジャーリーガーは納得しない。
データ分析屋たちは選手の輪に積極的にとびこみ、日常での対話を通じて選手たちの信頼を勝ち得た。
守備シフト(と各種新しい評価軸)を取り入れた2013年、パイレーツは21年連続負け越しを免れたばかりでなく、ひさびさのプレーオフへ進出した。誰も予想しなかった大躍進だ。パイレーツはほとんど補強を行わず、なけなしの予算を叩いて買ったフリーエージェント選手はどれも「終わった」選手ばかり。ファンやマスコミからは「パイレーツは勝てなさすぎてやけになっている」と絶望的に批評したほどだった。ところが代わり映えしないパイレーツと「終わった」選手たちは活躍しまくった。
その後、2014年、2015年と三年連続プレーオフ進出。最低クラスだった入場者数も急上昇した。
それでも地区優勝、ワールドシリーズにまで至らないのは、やはり『マネーボール』っぽいというか。
パイレーツの人々は自分たちの守備シフト革命のアドバンテージはしばらく続くだろうと考えていた。野球界は保守的な風潮が強い。そういった人々が「データなんかで野球がわかるわけがない」とセイバーメトリクスに反撥しつづけてきた。
ところが、メジャーリーグはパイレーツの予想を裏切った。パイレーツが20年ぶりのプレーオフ進出を果たした翌年の2014年には他の球団も次々と極端な守備シフトを敷くようになったのだ。
今では「メジャーリーグの守備シフト」は日常的な光景だ。そのせいで、メジャーリーグは投高打低に拍車がかかっているというデータも出ている。
セイバーメトリクスを進化させてきたのは BaseballProspeticves.com などに代表される市井のデータオタクたちと彼らのオープンソース文化だった。データ会社も彼らのデータ利用を奨励とまではいわないまでも黙認し、その解析を通じてオタクたちはメジャー球団の中枢で仕事するようになった。
現在、データ会社の提供するデータは素人の扱える許容量を超え、提供先以外には機密とされているデータもある。
野球は変わらないスポーツだった。等間隔に並んだ守備シフトはその象徴だったといってもいい。その変わらなさが野球に対する人々のノスタルジーの根源ともなってきた。
だが、その聖域ももはや壊されてしまった。野球がこの先どう変化するなんて、もう誰にもわからない。
最適化されつづけ、進化していく野球。その果てを、ちょっと見てみたい気もする。
『殺人を無罪にする方法』一話、二話。
![殺人を無罪にする方法 シーズン1 Part1 [DVD] 殺人を無罪にする方法 シーズン1 Part1 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51h2Z7azBOL._SL160_.jpg)
- 出版社/メーカー:ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
- 発売日: 2016/03/02
- メディア: DVD
- この商品を含むブログを見る
アメリカのロースクールに通う大学生たちが犯してしまった犯罪の顛末と、彼らを結びつけることになる刑法入門のクラスでの日常、それらの時間軸が異なる二つの物語が並行して語られる。
なんといっても強烈なのはヴィオラ・デイヴィス演じる刑法入門の教授。「無敗」の異名をとる現役の弁護士だ。
タイトルの『殺人を無罪にする方法』(How to get away with murder)は、教授が最初の授業で行う挨拶に由来する。「授業名は『刑法入門』……でも私はこう呼ぶ。『殺人を無罪にする方法』と」
彼女はたとえ依頼人が真犯人だろうがためらわない。「勝つためならなんでもやる」と公言するバリバリのマキャベリストだ。第一話では、なんと係争中の事案を授業のトピックとして扱い学生たちに裁判に勝つためのアイディアを捻出させようとする。いいのか、それ。
勝つために手段を選ばないダークヒーロー的弁護士、というと『ダメージ』のパティ・ヒューズを思い出す。『ハウス・オブ・カード』の政治家にしろ、『サンキュー・スモーキング』のロビイストにしろ、言葉を弄する職業の人らは倫理観なんて踏みにじってなんぼ、というのがエンタメ業界にはあるんでしょうか。こうした職業に対するヒューマニズムの欠如を疑う不信感は根深い。
IAMX - "I Come With Knives" - (Official Video)
一話の最後のほうで流れる IAMX の「I come with Knives」。
ジェイソン・ライトマン『サンキュー・スモーキング』

- 発売日: 2013/11/26
- メディア:Amazonビデオ
- この商品を含むブログを見る
『サンキュー・スモーキング』はJライトマンのデビュー作。レトロで洒脱な画調に多用されるシンメトリックな構図、オフビートな笑いと、ウェス・アンダーソンに近いにおいを感じる。
彼の好きな映画のかおぶれを見てみると、直接ウェス・アンダーソンを意識したというよりは、キューブリックとジョン・ヒューズを経たもの同士の収斂進化なんだろう。ちなみにリストにはアレキサンダー・ペインの『ハイスクール白書』も挙がっていて、なんだかよくわからないが妙に腑に落ちる。
本作の主人公(アーロン・エッカート)はタバコ業界のロビイスト。タバコの安全性を訴えて、需要を守るのが仕事だが、彼はハナからタバコの安全など信じてはいない。週末には銃器業界、車業界のロビイストとレストランに集まって「自分の業界が殺している人間の数」を誇り合っている。
そんな彼が、新聞記者から「なぜ信じてもないのにこの仕事を?」と尋ねられてこう答える。
「ローンの返済のためさ。みんなそうだよ。賃貸で満足する世の中になったら、平和になるだろうさ」
生活にするのは金が必要で、金は働かなければ手に入らない。主人公もこうも訊かれる。「他の仕事をなんでやらないの?」。主人公は言う。「僕はロビイストに向いてるんだ(good at)」。
世の中の仕事の大半に大義などない。与えられた仕事だからそれをやっているにすぎない。他の仕事でもいいのなら、今の仕事でもいいはずだ。
タバコによって日に数百単位で人が死んでいく。それは主人公にとって不可視の死だった。肉親でも友人もない、関係ない人の死だった。だからこそ目をそらしてローン代を稼ぎ続けられた。
凡庸な小悪人である彼がゆらぐ瞬間が二つ、訪れる。
一つは、長年マルボロの広告塔をつとめたのち肺がんを患い、タバコ会社を訴えた男の説得のためにその人の家を訪れたとき。男は自分の病は発覚したときに、株主総会で「良心を鑑みて、タバコの宣伝をやめるべきではないのか?」と会社に訴えたが、会社は逆に「あなたのご病気については同情するが、タバコが原因という証拠はない」として切り捨てた。また、広告塔だった事実ももみ消されそうにさえなった。
男はタバコ業界にいた人間だ。それも広告宣伝という、主人公と同じ分野のプロフェッショナル。主人公はそこに、未来の自分の姿を見る。
もう一つは、議会に召喚されたときにライバルであるタバコ規制派の議員からこう質問をなげかけられたときだ。
「あなたにはお子さんがいますね。その子が十八歳になったら、あなたは彼にタバコを吸わせますか?」
主人公は言葉に詰まる。いつもなら「ええ、もちろんです」とぬけぬけと答えるはずだが、いざ当人に見られている前でその質問をつきつけられると答えられない。
彼は倫理や道徳を欠いたサイコパスなどではけしてなく、だからこそおそろしい。
*1:戦争から長く遠くへだたって人々からすればファンタジックで痛みに満ちたエピソードの数々と叙情的な文体は、カレン・ラッセルやジュディ・バドニッツといった現代アメリカ奇想文学最前線の作家たちを思い出させる
*2:訳者あとがきより
*4:18世紀の女海賊
*5:この「戦時における女性の社会的地位の向上と終戦に伴うバックラッシュ」は、おなじく第二次世界大戦中に銃後の人手不足を解消するために多くの女性が社会進出を果たしたアメリカの状況にかぶるところもある。アメリカと異なったのは、その経験がその後の社会運動への布石とならなかったことだ
*6:原文ママ。同一人物の発言なのに一人称が揺らいでいるのは原書でもゆらぎがあったからだろうか?
*7:あとピクサー以後だけど夜に光る虫飛ばせばキレイだよね、っていうのは『ラプンツェル』を想起する
*8:あれがホモ・サピエンスの台頭を表しているのだとしたら、同時に食物連鎖のヘゲモニーをめぐって人間と恐竜がいつかは敵対するであろう末路をも暗示しているということでもあって、ますますそれっぽい
*10:ルイスは「キャラ」を作るにあたってのエピソードの取捨選択に長けている
*11:ちなみに日本プロ野球機構で公式に公開されている野手の個人成績データは打撃・走塁のみで、エラーすら含まれていない。